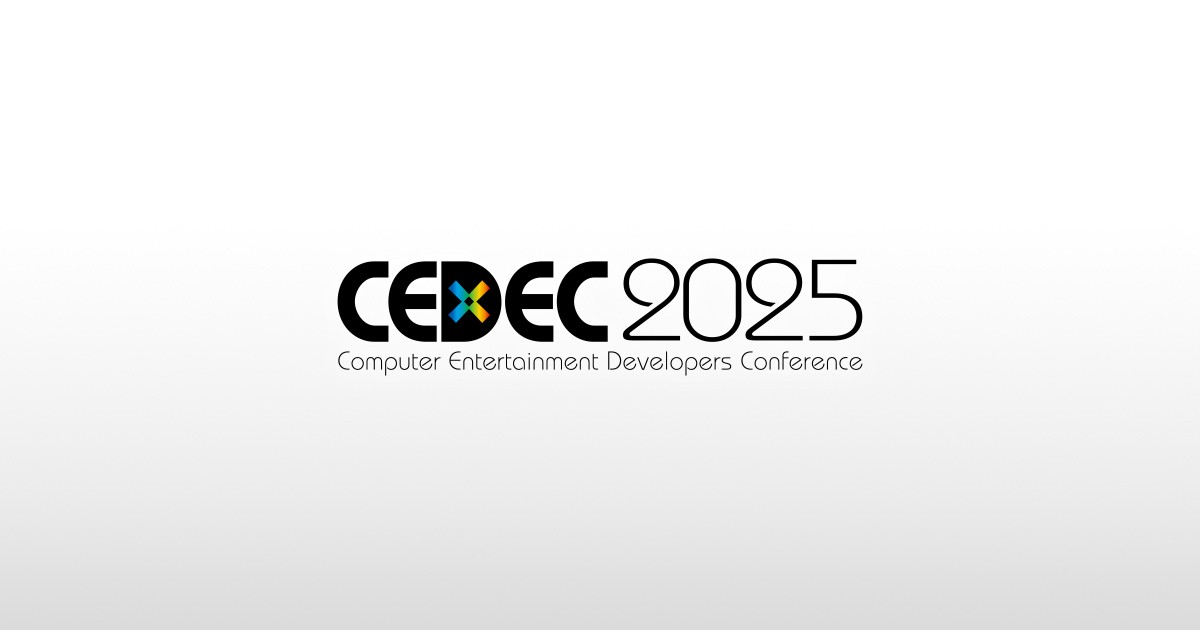どうも、ねへほもんです。
今日は自分史上最高に有意義な形で有給を消化できました。
こちらのイベントに行ってきたのでその報告です。
1.CEDECとは?
このブログの読者の方は、WIXOSSプレイヤーはじめ一般の方々が中心かと思います(僕もですが)ので、まずはCEDECとは何かからご説明します。
公式サイトの紹介文は以下の通りです。
「コンピュータエンターテインメント開発者を対象とした、 ゲームに関する技術や知識を共有する国内最大級のカンファレンスです。 毎年3日間にわたって開催し、エンジニアリング、プロダクション、ビジュアルアーツ、 ビジネス&プロデュース、サウンド、ゲームデザイン、 学術研究の7分野で約200ものセッションが行われます。」
簡単に言うと、同業者同士でゲームの開発の舞台裏を紹介し合って、お互いの今後の仕事に役立てましょうという会です。
で、ここで一つ問題なのですが、、、
「コンピュータエンターテインメント開発者を対象とした」
【悲報】ねへほもん、対象者ではない
ゲーム開発?したことないです。
ま、まぁ、、、ちゃんと受講料払って受けているのだから許してください。
物心付いてからはゲーマー一筋30年で生きていると、ゲームのプレイだけでなく、開発側にも興味も出てくるものです。
違う視点からゲームを見ることで理解が深まり、作り手へより深い敬意を持てるようになるというのも、ゲーム業界にとって意義のあることではないでしょうか?
近年はソシャゲが出てきて、プレイヤーと運営が身近になるとか、サービス終了のリスクを気にしてプレイヤーがセルランという運営側の要素を気にするとか、メンテ後にバグ祭りでたまに炎上するとか、プレイヤーと作り手の距離が縮まっていると思います。
更にプレイヤー側が作り手を深く知る場としてもCEDECは有意義ではないのか?
今日の体験を以下でご報告するので、ゲーム業界外の方でも、興味を持つ仲間が増えてくれると嬉しいです。
2.6限まで時間割を組もう!って大学生かな???
今日の体験記の前にもう一つご説明を。
受講する講義のお話です。
こちらは公式サイトのタイムテーブルですが、22~24日の3日間開催されており、受講する日のチケットを購入すれば、その日は1日中好きな講義を受講できます。(僕は有給消化勢のため24日のみの受講でしたが、3日間フリーパスもあります)
第1会場から第13会場まで、毎コマ13種類の講義があるため、興味のあるものがきっとあるはずですし、今回はAI、次はグラフィック、その次はゲームデザイン・・・とか多様な種類をバランスよく受講することもできます。
僕はタイムテーブルを見ただけで感動したのですが、ゲームって本当に色々な役割の方が関係しているのだと再認識しました。
まずはキャラをデザインしないと誰も登場しません。そのキャラも棒立ちではなくモーションを付けて動かさないといけません。動くとサウンドエフェクトが必要ですし、音と言えばBGMも必要です。
また、シナリオやゲーム全体の構成を考えないといけません。ただ全体像を決めて終わりではなく、個々のステージや敵味方のパラメータを設定しないといけません。更に、プランやデザインを作って終わりではなく、それを実装するプログラマーも必要です。
部外者の素人がパッと思いつくだけでもこれだけの機能が浮かぶのですから、裏にはもっと多くの方が関与されています。
そりゃぁ毎回13種類の講義ネタくらい出てきますよね。
昔は子供の遊びなんて言われていたゲームですが、今やeスポーツとかクールジャパンの文化と言われ地位が向上しました。
様々な方が技術を高め、アイデアを練り、協業して生まれる産物なのです、評価されて当然ですし、ゲーマー一筋30年という経歴に誇りを持てると感じました。
3.CEDEC体験記
1時間目「モンハンPの基調講演」
13種類から選べるとお伝えしましたが、最初は1種類のみです。
それもそのはず、
モンハンシリーズプロデューサー
の基調講演なんて有難すぎます。
他の講義を聞いている場合ではありません。
僕はアクション音痴過ぎるので未プレイで、モンハンといえば中学の卓球部で、同級生が部室でサボってPSPで遊んで没収されていた記憶が残っている程度ですが、それでも日本を代表する名シリーズのお話を聞けるのは光栄でした。
講演自体も未プレイ勢にも優しく、最初はオンライン環境が弱いからマルチプレイの実現から課題だったんだよという初代の昔話から始まり、様々な機能が追加されグラフィックが綺麗になり、最新のワイルズまで進化を遂げる過程を分かりやすくご説明いただきました。
特に印象的だったのが、各タイトルの進化の過程を辿るだけでなく、PSPを持ち寄って「一狩りしようぜ!」みたいなイベントの開催・コミュニティの形成についてもお話しされていたことです。
マルチプレイという形式上、友達の紹介でどんどん広まっていったという発展の経緯を辿ってきたこともあり、ただ開発側から一方的に製品をリリースして終わり、ではなくシリーズファンの方を大事にされ、新たなファンを開拓する努力を続けられたことが伝わってきました。
撮影NGだったため画像等で感動をお伝えできないのは残念でしたが、非常に感銘を受けた講演でした。
2時間目「AIエージェント」
1~3会場は先ほどのモンハンPこと辻本氏の講演のように、大きな会場で大衆向けに華やかな話をする講義が中心なのですが、小さめの会場でマニアックな話を聞くのも一興というものです。
ゲーム業界の将来という意味では、個人的にはこの講義が一番興味深かったです。
ゲームにおけるAIエージェントとは、ゲームの世界に踏み込んだ時に世界観や操作方法等のチュートリアルをサポートしてくれる存在です。
チュートリアル自体は現代のゲームにも存在しますが、それはあくまで一本道の体験会で、とりあえず攻撃ボタンを押してみよう、次にスキルを使ってみよう、最後に必殺技だ!みたいに言われた通りに操作して覚えるだけです。
そうではなく、プレイヤーが最初から自由に操作して、色々なボタンを押しながら理解を深めつつ、詰まった時にAIエージェントから的確なアドバイスをもらう形式の方が、プレイヤーが自らの試行錯誤でゲームを理解する達成感を得られるのではないか、そういう目的でAIエージェントを開発されたそうです。
この講義を聞いた時にパッと浮かんだのが時のオカリナのナビィです。
ナビィも旅の随所で操作方法を教えてくれはしましたが、更に気の利いたタイミングでアドバイスをくれるとか、上の画像のお気に入りの場所のように、無関係な話題でも応答してくれるようになれば、よりAIエージェント、ひいてはゲームの世界観自体をもっと好きになれるのでは、と思いました。
ChatGPTを用いて妖精型のAIエージェントが応答するという近未来の発表内容自体も衝撃的だったのですが、その後の実験に関する説明も印象的でした。
企業は単に凄そうな技術というだけでは開発や実装にGoサインを出しません。
新たな技術の導入により、プレイヤーの満足度が向上し、ゲームのプレイ時間が伸び、最終的には企業の利益になる仕組みでないと実用化には至りません。
そういう意味では、AIエージェントを導入したことによる効果測定も重要です。
また、効果測定により期待通りの結果を得られなかった場合でも、AIエージェントの導入を諦めるのではなく、AIエージェントの運用を工夫するとか、追加開発によって不満点を改善できるかもしれません。
効果を測定して、AIエージェント導入前と比べて有意に改善されたかを評価するという話を聞いて、統計学に基づいた学術的な取り組みで、こういう話を聞くのは大学以来だなぁと感じました。
まだチュートリアル部分だけで、一部のユーザーにテストしただけの段階のようですが、VRデバイスを付けたメタバースのユーザーでもテストされたようで、着実にソードアートオンラインの世界が近付いているなと期待が持てました。
SAOにもユイというAIのキャラが居ましたし。
昼休み
2時間目が終わると1時間程度の休憩がありますが、そこでも楽しめる要素は盛り沢山です。
会場には交流ラウンジという場所があり、各企業が出展で自社の製品を紹介するとか、実際に体験してもらうとか、参考書籍を売るコーナーとか、無料でお茶とお菓子が支給される(昼飯は外出せずにお菓子で済ませました)とか、講義以外にも色々あって驚きました。
こちらは、講演後に登壇された方と興味を持った一部の方が、延長戦として色々質疑応答できるコーナーです。
業界人の集まりですから、実際に自分の企業に導入したらどうか?みたいなディープな話も可能です。
書籍コーナーでお土産を買いました。
Unreal Engineは有名なので聞いたことがありますが、オープンソースで誰でも使えるとは知りませんでした。
全く予定が無くて困っていましたが、お盆休みの格好の研究材料ができました。
僕もユーザー体験コーナーにお邪魔しました。
こちらは「首掛け型ウェアラブルデバイスで変わるトレーディングカードゲーム配信」という出展で、WIXOSSはじめTCGガチ勢の皆さんは興味を持たれると思います。
元々は工業用に使用されていた製品ですが、出展者の方の個人的な趣味繋がりでTCGの配信にも利用されたようです。
デモとしてポケモンカードの大会動画を見せてもらいましたが、対戦卓だけでなく手元を映せる分、よりプレイングの選択過程まで詳細に分かり、ガチ勢目線ではトッププレイヤーの思考を知ることができるのは有益だと思います。
WIXOSSの大会にも導入したら面白いんじゃないですかね~~~?(チラッ)
なお、僕には某APという強力な知り合いが居るので、出展者の方の名刺を頂いてAPに繋げておきました。実現するかは知りませんが、ずんだもんコラボ(酒の席で僕が提案したネタが実現)のように首を長くして待ってます。
3時間目「アストロボットで学ぶレベルデザイン」
僕は非常に恥ずかしいことに、レベルデザインという単語の意味させ知らずに講義を聞きましたが、講演者の方のプレゼン能力が高すぎて今日の講義の中で一番分かりやすかったです。
講義では、上のような画像を用いて実例でレベルデザインのポイントに触れた後、その後毎回デモプレイ動画を見せる流れで解説されました。
本当に毎回デモプレイ動画が入ったので、非常に分かりやすかったです。
レベルデザインとは、アストロボットだとステージ設計等を行う役割なのですが、上の画像だとプレイヤーがどういう導線で動くかな~というのは青い線で想定して、それならその導線に沿って飛び越える段差を置くとテンポよくプレイできるとご説明されていました。
ゲームはボス戦のように歯ごたえある部分に集中できるよう、他はストレスなくテンポよく進められることが重要なので、一見地味ですがレベルデザインの仕事も快適なプレイを裏から支えるのだと理解できました。
また、単にストレスフリーに進めるだけでなく、一部で隠し要素&ご褒美を入れるなど、プレイヤーが達成感を得られる要素を織り交ぜることも大事とおっしゃっていて、レベルデザイン1つを取っても奥が深いのだと実感しました。
何より、経験者ほど長年の勘で済ませがちなレベルデザインの仕事を、30個のポイントにまとめて言語化し、動画やアストロボットのキャラを用いて分かりやすく資料にまとめ、聴衆に分かりやすくプレゼンする講演者の方の能力の高さに衝撃を受けました。
4時間目「揺れもの表現&AIローカライズ」
単なる講演だけではなく、スポンサーセッションとして企業の製品を紹介するセッションもありました。
1時間で2つのセッションを半分ずつ開く形式だったので、まとめてご紹介します。
前半は揺れものの表現に関する回で、マントやスカート等の揺れる表現に関する開発内容の紹介でした。
単に物理法則に従って揺らすだけではなく、時にはゲームらしく誇張して表現した方がインパクトが出る場合もあります。
また、実務上の大きな問題の1つとして、
上の画像の「ばね拘束がない場合」のように、スカートから脚がはみ出す等の表現が破綻する問題もありました。
昔のバグまみれのゲームとか、RTAのショートカット開発に見られる現象ですね。
また、後半はゲームを海外展開する上での翻訳の話でした。
日本で普通にゲームをプレイする上ではあまり意識しませんが、こういう所まで講義のネタが転がっている辺り、本当にゲームの業界は奥が深いですね。
ちなみに、僕はこの講義を聞くために「神魔狩りのツクヨミ」をプレイしました。
まぁ、講義だけの目的というよりは、
・メガテンテイストのイラスト
・ローグライクカードゲーム
・AIによるカード生成
と、挑戦的な要素を多く含んだ意欲作で元々興味があったという理由の方が大きいですが。
単なる翻訳だけの問題ではなく、上の画像のように、英語だと文字数が多すぎて欄外にはみ出すというゲーム特有の問題もあります。
そのため、単に日本語の単語をExcelシートに列挙して機械翻訳するだけでは不十分で、今回のプレゼンのように、スクショを見ながらAIに翻訳させると見栄えも良くなりますよ、という内容でした。
翻訳の世界まで技術者が工夫を凝らすとは、、、ゲームの世界は本当に奥が深い。
5時間目「数学」
最後は3時間目のような、素人でも理解できる題材にしようと思っていたので、最後に負荷を掛けようと数学の講義を受けました。
その結果、数分意識が飛びました。申し訳ありません。
ただ、講義の内容は学問としての数学としては初歩の内容で、実用的な側面を重視し、ゲームプログラマにとって関連の深い題材だったので、実務者にとっては有益だったと思います。
まずはゲームプログラマに関連する数学の領域がロードマップで示されました。
うーん、多すぎぃ。。。
高校は理系だから数学ⅢCまで履修したし、大学でもラクランジュの未定乗数法とか一部は聞き覚えがあるけど、まぁ覚えてないです。
ただ、分かりやすく解説しようと工夫はなされており、微分の傾きからズレを最小にする極小解を求めるという初歩の初歩から解説してくれたので理解できました。
「部屋の四隅にライトを設置し、ライトの明るさを調整することで、キャラクターの明るさを最適に調整する」という例題であれば、ライトの明るさが上のグラフでいうマテリアルパラメータに該当します。
人間が手作業で試行錯誤するなら、四隅のライトの明るさを少しずついじって、目標とのズレが拡大してしまったら逆方向に調整し、ズレが縮小したらその方向に少しずつ調整するという流れで調整しますが、それを数学的に行う時に微分の考え方を用います。
と、ここまでは感覚的によく分かるのですが、実務上は
・極小解が複数ある場合(上のグラフでいうと、左にも極小解の谷底が存在するが、ズレが最小になる訳ではない)
・変数が大量にある場合(ライトが4つあれば変数は4つ、実務はもっと多い)
・「部屋の明るさを変えると画像がどう変わるか?」「画像が変わるとプレイヤー視点の見た目が改善されるか?」という2段階の最適化問題を扱わないといけない
という、色々な問題があるので、ド基礎の話だけでは足りず、どんどん応用的な話に移ったという経緯です。
で、その辺で数分意識が飛んだしまいましたとさ。
10年以上ぶりの数学の講義でしたが、こういう学術的な話を聞けたのも貴重な経験でした。
次は最後まで起きるのが目標です(目標ひっく)
6時間目「スト6のまねもんくん」
難しい講義を乗り越えた(?)後は、最後は素人向けのキャッチ―なお話を聞いて締めることにしました。
ストリートファイター6をプレイされた方ならご存知かと思いますが、いかにも現代的な目玉機能である「まねもんくん」の裏話です。
まねもんくんとは、ランクマッチのランク帯別とかプレイヤー自身の過去のプレイ内容を学習させ、とあるランク帯の平均的なプレイヤーや自分のコピーと戦えるようにした対戦用AIです。
もう一人のボク!と戦えるということですね。
アクション音痴の僕は、例によってストリートファイターも未プレイではありますが、まねもんくんの機能は話題になったので存在は認知していました。
最初は学習過程を分かりやすく伝えるデモ動画として、
①全く動かないAIに対して波動拳を連射する
②次の対戦ではAIが学習して波動拳を連射してくるので、ジャンプ攻撃で避けながら攻撃する
③次の対戦ではAIがジャンプ攻撃を仕掛けてくるので、対空攻撃で迎え撃つ
といったように、素人AIがボコボコにされながら鍛えられる過程を解説してくれました。
で、次は実際の学習の様子として、ランクマッチのリプレイ動画を学習用に加工する方法を解説されました。
「体力、必殺技ゲージ、位置、相手との距離、状況」をタグとして、それらの状況下で学習対象となるランク帯のプレイヤーがどういう行動を取ったかを学習するという流れです。
特定の条件下で、上のランク帯の人ほど適切な行動を取るので上手いAIとなり、下のランクだと僕のように何も考えずバーサーカー特攻するデータを学習して下手なAIになるという訳です。
機械学習においては、単にAIにデータ(スト6でいうとプレイヤーの行動)を食わせるだけでなく、そのデータに関連する背景情報もタグ付けする必要があり、かつデータは数値等の客観的な指標である必要があります。
格闘ゲームのデータを数値化するのは難しいのでは?と思いましたが、上の画像のように7つの主要要素に分解すれば、数値に落とし込めるんだなと納得しました。
後は、スト6ではまねもんくんと対戦できるだけではなく、対戦後にAIによるプレイの分析コメント(〇〇は出来てたよ!〇〇が出来るようになるといいね!)も貰えるので、コメントの生成方法についても解説されました。
随所でスト6の対戦動画を用いて解説いただいたため、アストロボットの回と同様非常に分かりやすく、格闘ゲームにAIを導入するという革新的な試みを理解でき大満足でした。
個人的に印象的だったのは、「強さよりもらしさを意識した」と何度も強調されていた点です。
対戦用AIと言えば、僕にとっては将棋が一番身近なのですが、将棋だと最強や真理が追究されがちだったので、らしさを再現するという視点は新鮮に感じました。
確かに、人間が太刀打ちできないような最強のAIを再現するだけがAIの活用方法ではないはずです。
「もう一人の自分と戦いたい!」「ランクマッチに飛び入りするのは人間相手だと気が引けるから、まずは同じレベルのAIと対戦したい!」「開発者や有名プレイヤーの分身と戦いたい!」など、ゲームをより深く楽しむ要素として対戦用AIを活用する可能性は色々存在します。
将棋でも、もう一人のボクと対戦するとか、過去のレジェンド棋士のコピーと対戦するとか、実現できたら胸躍るに決まっています。(僕が知らないだけかもしれないので、既にあったら教えてください)
技術者が自分の実力を誇示するという目的に傾倒してしまうと、最強AIを開発する路線に向かいがちですが、あくまでゲームは楽しむもの、ユーザーに新たなプレイ体験を届けるという観点でAIの可能性を模索されていたことに感銘を受けました。
以上、6限分の講義プラス昼休みまで満喫しきったCEDECのレポでした。
来年も是非行きたいです!
来年はAsk the Speakerコーナーで講義後にディープな話ができるよう、Unreal Engine5に触れて開発者の気持ちを理解するとか、題材となるゲームをプレイしておくとか、自分をもっと鍛えておこうと思います。
僕のように興味を持たれた方がいらっしゃれば、来年行かれてみてはいかがでしょうか?
では(^^)/