『兄いもうと』のタイトルで1936年(昭和11年)6月21日に公開。製作はP.C.L.、配給は東宝。モノクロ。上映時間は61分[1]。 1936年度キネマ旬報ベストテン第7位。
| 監督 | 木村荘十二 |
|---|---|
| 脚本 | 江口又吉 |
| 原作 | 室生犀星 |
| 出演者 | 竹久千恵子 丸山定夫 小杉義男 |
| 音楽 | 近衛秀麿 |
| 撮影 | 立花幹也 |
| 製作会社 | P.C.L. |
| 配給 | 東宝 |
| 公開 | |
| 上映時間 | 61分 |
| 製作国 | |
| 言語 | 日本語 |
- スタッフ
- キャスト
カラー化フル動画
 あちゃ~
あちゃ~
牛鍋チェーン店"いろは"経営者木村荘平の正妻の十二男として、東京市芝区三田四国町(現在の東京都港区芝)の"いろは"本店に生まれる。幼くして父を亡くし、4歳から二代目木村荘平夫妻に育てられる。小学校卒業後、奉公に出されたが、異母兄木村荘五に引き取られて教育を受け、荘五と共に新しき村に参加。
1924年に映画界入りを果たし、1930年『百姓万歳』で映画監督デビュー。1932年、新興キネマをストライキで解雇される。
1933年、自らの独立プロダクション音画芸術研究所とピー・シー・エル映画製作所(東宝の前身)の提携で、社会派映画『河向ふの青春』を作る。

以後はPCLに所属。軽喜劇『音楽喜劇 ほろよひ人生』(1933年)などを経て、1936年、室生犀星原作の『兄いもうと』や三好十郎原作の『彦六大いに笑ふ』で進境を示し、PCLの代表的監督と目されるに至った。
1941年、満洲映画協会に移り、当地で敗戦を迎える。戦後も大陸に残って中華人民共和国の文化工作に協力。1953年に帰国してからは、『森は生きている』(1956年)など児童映画や反核映画を作り、日本共産党に入党した。
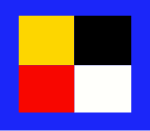 うわあ~
うわあ~
この村はただ生活するためのものではなく、精神に基いた世界を築く目的で開村されている。社会階級や貧富の格差や過重労働を排し、農業(養鶏のほか稲作[1]や椎茸栽培など)を主とした自給自足に近い暮らしを行う。労働は「1日6時間、週休1日」を目安とし、余暇は「自己を生かす」活動が奨励される。三食と住居は無料だが、私有財産を全否定しているわけではなく、毎月3万5000円の個人費が支給される[1]。

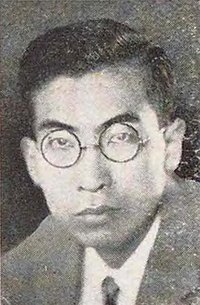 冒頭ラフマニノフ
冒頭ラフマニノフ
近衛 秀麿(このえ ひでまろ、旧字体:近󠄁衞 秀麿󠄁、1898年〈明治31年〉11月18日 - 1973年〈昭和48年〉6月2日)は、日本の指揮者・作曲家。正三位勲三等。元子爵。元貴族院議員。後陽成天皇の男系12世子孫である。
秀麿は2度の結婚の他に「妾」も持っており女性遍歴も派手であった。2人の正式な妻の他に、実子を産んだ女性が少なくとも2人おり、また、終戦後アメリカ軍に抑留された際、尋問で子供の数を聞かれ、しばらく沈黙した後「今何人いたか数えているところだ」と言い放って取調官を沈黙させたように、他にも実子誕生までに至った女性が何人かいるようである。名門貴族の家ならではの複雑な事情が入り混じっている。
なお、現在NHKの放送終了時(サインコール時)やオリンピックの表彰式の国歌など公共の場で使用される君が代は、秀麿の編曲によるものである。
晩年、秀麿はNHKの受信料を払わなかった。それはNHKがサインコールに使用した秀麿編曲の君が代の著作権代を支払わなかったからと言われている[要出典]。