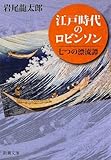『江戸時代のロビンソン -七つの漂流譚-』
海に囲まれた日本。しかし何故か国産の海洋冒険小説と呼ばれるジャンルが人気を博したことは無い!? こんな疑問を投げかけるイントロダクション。
著者の調べによると、日本では結構、漂流して生還した実話が残っているとのこと。江戸時代、相当な数の漂流生還者がいたらしい。しかも、その漂流期間が長い。
(1) 何故、江戸時代に長期間に及ぶ漂流が頻発したのか?
(2) そして、漂流・生還の実話が紙の記録に多く残されているにも拘らず、そういった話をあまり聞いたことが
無いのは何故か?(私が知っていたのは、精々が、アメリカ船に助けられたジョン万次郎の話程度だ。)
こういった疑問に答える序章の「漂流の背景」。
この序盤を読んだだけで、グワッシと掴まれた。持ってかれた。
(1)の理由は実に判りやすい。
江戸時代の廻船船の構造自体は結構頑丈で、しかも積荷も多く漂流時の蓄えがソコソコあった。その一方で、江戸時代の航路としてはもっぱら陸の見える沿岸域でしかなく、外洋での航海技術が未熟であったこと。が要因として挙げられている。
(2)については、日本文化の内向きなメンタリティ(具体的なことは本書を読んでください)による隠蔽体質などを挙げて、それを嘆いている。
本書中、こうした日本文化・体制のマイナス面に対する恨みごと・愚痴が折に触れてでてくる。尤もなことを云っているように思うが、余りにも愚痴が多く、この部分についてはウザイ。
とにかく、著者は、頻発した漂流譚、否応無き冒険とサバイバルを経験した人物達・・・・・この漂流者たちのことを著者は“ロビンソン”と云っている・・・・・の実話を明るみに出したかったとのことである。
で、肝心の漂流譚であるが、本書の題名にもあるように、7ケースが紹介されている。
■東京から約580km南方に位置する無人島(鳥島=とりしま)に漂着し、そこで20年以上もサバイバルした話。
■同じ鳥島に、異なる時期に漂着した3組のロビンソン達がサバイバルし、ついには協力して脱出する話。
■大黒屋光太夫たちのシベリアでの話(これは割りと有名か)。
■ボルネオ・ジャカルタに漂着し、現地で数年間奴隷とされながらも、策を巡らして日本行きのオランダ船に
乗船する話。
■484日間も太平洋を彷徨い、ついにカリフォルニア沖で英国商船に救出される話。
・・・・などなど、その一つひとつの話の中身が実に凄まじい。スゲー!としか言いようがない。
著者の云うとおり、こうした記録が存在することをもっと多くの人が知っていてもイイ・・・(かも)。