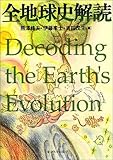『地球46億年全史』
- The Earth (2004)

- 『地球46億年全史』 リチャード・フォーティ/著、 渡辺政隆/訳、 草思社(2008)
前作 『生命40億年全史』 を読んでから4年。続編を待っていたといえば待っていた。忘れていたといえば忘れていた。
読み終わった現在、奇妙な感覚に包まれている。
本書、全部で13章で構成されているのだが、11章までを読んでの評価と、12章と13章を読み終わってからの評価がまったく違う・・・。
さて、この本、書名から想起されるものと実際の内容がいささか異なる。地球の誕生から現在までの形成史・地史とか、プレートテクトニクスやプルームテクトニクスなどといった地球変動のメカニズム・仕組みみたいなものを、順を追って、体系的に説明してゆく類の内容ではない。
著者が、ベスビオ火山やポンペイ、アルプス、ハワイ諸島、スコットランド、ニューファンドランド島、サンアンドレアス断層、グランドキャニオンなどを訪れ、彼の地の鉱物・岩石・岩盤・断層・地質構造などを見て、その地域の形成のされ方や形成時期などについてを、各所の地質年代の順番や場所的な繋がりに拘ることなく語っている。
その語り口は、地質学や地球物理学などの専門用語をむやみに多用するものではなく、非常に簡単で日常的な言葉・用語を使いながら判りやすい説明を試みているようである。
時には、文学的な比喩なども使ったりして、親しみやすさを醸しだす工夫をしているようにも見受けられる。
ほとんど紀行文、旅エッセイの様相である。旅番組で風景を語るナレーションのようでもある。
そうしたナレーションの中に、ほんの少し、地質学や地球科学の基礎的な知識をちりばめてるといった感じだ。
5章で、プレートテクトニクス理論誕生の歴史とメカニズムについて、少々地質学っぽい記述がされている箇所以外は、ほとんどの章が「旅エッセイ」風の調子である。
地球史について、順を追って一通りのことを知っておきたいという方には、ページ数の割には知識量の少ない書物であり、あまりお薦めできない。
別の本を読んだ方がイイ(例えば↓こんなの・・・)。
では、地学・地球物理学的風味を加えた「旅エッセイ」として面白かったかというと、私にはそれほどでもなかった。欧米の著者にありがちな無駄な比喩を使った文章が多すぎるのだ。滅多やたらに長い無駄な比喩の多用が、ページ数を増やしている原因になっているように思えた。
さらに、世界各地の地質や地質構造を説明するにしては地図を始めとした図表が少なすぎる。文章だけで説明しようとするから、余分で無駄な描写が増えるのである。こういった類の内容の本が、ビジュアル表現を軽視しているのはいただけない。
ただ、このような、無駄な語りの多い、ゆったりとした調子で書かれたサイエンス・エッセイが好みだという方もいるだろう。私の好みでなかっただけだ・・・。
・・・と、ここまでが、11章までを読んでの感想である。
好きな分野の内容の本なのと、貧乏性なのが幸いして(災いして?)、ここまで読み続けたが、これが違う分野の本だったら危うく途中で放り投げ出すところだった。
ところが、うって変わって12章では私の嗜好にフィットした内容の知識と哲学が語られていた。
12章のメインテーマは、「地球深部」である。著者も云っているが、この12章の内容は他の章に比べると理屈っぽい。
細かい内容を紹介しても意味はないので止めとくが、とにかく、一般の人が日常を過ごすにはほとんど役に立たない知識が書かれている。だが、そういった内容は、結構私の好物なのである。
“地球で一番豊富にある鉱物は下部マントルのペロブスカイトである”とか、“モホロビチッチ不連続面の上下でP波速度は7.2km/secから8.1km/secに変化する”とか・・・・・
このテの日常ほとんど役立たないコトを知るという贅沢にも増して、さらにこの12章では著者の達観した哲学が語られている。私メとしてはタダただ、その通り!と、膝を打ってしまうのであった。
一例を紹介しておこう。
■地球深部を源とするダイナモこそが、海洋底を拡大・縮小し、大陸同士を衝突せしめ、地殻変動を生じさせ、山脈や砂漠や大河が土地を分断し、民族を分け、言葉を分け、人類の栄光のひとつである多様性をもたらした。風景や文化の詳細はすべて地質に根ざしている。
■地質学は、ヒトに合理的な時間の尺度を持たせる。人類は万物の象徴に近い存在などではなく、ほんの付け足し、意識を持つ追伸に過ぎない。
■地殻変動に対する反応のひとつとして、とてつもない地球の歴史に驚愕し、その一部を理解する特権に浴したことを感謝するというもの。私たちはみな、説明できることに美を見い出しつつも、理解の及ばない複雑な世界や現象の奥深さに喜びを感じる心に恵まれている。
私なんぞ、このような見識に触れること、そして、その中の僅かでもいいから著者(他人)の言い分を理解できること、それこそが科学することの醍醐味であると思っちゃうのである。
この12章を読めただけでも、この本を読んだ甲斐があったってもんだ!
最終13章は、「地球周回の旅」。この章では、特定の地点の地質を取り上げてきた各章を総括して、地球システム変動の歴史の一般的な事例を語っている。
この章を頭に持って来てくれてりゃ良かったのに! と思わずにはいられなかった。
私としては、総論から入って、ある程度概略でいいから全体像を掴ませてもらった上で、各論へと詳述する形式を採ってもらいたかったナ。そうすれば、1章から11章までを読んだ時の印象も好転しただろうに・・・。
まァ、とにかく、12章と13章があったおかげで、この本を褒めて紹介することができた。