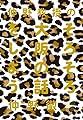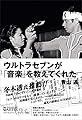読んだ本の数:73
読んだページ数:19745
ナイス数:354
 楽譜の風景 (岩波新書)の感想
楽譜の風景 (岩波新書)の感想岩城さんの苦労話が面白い。日本のオーケストラ、現代音楽の草分け的存在だからご苦労も多かったであろう。「春の祭典」を振り間違える話は大変だなぁと思う。そのあとのメルボルン響の慰め方がなかなか泣ける話である。確かに暗譜で振るとかっこいいけどねぇ。「作曲家の中には、自分が書いた複雑な音を聴き分けられない人が、少なからずいる。」「初演の練習の時に作曲家は病気になってはいけないのである。」「世の中には、いろいろな演奏者がいる。はっきり言えば、おそろしくバカなピアニストもたくさん存在するのだ」等草創期ならではの警句も
読了日:01月03日 著者:岩城 宏之
 プレゼント (中公文庫)の感想
プレゼント (中公文庫)の感想葉村晶シリーズの記念すべき第一作である。文章の書き方そのものにトリックが仕掛けてある場合があるので、うかうか読んでいると最後にどんでん返しできれいに決められても、どういう意味かがすぐにわからずもう一度読み直すことになったりする。二度楽しめてお得といえばお得だろうか。
読了日:01月05日 著者:若竹 七海
 依頼人は死んだ (文春文庫)の感想
依頼人は死んだ (文春文庫)の感想女性探偵でハードボイルドをやろうという趣旨は非常に面白い。最後にどんでん返しを食らって、もう一度読み直させられることがあるのは前作同様である。書き下ろしの最後の短編は超自然的な終わりになっていてあまり面白くない。強力な催眠術なんか導入したらせっかくの推理小説をスポイルしてしまう。
読了日:01月12日 著者:若竹七海
 悪いうさぎ (文春文庫 わ 10-2)の感想
悪いうさぎ (文春文庫 わ 10-2)の感想葉村晶シリーズの長編なのだが、今一つ調子が出ていない感じはある。若竹さんの持ち味である「驚きのどんでん返し」は長編ではやりにくい面もあるだろう。結局、女ハードボイルドの葉村と警察の柴田や探偵会社の桜井らとのやりとりを楽しむことになり、それはそれで結構なのだが…大家の光浦がいいキャラでこれはクリス松村さんにぜひ演ってもらいたい。
読了日:01月20日 著者:若竹 七海
 オリヴィエ・メシアンの教室 作曲家は何を教え、弟子たちは何を学んだのかの感想
オリヴィエ・メシアンの教室 作曲家は何を教え、弟子たちは何を学んだのかの感想思ったより実例を挙げての説明に乏しく、期待したものとは違っていて私としてはつまらなかった。一部春の祭典の分析などちょっと顔を出すのだが…楽譜の書ける音楽の話は譜例がなかったら始まらないと思うのだが。
読了日:01月25日 著者:ジャン・ボワヴァン
 暗い越流 (光文社文庫)の感想
暗い越流 (光文社文庫)の感想葉村晶、いよいよ殺人熊書店員となる。シリーズではないけれど、「狂酔」が面白かった。南治彦シリーズも最後にもう一ひねりというのがしつこくもあり、サービス精神ともいえるだろうが微妙なところだ。
読了日:01月26日 著者:若竹 七海
 ジャズからの出発 (1973年)の感想
ジャズからの出発 (1973年)の感想50年代には「ジャズを推し進めて世界革命が起きる」とまじめに考えていたのだろうか。とするとこれは赤軍派にも匹敵する妄想である。銀巴里のセッションというのがYouTubeに上がっていたので聞いてみたがお寒い限りで、日野皓正が光っているくらいで山下洋輔にしろ菊地雅章にしてもおぼつかない。高柳昌行に至っては…山下洋輔は「まともなジャズ」では勝負できないのがわかってフリーに「逃げ」、そこへまともな渡辺貞夫が帰ってきた。この本はむしろ演歌・歌謡曲論の方が面白い。結局ジャズの理解できなかった著者の本だという気がする。
読了日:01月31日 著者:相倉 久人
 さよならの手口 (文春文庫)の感想
さよならの手口 (文春文庫)の感想面白かった。特に最後の一ひねりは洒脱である。ただ、長編をもたせるための骨格になる謎がすっきりしていない。なるほどこれですべての説明がつく、というカタルシスに欠けるのだな。ディテールはいつものハムラもので、楽しませてくれるが…しかしハードボイルドとはいいながら怪我の多い探偵である(笑)
読了日:02月04日 著者:若竹七海
 現代音楽史-闘争しつづける芸術のゆくえ (中公新書, 2630)の感想
現代音楽史-闘争しつづける芸術のゆくえ (中公新書, 2630)の感想大変勉強になった。私の「現代音楽」の時間はせいぜい80年代で止まってしまっており、そのあとの40年近くを駆け足で取り戻すのに本書は大変よい助けであった。私自身の創作は80年代から細々と続いてはいたがそれは主にジャズやポップスの世界においてであり、その後の現代音楽の展開にはあまり興味を持てないでいた。この40年間が「現代音楽」にとって豊かな時代であったかというのは簡単には答え得ない質問であろうが今でも70年代的感性しか持ち合わせない私にとってある種の「開き直り」をさせてもらうのに、本書は大変助けになった。
読了日:02月12日 著者:沼野 雄司
 錆びた滑車 葉村晶シリーズ (文春文庫)の感想
錆びた滑車 葉村晶シリーズ (文春文庫)の感想再読ですが、やっぱりなにかしっくりこない。話がだれてくると探偵を無茶な窮地に放り込む。サブストーリーの一つ二つはいいのですが、それがどうも有機的なつながりが感じられない。最後の謎解きも凝ってはいるがとってつけた感がどうしても残る。この小説に関しては微妙であります。
読了日:02月26日 著者:若竹 七海
 不穏な眠り (文春文庫)の感想
不穏な眠り (文春文庫)の感想面白かった。掌編というのか、このくらいの長さが葉村モノには適しているのではないか。こちらが老齢化で長編を追いきれなくなっているだけかもしれないが。
読了日:03月01日 著者:若竹 七海
 レキシントンの幽霊 (文春文庫)の感想
レキシントンの幽霊 (文春文庫)の感想再読である。村上春樹さんの短編・中編はどれも好きなのだが、「めくらやなぎと、眠る女」が、言葉の細かいディテイルまで彫琢されたことがよくわかり、読んでいて快い。
読了日:03月06日 著者:村上春樹
 哀しい予感の感想
哀しい予感の感想この小説が書かれた1988年には、アメリカに居て、父の容体がよくないことを聞かされて夏には一時帰国、葬式をすませてまたもどったのだった。時代の空気感というものはありますね。初読だが、これについていくにはもう歳をくい過ぎた。
読了日:03月09日 著者:吉本ばなな
 あすなろ物語(新潮文庫)の感想
あすなろ物語(新潮文庫)の感想いまさらという感もあるが再読である。主人公は一貫しているが掌編集といった方がいいだろう。最後の終戦後の物語が、結局自分の体験に一番近いこともあってか面白かった。
読了日:03月14日 著者:井上 靖
 日本人とユダヤ人 (角川文庫 白 207-1)の感想
日本人とユダヤ人 (角川文庫 白 207-1)の感想70年代のヒット作を再読。批判本が出たくらいで、インパクトのある本であった。ユダヤ人という鏡(まったく平らではない鏡だが)に映してみて日本人はどう見えるのかという実にユニークな視点で、「日本教」という概念を提示した画期的な書物だったと思う。ユダヤ人とその歴史についての記述が不正確ということはあるかもしれないが、それを持って本書の日本人とその文化に対する発見が無になるものではないと思う。50年を経て日本人理解の切り口は古びてはいない。
読了日:03月19日 著者:イザヤ・ベンダサン,Isaiah Ben-Dasan
 日本の詩歌 (9) 北原白秋 (中公文庫)の感想
日本の詩歌 (9) 北原白秋 (中公文庫)の感想本棚の奥で未読になっていたのを引っ張り出してきた。白秋でも意味の取れないところが結構あり、この本の注釈は大変参考になった。「若きロテイの物思い」のロテイがPierre Lotiとはこの本に教えられた。
読了日:03月25日 著者:北原 白秋
 日本教について (文春文庫 155-1)の感想
日本教について (文春文庫 155-1)の感想再読である。本多勝一さんへの最初の手紙は確かに「失礼」かもしれないが、内容的には本質をついている。明らかに虚偽とわかる情報についてもそれが一旦「踏絵」になってしまうと是認する「証拠=証言」を山のように集めてくる。異なる証言の間を分析して真実にせまることができなくなる。日本教の日本教たる所以で、これは21世紀になっても令和になっても変わらない。実体語・空体語のモデルはモデルに過ぎないが実に秀逸なモデルである。昨今の事例に当てはめてベンダサンさんの説明が聞きたいところだ。
読了日:03月29日 著者:イザヤ・ベンダサン
 「法華経」を読む (講談社現代新書)の感想
「法華経」を読む (講談社現代新書)の感想面白いが紀野さんの御説であって「法華経を読む」という題名が正しいかどうかは疑問である。「人間は、自分で自分にきめた生きざまというものがある。それを破りたくはない。…いつでも絵に描いたようにすっきりと生き、そして死にたいものである」なんてのは、いっちゃあなんだが、それがもっとも離れるべき「欲」ではなかろうか。一方、紀野さんが戦後に非道な命令を受けて上官を斬りに行こうとするエピソードなんかは面白い。人間を見る思いがする。いずれにせよ私なぞ「智なきもの」なので箸にも棒にも掛からぬようだ。これを縁なき衆生という。
読了日:04月10日 著者:紀野 一義
 福家警部補の挨拶 (創元推理文庫)の感想
福家警部補の挨拶 (創元推理文庫)の感想以前、檀れいさんの主演のテレビドラマを見て記憶にあった。刑事コロンボの舞台を現代日本に移し、主人公を風采の上がらない「女性」刑事にしたところが工夫である。倒叙であるから犯人はわかっている。それを地味な福家警部補がじわじわと捜査を進めていかに逮捕に持ち込むかが興味の中心である。「あと、もう一つ」というのもコロンボ風だ。おんぼろの車にのる代わりにいつも警察手帳をごそごそとカバンのなかで探していたりする。最初の出会いで実は犯人がわかっていた、というのもコロンボ流ですな。面白く読みました。
読了日:04月17日 著者:大倉 崇裕
 社会人1年目からのとりあえず日経新聞が読める本 (「やるじゃん。」ブックス)の感想
社会人1年目からのとりあえず日経新聞が読める本 (「やるじゃん。」ブックス)の感想経済形ハウツー本の中ではまともなものでお勧めするにやぶさかではないが、株式投資をすすめておいて、でも自己責任で、というのは当然と言えば当然だがいかがなものか。定期預金を選ぶという戦略もあり得ると私は思います。この手の本の宿命としてどんどん古くなるのが難点。ツボは押さえているのでこれを片手に最新の日経新聞を読めということでしょうな。2016年時点の情報で構成されているが、この時はコロナのことなんか予想もつかなかったですよねぇ。
読了日:04月19日 著者:山本 博幸
 とにかく散歩いたしましょうの感想
とにかく散歩いたしましょうの感想小川洋子さんは確かに岸本佐知子さんと通底するものがある。旅行の時など、大事に際してささいなことが気になるのはとてもよくわかる。そのささいなことに神経を集中して大事をやり過ごそうとしているとご本人も気が付いておられるがおそらくその通りだろう。外出嫌いも我が意を得たりと思うところである。めったやたらにアウトドアな人が理解できないが、まぁ人それぞれということでもあろう。
読了日:04月20日 著者:小川 洋子
 さいはての彼女 (角川文庫)の感想
さいはての彼女 (角川文庫)の感想こういうのがライトノベルというのでしょうか?何か引っかかるものがまったくないのがいいようなつまらないような。
読了日:04月25日 著者:原田 マハ
 ジョーカー・ゲーム (角川文庫)
ジョーカー・ゲーム (角川文庫)読了日:04月30日 著者:柳 広司
 わたし、定時で帰ります。(新潮文庫)の感想
わたし、定時で帰ります。(新潮文庫)の感想仕事にどこまでエネルギーを注ぐかという問題を扱う。残業、サービス残業、有休取得しない、休日出勤、果ては何日も徹夜。インパール作戦まで持ち出して無茶な仕事ぶりが糾弾される。自分のことを想えば、時代もよかったし、会社にも余裕があったと思う。熱があればさっさと帰って医者に行けと言われたし、最高月間残業時間は60時間、サービス残業はもちろん、残業そのものはなるべくやめるようにという社風であった。さらに企画という仕事が決まった時間を消費するという性格のものではなかったことも大きい。あ、小説としては面白かったです。
読了日:05月07日 著者:朱野帰子
 マーブルな女たちの感想
マーブルな女たちの感想また、小説のふりをしているが小説でないものを読んでしまった。最後まで読んだのだから特に苦情はないのだが、何か小説らしくない。そこがいいのだろう。「文学」を求める向きにはおススメしない。
読了日:05月09日 著者:きじまはるか
 青の炎 (角川文庫)の感想
青の炎 (角川文庫)の感想よくできた倒叙ものなのだが、何より主人公が漱石「こころ」の登場人物の心理が理解できないという点に非常に共感するものである。ホントあの「先生」という人は理解を超えている。漱石は好きだが、「こころ」はよくわからないといわざるを得ない。
読了日:05月11日 著者:貴志 祐介
 逆ソクラテス (集英社文芸単行本)の感想
逆ソクラテス (集英社文芸単行本)の感想何度も「歩」君の心理描写を繰り返してクライマックスに至る手法は面白かった。これが評価されるのも本屋大賞ならではというところか。
読了日:05月20日 著者:伊坂幸太郎
 大統領の密使の感想
大統領の密使の感想何度読んだかわからないが、昭和46年の初版だから最初によんだのは中学生の時だろう。驚くことにほとんどのギャグ・くすぐりの類を覚えていることである。伝奇小説のパロディであるが、B級サスペンスの要所をきっちり押さえているところがさすが小林信彦である。アレン・スミスのプラクティカル・ジョークの話や、戦後の闇市の話など関係ない脱線が楽しい。小林信彦さん自身「落語の笑い」がベースにあると書かれているから、私の笑のセンスも結局そのあたりに基礎をおいたことになる。
読了日:05月20日 著者:小林信彦
 日中戦争―和平か戦線拡大か (中公新書 133)の感想
日中戦争―和平か戦線拡大か (中公新書 133)の感想1931年の満州事変から1945年の日本の敗戦に至るまで、日中間の戦争の動向を淡々と記している。日本が中国大陸に侵攻することで中国の人々の生活にどのような影響を与えたかといったミクロな話はひとまず置かれているきらいはあるが、死者数、傷病者数、そして日本に連行された中国人の話など読み進むにつれ、日本が何をしたのかが明確なイメージをもって立ち上がってくる恐ろしさがある。日本が韓国、満州、蒙古、そして中国にどれだけの被害を与えたのかを今一度確認するのに便利な小史である。
読了日:05月21日 著者:臼井 勝美
 大統領の晩餐 (角川文庫)の感想
大統領の晩餐 (角川文庫)の感想本作のテーマは求道小説と中華料理。猫探しもテーマのひとつであるが、この点はあまり掘り下げられていない。東映映画・日活映画に関する蘊蓄も語られている。1972年作品だが、1972年というのは私にとっては沖縄返還と六文銭の年であり、ある種のターニングポイントであった。オリジナルの表紙はおなじ絵柄だがもっと淡い色遣いである。
読了日:05月22日 著者:小林 信彦
 合言葉はオヨヨ (角川文庫 緑 382-6)の感想
合言葉はオヨヨ (角川文庫 緑 382-6)の感想再々読くらいだ。これに先立つ「大統領の密使」「大統領の晩餐」にくらべて脱線が少ないのがややさみしいのと、プロットに凝りすぎてわかりにくいのが難点だが、多少は残っている脱線部分はとても楽しい。週刊朝日にこのような遊びの多い小説が連載されていたというのも不思議だ。時はこれもまさに1972年、沖縄返還と六文銭の年である。
読了日:05月27日 著者:小林 信彦
 秘密指命オヨヨ (角川文庫 緑 382-7)の感想
秘密指命オヨヨ (角川文庫 緑 382-7)の感想これも再々読くらいだと思う。サスペンスであり観光小説であるので、テンポが今一つだが、ところどころにある脱線が面白いのでそこを楽しみに読むことになる。作者はヨーロッパ各地、南はモロッコまで取材旅行をされたようだが、それが1972年。作中にすでに日本からのパックツアーが描かれているので、そろそろエコノミックアニマルの本領発揮といった時期だったのであろう。
読了日:05月30日 著者:小林 信彦
 ノルウェイの森 上 (講談社文庫)の感想
ノルウェイの森 上 (講談社文庫)の感想再読だが、ほとんど忘れていた。要は、一にセックス、二にセックス、三にセックス、4に自殺、自殺、自殺、5に二股、という小説である。くだらないとは言わないし、洒落た会話や名言もちりばめられているが、要するにそういうことだ。
読了日:06月03日 著者:村上 春樹
 38万人の仰天 (中公文庫)の感想
38万人の仰天 (中公文庫)の感想1982年作品。私が初めて大阪という魔界の地に足を踏み入れたのが1981年。当時の風俗・気分が活写されていて、その興味で読み直した。思えば大阪へ行って(1年間ではなかったが)配偶者をつれて東京に戻ったのは主人公の草薙と同じであるな。
読了日:06月07日 著者:かんべ むさし
 ムーン・リヴァーの向こう側 (新潮文庫)の感想
ムーン・リヴァーの向こう側 (新潮文庫)の感想平成7年作品。ラブ・ストーリーはともかくとして、丹下健三=鈴木俊一による「町殺し」という小林信彦さんの持論がはっきり展開されている小説である。「深川」とか「川向う」とかのキーワードから東京の成り立ちも語られる。江戸の北の郊外に育った私には遠い世界だが、東京を多少知るにつけ興味深い。
読了日:06月09日 著者:小林 信彦
 イーストサイド・ワルツ (新潮文庫)の感想
イーストサイド・ワルツ (新潮文庫)の感想再読。平成7年の「ムーンリヴァーの向こう側」に先立つこと2年、1993年作品だが、どちらも中年男が年下の女性といい仲になるというおとぎ話めいた設定であり(いや、世の中にはそういうこともあるらしいが)、女が深川生まれで「川向う」と川の西側の物語であるという点も同じで、この二作は双子のようによく似ている。本来の東京の「下町」「山の手」を記録しておきたいという作者の意図がよく表れており、また成功していると思う。
読了日:06月10日 著者:小林 信彦