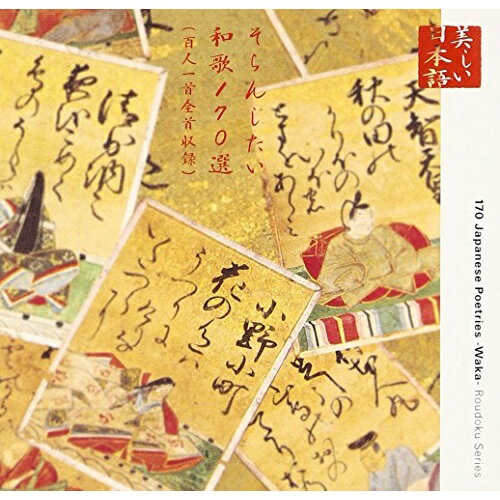白露に 風の吹きしく 秋の野は つらぬきとめぬ 玉ぞ散りける
文屋朝康(ふんやのあさやす)は康秀の子である。康秀は小倉百人一首に「ふくからに」を撰歌されている。朝安は、平安中期に活躍した歌人である。しかし官僚としての活動状況についてはあまりよく知られていない。また撰首された歌は少ないが、宮廷内の歌合などでは活動していたようである。この歌だけみても流麗絢爛で、風体もよく優れた詠み手であったのはよくわかる。大舎人大允に任命されていることからも、王家の雑用係として働き、気配りも良くできたに違いない。しかし、構図の中で隙の無い歌からは、神経質な印象も伺い知る事ができる。
さて歌を見てみよう。「白露(しらつゆ)」は、草木の葉や枝にあって、白く光って見える露のことで、季節は秋を示す。「露」が球形に見えるので、下句「玉」に懸かっている。「ふきしく」は「吹き頻(しき)る」の事で、「しきりに吹き付ける」という意味である。「秋の野は」の「は」は格助詞「に」の転化、そして「葉」に通じて、白露の置かれている場所を示している。
下句「つらぬき」は皮革靴「頬貫(つらぬき)」のことである。毛皮をつかうこともある。袋状にして足の甲の上を紐で縛る。「とめぬ」は「とめ・ぬ」=「とめて・しまったら」の意味で、「たま・ぞ」の「ぞ」は強調、「玉のように」といった意味である。訳してみよう。
「秋だというので、とある野原に早朝からやってきたものの、秋風が強く吹き付けていて、草木の葉に置かれた白露が、頬貫の足を止めたにもかかわらず、玉のようにちりぢりに散っていくではないか、ああ、もうすっかり秋なのだなぁ」
さて、この歌にも、もちろん裏がある。まず「露」だがこれは、狩衣の袖くぐりの緒の垂れた端を意味していて、この部分は玉結びになっている。「かせ」は「悴」で、身分の低い者を指す。「ふき」は衣(この場合は秋なので綿入れ)の袷(あわせ)の袖口で、裏布を表に折り返して縁のように仕立てた部分をいう。「吹き返し」といわれている部分だ。「しく」=「如く」、「〜のように」の意味で使われている。「秋の野」の「野」は「ぬ」と読み、「瓊(ぬ)」で赤い玉を意味する。したがって「秋の」は秋に用いる襲色目のうち、楓紅葉(かへでもみぢ)、捩り紅葉(もぢりもみぢ)あたりだろうか。
下句「つらぬき」は「頬貫」、「とめぬ」は、頬貫の紐を止め直そうとしたとき、という意味となる。「玉ぞ」は「瓊」のことで、白い露(紐端)同士を留めていた赤い玉である。「散りける」は玉が外れて、落ちてしまった、という意身である。訳してみよう。
「秋だというので、綿入れの衣を出して、襲をあわせてみたが、私のように位の低い者が着る衣では、汚れが目立つから、吹き返しを少し多めに取らなければならければ、みっともない。出かけようとして、頬貫の紐が緩んでいたので結び直したら、紐止めの瓊玉が、落ちて散ってしまった。季節が変わるというのは、大変な事よ。」
王家の雑事を一手に引き受けていたのだろう、季節が変わる時期の忙しさが手に取るようにわかる。父親の文屋康秀も同じような心情で歌を詠んでいる。
「つらぬき」で詠まれた狂歌。
三十八 紀定丸 理齋随筆
狂)手づくりの 団子の串の ふと過ぎて つらぬきとめぬ 玉川の里
「玉川」は東京都調布市。この歌は連歌四首の一部で、冒頭は蜀山人の歌で始まっている。続けて書いてみよう。
蜀山人
狂)玉川の 昔の人の 手づくりは 徳用向(むき)か 何かしらなみ
紀定丸
狂)手づくりの 団子の串の ふと過ぎて つらぬきとめぬ 玉川の里
理齋
狂)二つ文字 牛の角もじ すぐなもじ むかしの人の こひしきや謎
手柄岡持
玉川は手織りの布をさらす川で、万葉集・東歌にも詠まれている。
万葉)玉川に さらすてづくり さらさらに 何ぞこの児の ここだかなしき
拾遺集では下句を変えて次の様に詠んでいる。
拾遺)玉川に さらすてづくり さらさらに 昔の人の 恋しきやなぞ
蜀山人達は、これらの古歌を引用して遊んだわけだ。それにしても「団子の串が太すぎて、団子がとれない!」と叫んでいる姿が目に浮かんでくる定丸の狂歌のおかしさは、最高だ。