おそらく、今を生きる僕たちの共通の悩みかもしれない。
過去の貴重な音楽をそのまま再現することに、最大限の喜びを感じるとしよう。それは模倣だというのか、引用と言えるのか。どちらにしても、それが気持ち良いことであれば、人間はそうする。いずれその先にオリジナリティーは生まれてくるのだから。
Contemporary Eclectic Replica Orchetstra…と始まるセルフタイトル曲「C.E.R.O」、バンド名の意味を歌う。これは自身の特性を揶揄しているのか、はたまた、自信の表れなのか。現代的に、良い音楽のエキスを取捨選択して、それをそのまま完全に表現できるオーケストラ。素晴らしい。正に彼らだ。
タイトルの『Obscure Ride』を表すかの如く。作品は移りゆく時代と靄のかかったタイムラインを流れている。
最初の「Yellow Magus」「Elephant Ghost」は今の現実世界での表現だ。
ネオ・ソウルな楽曲で乗っていくメロディ。続く「Summer Soul」は破格の気持ちよさを兼ね揃えた、cero的現在進行形の最終地点と言えるものだろう。
突然、「Rewind Interlude」で時間軸が巻き戻される。過去のある地点から、今の時代に流れていくことになる。
ここで、本作のウィークポイントとも言える歌詞が、「tick tack」にある。《どっかでリューズが巻き戻されたような、やり直しの時間を生きているような》という歌詞。これこそ、青春感を含むヒンヤリとした皮膚感覚を端的に言葉にした部分だ。これが僕たち世代の弱さでもあり、冷静さをつかさどる側面でもある。
再び、今の時代に戻り「Roji」へ。
ボーカル高城昌平が自身の母親と経営しているカフェと同タイトル。ここが過去と現在の交差点として機能している。彼にとってもこの場所がそういう意味を持っているのだろう。
ソウル、ジャズ。ヒップホップを通過したブラック・ミュージック、その流れと共に時間は夜へと。作品はクライマックスへ進む。「DRIFTIN'」「夜去」それは、夢の世界の入り口だったのだ。「Wayang Park Banquet」から「Narcolepsy Driver」へ、どんどん深層心理の奥の奥へ進んでいく様子を描く。
ラストは「FALLIN'」《行こう夢の中へ 何度でも》場面はついに夢の中へ。でも、逆にそれは現実なのかもしれない。
多様なブラック・ミュージックを使いこなし過去と現在、現実と非現実をスライドしていく歌詞。何故、彼はそのような音楽を選択したのか。それは、変な意味でとらえないで欲しいのだが、黒魔術として機能させることが出来るからだ。一つのビートの反芻とはまた違った形で、縦横無尽に迸るリズムは、聞くものの脳を覚醒させ、全ての時間をあいまいにする。
そう、僕たちは一瞬でタイムスリップを体験出来る音楽を渇望している。ただ、この魔術の恐ろしさは、扱ったものさえも同じようにかかってしまうのだ。
cero自身も、彼らの音楽を聴いた者も全ては曖昧模糊な景色にいざなう。
そんなものを僕たちは求めてやまないはずだ。
Obscure Ride 【通常盤】/cero
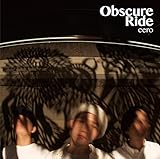
¥2,900
Amazon.co.jp