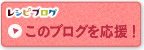お久しぶりです。
そして、突然、汚いものをお見せして申し訳ありません![]()
えぇ。
ご覧いただいて、お分かりいただけますように、
またしても、うっかり、ステンレス鍋を焦がしました!🤣
味噌汁を火にかけて、息子の相手してる間に、火を止めた気になってて、そのままお風呂入れたりしてたら、すっかり忘れてた😱
お風呂から上がって、焦げ臭い匂いで、あ!!!!!と気づいた時にはすでに遅し。。。。
底が一面、真っ黒に。。。。
うちのキッチン、安全装置がついていて、焦げたら、自動で火が止まる仕組みになってるので、火事にはならないんですが。。。
(火事にならない技術の進歩に感謝が絶えません😭)
またしてもやってしまったー。。。。
焦げ焦げ真っ黒。。
あーあー。。。。。
鍋底にこびりついた焦げ、具材を全部捨てて、シリコンヘラで軽く擦ってみたけど、完全無欠で真っ黒黒。
まっくろクロスケか!?というくらい黒い。
取れる気配もまったくない。。。。
これは、もはや鍋捨てるしかないレベル!?![]()
なーんてことは、ない!![]()
ふっ😏
そこは、ご心配無用!
えぇ、こういうことを繰り返してますとね。
何故か技術が勝手に磨かれまして。
はい!( ′▽`)ノ
ぴっかーん!!!!![]()
![]()
![]()
なんということでしょう(♡ˊ艸ˋ)♬*
あの焦げ焦げの鍋が、新品同様の輝きに!![]()
![]()
(ちなみに、この写真の時点では、まだ洗剤使って洗ってません(笑))
で、まぁ、今回、焦がして、処理してる時に、ふと。
あー。そういや、大学時代に、一人暮らしの女友達の家に料理を作りに行って、たぁーこ。が帰った翌日、その子が起きてみると、
前にその子が焦がしてしまった鍋の焦げがすっかり消えてたから、
どうやって焦げを落としたの!?
と聞かれたことあったなぁー。
というのを思い出しました。
んー。。。。。![]()
そういや、たぁーこ。、どっかのたぁーこ。の記事でだったか、コメントだったかで、鍋の焦げの落とし方を簡単に書いた気もするけど、ちゃんとは記事にしてないよなぁ。。。??![]() 多分?
多分?
あれ?どうだったっけ?
でも、写真は絶対に撮った記憶ないな。
この方法、きちんと知りたい人いるかしらん?![]()
と、今回、処理の途中で写真を撮ってみました(笑)
(えぇ。最初の酷い焦げ写真、これでも処理途中の写真でして、最初は、右底のような焦げが、
底一面広がってましたともさ🤣)
息子の夕ご飯をしながら、焦げ処理してたので、写真は少ないですが、一応ご紹介です!🤣
というわけで、
さぁ!今日の本題!
たぁーこ。流!
鍋の焦げ取り方法でーす♪
アルミ鍋は、そもそも、酸性にもアルカリ性にも弱いそうなので、使えない技ですが、ステンレス鍋の方で焦げてしまったらどうぞお試しください🤣
とは言っても、
まぁ、滅多に、たぁーこ。みたいに鍋を焦がす!なんて、ない方が多いと思うので、ほとんどの方には、不要な技術かもしれませんが(笑)
でも、日々、料理していると、鍋底とか鍋横とか汚れてくるじゃないですか?
それにも応用できるので、よければご参考までに![]()
材料
用意するもの
・重曹
・クエン酸
・水(適量)
これだけです(@>ω<)ノ★゛
焦げの落とし方
① まず、焦げた鍋を用意します。具材等は捨てて、水分も捨てておきます。(水滴はついてても全然構いません。焦げ鍋を洗剤で洗っておく必要もないです)。そこに、重曹を底一面真っ白になるくらいまきます。それを柔らかめのシリコンヘラ等で擦って焦げに馴染ませ、水でザックリ洗い流します。
たぁーこ。の聞き齧りによりますと、
科学的には、焦げって、酸性らしいんですよねー。
本当かどうかは知りませんが、そうらしいです。
だから、アルカリ性の重曹が酸性の焦げを吸着して焦げが落ちる!
というのが一般的解釈らしいんですが、それだけだと、科学的説明とは相反して、ここまでの焦げの場合、いくらアルカリ性を足しても、焦げが全部は落ちたことないんですよね🤣(普通、焦がしても、ここまでは焦がさないのかなぁ![]() !?)
!?)
② ①の水でザックリ洗い流した鍋に、今度はクエン酸を底一面巻いて、焦げている箇所まで水を加え、火にかけ、お湯になるまで温めます。
お湯になったら、火を止めて、お湯を、水を流しながら、捨てます。(配管を痛めないように、必ず水を流しながらお湯は捨ててね)
はい!
この時点が、最初の写真でーす![]()
一度重曹したものなんだけど、
案の定というべきか、右横も右底もまったく汚れが取れてません。
というわけで、ここからがたぁーこ。流!
ワザと酸性を投入!!!![]()
これまた、むかーし、りんごをレモン汁で甘酸っぱく炒めた鍋を洗ったら、ピカピカになったことがありましてね?
酸性を入れたはずなのに、ピカピカに!?
という体験をして不思議に思ってたんです。
で、たぁーこ。ある日、鍋を焦がした時に、その経験を踏まえて、ある妄想をしました。(まったくもって科学的根拠はないです🤣妄想です)
焦げは酸性らしいけど、
もしや、焦げにも、まだ酸性になりきれてない
アルカリ物もあるのかもしれない??
もしくは、焦げの酸性をより強化することで、次にアルカリを投入した時に、吸着率があがるかもしれない???
と思ったわけです。(まったく根拠もない、単なる妄想ですので、科学的には間違ってると思います(笑)あしからず🤣)
んでも、焦げ鍋でワザワザ、再度、りんご煮をつくるわけにはいかないですし、
こういう時は、クエン酸ー!!!
りんご煮みたいに少しあっためてみよう!![]()
と軽い気持ちでやってみたら、
何故かうまくいったという🤣
未だに科学的根拠は不明です🤣
別にあっためるだけで、沸騰させる必要はないです。
③ ②のお湯を捨てた鍋に、クエン酸をさらに入れてよく焦げの部分に馴染ませ、そこに重曹もクエン酸と同じくらい加えて馴染ませ、そこに水を加えて発泡させながら、焦げをとるようによくかき混ぜ、発泡がおさまったら、水を捨てる。
こちらは、焦げが酷い場合に、発泡パワーで汚れを浮かせてみよう!と思ったのがキッカケでした🤣
こちらも科学的根拠は不明ですが、何故か、ききます(笑)
今回は、焦げが酷かったので、この発泡の工程もしました(笑)
ただ、この発泡だけ、息子も一緒にやりたがったので、ここの写真がありません![]() (最近、息子、お風呂の発泡剤にハマってまして、一緒に作ったりしてるんですが、それで、すでに、重曹とクエン酸に水を加えると泡泡になることを知ってまして🤣自分で発泡剤を作るー!と勝手に掃除道具入れから重曹とクエン酸持ってきたりします。。。)
(最近、息子、お風呂の発泡剤にハマってまして、一緒に作ったりしてるんですが、それで、すでに、重曹とクエン酸に水を加えると泡泡になることを知ってまして🤣自分で発泡剤を作るー!と勝手に掃除道具入れから重曹とクエン酸持ってきたりします。。。)
ちなみに、焦げが酷くない場合は、①と②と次の④だけで焦げは落ちます🤣
焦げてなくて、汚れが酷いなーってくらいなら、②→④の工程だけで汚れは落ちちゃいますし、
酷い焦げの場合でも、基本は、①→②→①→②→④でおちるので、たぁーこ。も発泡するのはこういう完全に捨てるか?というくらい酷いなレベルの焦げ焦げモードの時くらいです🤣
④ ③の鍋に、重曹を加えて、重曹に、焦げをよく馴染ませる。
これ、重曹に焦げを馴染ませた写真です。
真っ白だった重曹が、焦げを馴染ませるように混ぜている間に、みるみる茶色になっていきます。
そして、お分かりいただけるように、この時点で焦げが。。。。。
⑤ 水で鍋を洗ったら、はい!このとおり、ぴっかーん!!!₍₍ ◝(●˙꒳˙●)◜ ₎₎
あとは、普通に、スポンジで洗剤使って洗ったら終了です。
意外と簡単に落ちちゃいます![]()
時間にしても、ご飯の用意をしながらでしたが、30分もかかってないと思います。
もし、たぁーこ。と同じく、
やっちまったー!!!!![]()
って方がいらっしゃったら、ご参考までに![]()