今日はウランバートル市はやたらと停電続発です。
大体1時間ぐらいで復旧しているのですが、うちだけでなく、点々とあちこちで停電らしい。
折しも、本日は、第5火力発電所プロジェクトクトの入札希望者の現場視察+説明会の日。
そんなことから、久々の計画停電(抜き打ち)じゃないかしら、とうがった見方をしながら、馬乳酒をかっくらって酔っぱらっている私です。
こんばんは。モンゴルだるま@モンゴルです。
草原では、クリーンエネルギーとバイオマス燃料のみ使用のエコライフを営んでおります。
モンゴル語通訳・翻訳・コーディネーター・リサーチャーなど、モンゴルに関わるいろんなことを、頼まれたら、「はいよ」と引き受ける気のいい庶民な兼業遊牧民であります。
さて、第5火力発電所ってなぁに?おいしいの?という方のために。
90年代に、ちょいと第4火力発電所の日本政府援助プロジェクトにかかわらせていただいて聞きかじった知識などを披露してみますね。
なにせ、まだ学生時代の助っ人通訳だったし、子供で難しいことわかんなぁい、っていうハタチそこそこの小娘だったころの(そう、ゴビ砂漠では恐竜の卵がゴロゴロしていた頃)話なので、うろ覚えっていうところもあるから、詳しい人、訂正あったら、こっしょり教えてくださいね。
さて、今、モンゴル国内には4か所の火力発電所が稼働しております。
ウランバートル市内にある第2、第3、第4火力発電所+南ゴビのツォグトツェツェーというソムの近くの石炭鉱山を開発している民間企業が持ってる小規模火力発電所です。
第1火力発電所は、規模が小さいうえに老朽化がひどく、いつ事故がおきてもおかしくない、という状態なので、そのまま放置・閉鎖状態です。
そして、第3、第4(メインは第4)火力発電所が主にウランバートル市の暖房供給とモンゴル全国の電気供給の8割以上を賄っております。
第3火力発電所はアメリカの援助で、第4火力発電所は日本の2期にわたる無償援助と2回の円借款によるプロジェクトで改修工事が行われたわけですが、第3火力発電所は、もはや一部機材の交換や修理だけではおっつかないくらいな状態だったりするようです。
しかし、ウランバートルのみならず、鉱山開発が活発化すれば、それにともない重工業のプラントも増える→電力需要はますます増える、という状態。
そんななかで、第5火力発電所計画は10年ぐらい前から話はされていたものの、これまで、なかなか実現化に至らなかった大型案件のひとつというわけ。
うっわー・・・ざっくりすぎる?でも、あんまりオタッキーな説明をしてもね。
アメリカの援助でリハビリテーションが行われた第3火力発電所の設備を徐々に更新(設備の入れ替え)をしながら、150MW規模のプラントを3基設置して450MW規模にする、という計画。
アジア開発銀行(ADB)のコンサルタントチームが詳細設計まで行ったところで、はれて、今回の入札公示となったわけです。
このプロジェクトの難しそうなところは、プラント建設だけでなく、その後の発電供給オペレーションもカバーしなきゃいけないってこと。
いわゆるPPP(Public/パブリック(官)・Private/プライベート(民)・Partnershipパートナーシップ(提携))でその後の運営をやっていきましょうってことなのですが・・・
正直、モンゴルでPPPって成り立つの?という素朴な疑問があるのです。
庶民の私たちにとっては、電気代が過去4年の間に、ほぼ2倍に単価が値上げされるっていうのは、ひぃー!っていう生活費の圧迫以外の何物でもないのですが、でも、電気供給側からすると、世界的に見てもモンゴルの電気代って安いのだそうです。
来年度からは徐々に電気料金課金システムの縛りが緩み、自由化になる、とか民間企業の売電業務が認められるようになる法整備が進んでいるわけですが、今のところ、発電所も送電サービス(高圧電線で電気を送る)も給電サービス(一般家庭や企業・団体など個別の物件に電気を供給管理する)も全部、国有株式会社(いわゆる国営企業)なのです。
そして、しばしば、停電になったりするのですが、それは需要量に対しての供給量が足りない、というだけでなく、ぶっちゃけ、石炭代金の支払いが滞って、石炭備蓄が足りなくなった、とかいう結構、ショボイ理由で停電とか制限給電されちゃうこともあるという実態。
つまりは、決して現状では電気会社って儲かる商売じゃないみたいなのです。
モンゴルは水道公社も電気関係も今後はPPPを導入していきたいみたいなのですが、水道公社にいたっては、累積赤字がどこも結構たまっていて、それは彼らの経営が下手だから、ではなく、ひとえに料金体系が国あるいは地方自治体によって決められちゃうため、経営努力だけでは乗り越えられない壁があるっていうのが現状。
ここ15年ぐらい発電所とかの経営関係とかの状況にはノータッチだから詳しいことはわからないのですが、たぶん、どこの公社も似たような赤字経営なんじゃないかなぁ?
そんな感じでConcession lawが2010年に国会で承認され、PPP実施の環境は整ったー!とモンゴル側は報道してたり、お役人様たちもコメントしてるんだけど・・・ほんとかなぁ?
ただ、モンゴルの経済成長は爆発的になり、3年後ぐらいには一人当たりのGDPは$3,000超えるとか$5,000に達するとかいう予測もされちゃってるくらいなのです。といっても鉱山開発による天然資源輸出などでの収入が増えるだけで、たぶん、われら庶民にはあんまり関係ないというか、むしろ、インフレとかいろんなことで圧迫されちゃうんだろうな、と懸念していたりするのです。あぁ、小心者。
まぁ、世界各国からの入札に参加しようかなぁ、という人たちが集まっている中での、しばしば停電というのは、電機業界のパフォーマンスなのかしら?とうがってみちゃうわけです。
「ほら、ウランバートルでは頻繁に停電してるでしょ。これからの発展に必要な電気がないってのはとっても困るのです。なんとかしてぇ」みたいな?
というのも、普段から停電はしばしばあるこの街ですが、1日に、5回も6回も(外出中は気がつかないからもっとかも?)停電するっていうのは、過去10年間の在住経験でも、初めてのことだからです。
停電があると、いつ、電源が落ちるかわからない、ってことでうっかりスカイプなどでチャットとかネットで打ち合わせなんてしてられない。
そうなってくると、やれることって少なくなる。
仕事自体のモチベーションが維持できない。
ネットサーフィンして遊んじゃおっか?
とグダグダ状態になってしまいます。
そんなこともあるので、私としてもモンゴル国内の電気が安定的に供給される、ということはとても歓迎すべきことなのです。
まぁ、住民を巻き込んでの停電パフォーマンスの成果が入札に反映されることを期待します・・・と日記には書いておこう。
モンゴルだるまでした。
PC作業をする場合は、バッテリーが長持ちするタイプのノートパソコンがおすすめです。
デスクトップなどの場合、データがぶっとんだり、電圧降下とか過電圧とかでACアダプターがぶっとぶこともあります。


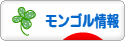
にほんブログ村
大体1時間ぐらいで復旧しているのですが、うちだけでなく、点々とあちこちで停電らしい。
折しも、本日は、第5火力発電所プロジェクトクトの入札希望者の現場視察+説明会の日。
そんなことから、久々の計画停電(抜き打ち)じゃないかしら、とうがった見方をしながら、馬乳酒をかっくらって酔っぱらっている私です。
こんばんは。モンゴルだるま@モンゴルです。
草原では、クリーンエネルギーとバイオマス燃料のみ使用のエコライフを営んでおります。
モンゴル語通訳・翻訳・コーディネーター・リサーチャーなど、モンゴルに関わるいろんなことを、頼まれたら、「はいよ」と引き受ける気のいい庶民な兼業遊牧民であります。
さて、第5火力発電所ってなぁに?おいしいの?という方のために。
90年代に、ちょいと第4火力発電所の日本政府援助プロジェクトにかかわらせていただいて聞きかじった知識などを披露してみますね。
なにせ、まだ学生時代の助っ人通訳だったし、子供で難しいことわかんなぁい、っていうハタチそこそこの小娘だったころの(そう、ゴビ砂漠では恐竜の卵がゴロゴロしていた頃)話なので、うろ覚えっていうところもあるから、詳しい人、訂正あったら、こっしょり教えてくださいね。
さて、今、モンゴル国内には4か所の火力発電所が稼働しております。
ウランバートル市内にある第2、第3、第4火力発電所+南ゴビのツォグトツェツェーというソムの近くの石炭鉱山を開発している民間企業が持ってる小規模火力発電所です。
第1火力発電所は、規模が小さいうえに老朽化がひどく、いつ事故がおきてもおかしくない、という状態なので、そのまま放置・閉鎖状態です。
そして、第3、第4(メインは第4)火力発電所が主にウランバートル市の暖房供給とモンゴル全国の電気供給の8割以上を賄っております。
第3火力発電所はアメリカの援助で、第4火力発電所は日本の2期にわたる無償援助と2回の円借款によるプロジェクトで改修工事が行われたわけですが、第3火力発電所は、もはや一部機材の交換や修理だけではおっつかないくらいな状態だったりするようです。
しかし、ウランバートルのみならず、鉱山開発が活発化すれば、それにともない重工業のプラントも増える→電力需要はますます増える、という状態。
そんななかで、第5火力発電所計画は10年ぐらい前から話はされていたものの、これまで、なかなか実現化に至らなかった大型案件のひとつというわけ。
うっわー・・・ざっくりすぎる?でも、あんまりオタッキーな説明をしてもね。
アメリカの援助でリハビリテーションが行われた第3火力発電所の設備を徐々に更新(設備の入れ替え)をしながら、150MW規模のプラントを3基設置して450MW規模にする、という計画。
アジア開発銀行(ADB)のコンサルタントチームが詳細設計まで行ったところで、はれて、今回の入札公示となったわけです。
このプロジェクトの難しそうなところは、プラント建設だけでなく、その後の発電供給オペレーションもカバーしなきゃいけないってこと。
いわゆるPPP(Public/パブリック(官)・Private/プライベート(民)・Partnershipパートナーシップ(提携))でその後の運営をやっていきましょうってことなのですが・・・
正直、モンゴルでPPPって成り立つの?という素朴な疑問があるのです。
庶民の私たちにとっては、電気代が過去4年の間に、ほぼ2倍に単価が値上げされるっていうのは、ひぃー!っていう生活費の圧迫以外の何物でもないのですが、でも、電気供給側からすると、世界的に見てもモンゴルの電気代って安いのだそうです。
来年度からは徐々に電気料金課金システムの縛りが緩み、自由化になる、とか民間企業の売電業務が認められるようになる法整備が進んでいるわけですが、今のところ、発電所も送電サービス(高圧電線で電気を送る)も給電サービス(一般家庭や企業・団体など個別の物件に電気を供給管理する)も全部、国有株式会社(いわゆる国営企業)なのです。
そして、しばしば、停電になったりするのですが、それは需要量に対しての供給量が足りない、というだけでなく、ぶっちゃけ、石炭代金の支払いが滞って、石炭備蓄が足りなくなった、とかいう結構、ショボイ理由で停電とか制限給電されちゃうこともあるという実態。
つまりは、決して現状では電気会社って儲かる商売じゃないみたいなのです。
モンゴルは水道公社も電気関係も今後はPPPを導入していきたいみたいなのですが、水道公社にいたっては、累積赤字がどこも結構たまっていて、それは彼らの経営が下手だから、ではなく、ひとえに料金体系が国あるいは地方自治体によって決められちゃうため、経営努力だけでは乗り越えられない壁があるっていうのが現状。
ここ15年ぐらい発電所とかの経営関係とかの状況にはノータッチだから詳しいことはわからないのですが、たぶん、どこの公社も似たような赤字経営なんじゃないかなぁ?
そんな感じでConcession lawが2010年に国会で承認され、PPP実施の環境は整ったー!とモンゴル側は報道してたり、お役人様たちもコメントしてるんだけど・・・ほんとかなぁ?
ただ、モンゴルの経済成長は爆発的になり、3年後ぐらいには一人当たりのGDPは$3,000超えるとか$5,000に達するとかいう予測もされちゃってるくらいなのです。といっても鉱山開発による天然資源輸出などでの収入が増えるだけで、たぶん、われら庶民にはあんまり関係ないというか、むしろ、インフレとかいろんなことで圧迫されちゃうんだろうな、と懸念していたりするのです。あぁ、小心者。
まぁ、世界各国からの入札に参加しようかなぁ、という人たちが集まっている中での、しばしば停電というのは、電機業界のパフォーマンスなのかしら?とうがってみちゃうわけです。
「ほら、ウランバートルでは頻繁に停電してるでしょ。これからの発展に必要な電気がないってのはとっても困るのです。なんとかしてぇ」みたいな?
というのも、普段から停電はしばしばあるこの街ですが、1日に、5回も6回も(外出中は気がつかないからもっとかも?)停電するっていうのは、過去10年間の在住経験でも、初めてのことだからです。
停電があると、いつ、電源が落ちるかわからない、ってことでうっかりスカイプなどでチャットとかネットで打ち合わせなんてしてられない。
そうなってくると、やれることって少なくなる。
仕事自体のモチベーションが維持できない。
ネットサーフィンして遊んじゃおっか?
とグダグダ状態になってしまいます。
そんなこともあるので、私としてもモンゴル国内の電気が安定的に供給される、ということはとても歓迎すべきことなのです。
まぁ、住民を巻き込んでの停電パフォーマンスの成果が入札に反映されることを期待します・・・と日記には書いておこう。
モンゴルだるまでした。
PC作業をする場合は、バッテリーが長持ちするタイプのノートパソコンがおすすめです。
デスクトップなどの場合、データがぶっとんだり、電圧降下とか過電圧とかでACアダプターがぶっとぶこともあります。


にほんブログ村