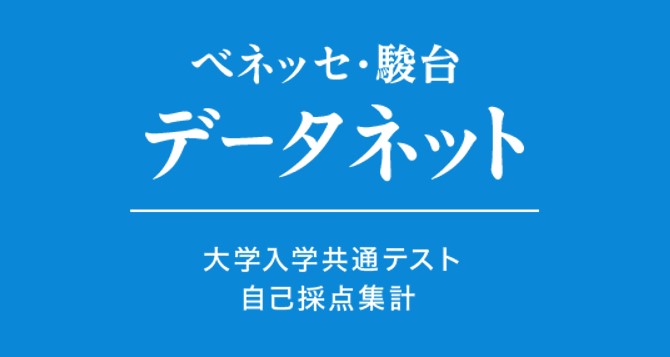なんかアメブロ1日メンテが入ってましたね。
さて。
共通テストが終了したら自己採点です。
正解・配点が各予備校のホームページや翌日の新聞などに公開されますので、それをみながら〇つけする方法もありますが、自分の解答をポチポチ押していくと自動で採点して総合点まででるチェッカーが色々でてきますので、それを利用すると簡単ではやいです。
自己採点した点数をその日のうちにフォームで高校に送るところもありますが、だいたい翌日学校に登校してリサーチを記入→提出します。
リサーチとは全国の受験生の共通テスト自己採点結果を集計したうえで、各予備校等が分析し、国公立大・私立大共通テスト利用入試の合格可能性判定を行うものです。
前にも書きましたが、共通テストの結果は受験が終わるまでわかりませんので、自己採点+各予備校のリサーチによる手助けという何とも頼り無い手段をもとに出願しなくてはならないのです。
受験生が多いから仕方ないのかもしれませんが、翌日に正式な結果が出た中学受験の日能研ってすごいなぁ…みたいなことがよぎります。
マークシートだからそんなに自己採点間違えないでしょう…と思う方もいるでしょうが、これがきちんと間違えずにマークできる&書き写してくる子は意外と多くないそうです。高3のはじめの模試の自己採点では、ピタリ賞はクラスで1人か2人なんて話もききます。
なので多少模試を経験して慣れているとは思いますが、そこまで自分の子供を信じられない悲しさよ。
ネットでリサーチを出せるところもありますが、私の周りのほとんどのお友達のお子さんの学校は共通テスト翌日の16日に高校に登校して駿台&ベネッセと、河合塾に提出してきたようです。
その結果は紙で20日に渡されるので再び登校しましたが、だいたいその前に各予備校でネット判定をみることができます。なので紙でもらうころにはもう知ってるよ…的な感じではあります。
このリサーチは自分の立ち位置を把握するのと同時に、国公立の受験校を変更する時なんかにも使います。
ちなみに2023年の国公立大2次試験の出願期間は1月23日(月)から2月3日(金)でした。
そう考えるとリサーチのあとにすぐ出願がはじまる感じですよね。
共通テストリサーチの結果などを参考にすみやかに出願校を決定する必要があるのですが、決断をくだすとなると結構タイトなスケジュール。これまでひたむきに志望校をめざしていた方にとってはえぇぇ…です。
それまでの模試でドッキング判定といって、共通テスト模試と記述模試を組み合わせて国公立大学の判定を出していたと思うのですが、この本番の共通テストリサーチでも駿台や河合の最後の記述模試の数値を入力すると、共通テストの結果と組み合わせて国公立二次試験の可能性をドッキング判定をしてくれたりもします。
高校3年生は何かと模試が多いので面倒な部分もありますが、駿台と河合のリサーチをもとに判定したいならばこの最後の記述模試はとても大事なもの、受けておいた方がいいものになります。
残念ながら息子はこの最後の模試の時にコロナ陽性で自宅療養中。結局模試を受けられずに終わりました。
共通テストリサーチだけじゃなく、最後の記述模試で私大の併願校なんかも面談で話し合ったりするというのでガックリ…。
なので我が家に関してはドッキング判定も出ないし、なんだかよくわからん…でリサーチ終了しました。
私大進学を考えていない国立熱烈志望だと、リサーチ結果をみて安全な国立に流れる傾向もあります。バンザイA判定で余裕と思いきや蓋をあけたら人数がものすごく増えていて焦ったみたいな話をお友達から聞いたりもしました(結果的にそのお友達のお子さんは合格していたので、リサーチ正しいとなりますね)
共通テスト&リサーチを受けるまではあまりピンときていなかったのですが、足切りがあるケースの場合は注意が必要です。
足切りというのは国公立大学でおこなわれるものなのですが、大学の募集人員に対して志願者が多かった場合にその人数を超えてしまうと(3倍までとか4倍までとかあらかじめ倍率が決まっているのですが)、一定の水準に達しなかった受験生に対して2次試験の受験資格を与えないことがあります。
わかりにくいので、ニュースにもなっていた今年の東大を例にあげてみましょう。
2月3日に出願をしめきったところ、理科二類の志願者が多く、3.5倍の足切りラインに対して4.3倍の人数が集まりました。
共通テストの成績で上からとっていくので、14日に発表される第一次段階選抜の足切りラインである共通テストの点数が理科二類は結構高くでました。
この図でおわかりかと思うんですが、志願者増による足切りがなければどんなに低い点数でも二次試験をうけることは可能ですが(おそらく文科三類は足切りなし)、理科二類志望者は900点満点中711点がなければ足切りで涙をのんだことになります。
これはもちろん第一次段階選抜の結果が2月14日にでてわかるのですが、ある程度はリサーチ結果から予測をつけることができます。
事前にリサーチから受験者動向や予想点をだしているところも多いのでそちらをチェックして、危険な場合は対策を考える必要があるのです。
共通テストを自己採点して、リサーチ結果で危ないラインにいるなと思ったら、毎日発表される各国立の志願者状況をギリギリまでみて出願を考えたり、東大なんかですと科類を変更したりしないと、記念受験どころか受けに行くことさえできずに終わる…という悲劇もおきます。
ドラゴン桜2で藤井が急に文転する話もありましたが、文系と理系では足切りラインの点数がそもそも違う。二次試験の科目が得意で文転可能ならそれもありという力業でしたが。(文科うけるなら社会を共通テストで2科目うけていなくてはいけない?)
読んだときはピンときませんでしたが、実際に息子が国立受験に直面してわかるこの感じね!足切りってそーゆーことね!みたいな。
我が家はそこまで国立熱烈志望でもなかったので、志望校は変える気がなくさっさと決めたところに出願したのですが、実際の出願の数をみると模試の時の動向とずいぶん違っていて、受験って蓋をあけるまではわからないものだなぁと思ったものです。
「共通テストはほどほどで大丈夫。二次が勝負だ!」とか、「二次の配点が大きい大学だから共通テストが悪くても逆転できる」とか思っていても足切りの前には無情。また逆に共通テスト配点が大きい国立を考えていたけれど、共通テストで大こけしたら2次の配点の大きいところにかえないといけないのです。
共通テストを甘くみてはいけません。
これは後期の試験にもいえることで、後期の国立はみかけの倍率がものすごいことになります。すごいところは50倍とかこえちゃったりします。
なぜなら前期と後期の出願が同じ時期におこなわれるからです。
つまり前期に受かるかどうかわからない中で、何としても国立にうかりたい層は後期に出願しないといけないのです。
そんな訳で、募集人数の少ない後期の大学には人数が集中してすごいことになり(実際は受かった人は受けにこないで欠席者が増える)足切り点が高かったりするケースもあります。
すると、受ける前に向こうからお断りの連絡がくることになるので、このケースに関しては結構メンタルにきます。
付き合うかどうかわからないけれど、デートの約束をいれてみたら、なんかデートの前に振られた…みたいなね。
「この大学を受けたいから受けるんだ!」という熱意は大事ですが、共通テストの点数が達しているのかどうかということは非常に大事なことなのです。でもこれ、リサーチの時まで私もあまりピンときていませんでした。高校から本人に話はあったのかもしれませんが、うちは息子が学校であったことを話すタイプではないので…
また国立だけではなく、私大の話もしますが。
共通テスト利用入試はだいたい共通テストを受ける前に出願締め切りになります。つまり体感も自己採点も関係ないギャンブルです。
目安になるのは過去の模試の点数だけ。
実際の試験でとれるかどうかわからないところに出願する怖さ。こんな入試システムってどうなのよ?
しかし、早稲田や一部私大の国公立型科目の共通テスト利用なんかは共通テスト後も受け付けてくれたりするので、結果をみて出願したいという人はリサーチを見て急いで出願することが可能。
でもだいたいそのあたりに出願してくる層は確実に点数とれて合格をもらいにくる層か、ボーダー前後でワンチャンにかける層なので、ボーダー以下ですと早稲田なんかはぐっと厳しい戦いになります。
そのボーダーを判断するのがネットのリサーチです。(続く)