*2月11日エントリー の続きです。
R大学文学部史学科の院生・あんみつ君![]() 、今回は近現代史のしらたま教授
、今回は近現代史のしらたま教授![]() との歴史トークで、テーマは天保の改革周辺。
との歴史トークで、テーマは天保の改革周辺。
本日は、大塩中斎大坂に檄す のおはなしです。

![]()
![]()
![]()
あんみつ![]() 「しらたま先生、半世紀に渡る十一代将軍徳川家斉の治世後半はごく近臣による放漫な政治。そこに降ってわいたのが大塩平八郎の乱です(←「大御所半世紀⑫(終)」 から続く)。規模は大きくないとはいえ百姓一揆のたぐいでなく、幕臣が明確な思想をもって幕政批判の火の手を挙げたんですから」
「しらたま先生、半世紀に渡る十一代将軍徳川家斉の治世後半はごく近臣による放漫な政治。そこに降ってわいたのが大塩平八郎の乱です(←「大御所半世紀⑫(終)」 から続く)。規模は大きくないとはいえ百姓一揆のたぐいでなく、幕臣が明確な思想をもって幕政批判の火の手を挙げたんですから」
しらたま![]() 「大塩平八郎正高は大坂天満、代々東町奉行の与力の家柄だ。遠山金四郎と同い年の寛政五年(1793)に生まれ、中斎と号する陽明学者でもあった。弁の立つ美男子だったけど、結核を患っていたので体は弱く、祖母の実家筋西田格之助を見込んで養子にもらっている」
「大塩平八郎正高は大坂天満、代々東町奉行の与力の家柄だ。遠山金四郎と同い年の寛政五年(1793)に生まれ、中斎と号する陽明学者でもあった。弁の立つ美男子だったけど、結核を患っていたので体は弱く、祖母の実家筋西田格之助を見込んで養子にもらっている」
あんみつ![]() 「大塩は東町奉行・高井山城守の信任を得て剛腕を振るいます。有名なのは西町与力、弓削新左衛門の汚職横暴を摘発したことと、キリシタン系カルト教団との対決です。京八坂の陰陽師、豊田 貢(みつぎ)なる54歳の女性が教祖でした」
「大塩は東町奉行・高井山城守の信任を得て剛腕を振るいます。有名なのは西町与力、弓削新左衛門の汚職横暴を摘発したことと、キリシタン系カルト教団との対決です。京八坂の陰陽師、豊田 貢(みつぎ)なる54歳の女性が教祖でした」
しらたま![]() 「開祖は水野軍記という宮家の青侍だったが、すでに物故していた。教団は女性ばかりを虜にして家の金品を上納させるというまさにカルト。大塩の探索でこれがキリシタンであることがわかり、豊田及び主だった弟子を処刑した。彼女らは磔柱で ‟センスマルハライソ(デウス、マリアのおわすパラダイスへ)” と唱え続けたという」
「開祖は水野軍記という宮家の青侍だったが、すでに物故していた。教団は女性ばかりを虜にして家の金品を上納させるというまさにカルト。大塩の探索でこれがキリシタンであることがわかり、豊田及び主だった弟子を処刑した。彼女らは磔柱で ‟センスマルハライソ(デウス、マリアのおわすパラダイスへ)” と唱え続けたという」
あんみつ![]() 「こうした功績で大塩の名は高まりましたが、同役を摘発したことで嫉みも買い、高井奉行の退職により大塩も38歳で隠居。自宅を <洗心洞> と名付け私塾を開き、学究に専念します。退隠後の大坂奉行所はあまり評判良くなかったようですね。新東町奉行・跡部良弼(よしただ)は江戸の老中水野忠邦の実弟であり専断。町人より幕府の方を気にするタイプです」
「こうした功績で大塩の名は高まりましたが、同役を摘発したことで嫉みも買い、高井奉行の退職により大塩も38歳で隠居。自宅を <洗心洞> と名付け私塾を開き、学究に専念します。退隠後の大坂奉行所はあまり評判良くなかったようですね。新東町奉行・跡部良弼(よしただ)は江戸の老中水野忠邦の実弟であり専断。町人より幕府の方を気にするタイプです」
しらたま![]() 「当時、民生は窮迫するばかりだった。冷夏多雨、蝗害や天災、疫病の年が続き、東北地方を中心に <天保の大飢饉> と呼ばれる大惨事だ。かつての松平定信による寛政改革、社会事業の効果で(→「大御所半世紀③」)天明大飢饉級の大量餓死こそ免れたが、不作により米価は全国的に急騰する」
「当時、民生は窮迫するばかりだった。冷夏多雨、蝗害や天災、疫病の年が続き、東北地方を中心に <天保の大飢饉> と呼ばれる大惨事だ。かつての松平定信による寛政改革、社会事業の効果で(→「大御所半世紀③」)天明大飢饉級の大量餓死こそ免れたが、不作により米価は全国的に急騰する」
あんみつ![]() 「困窮した農村では逃散、哀訴を経て全国的な一揆・打ちこわしに発展します。とくに天保七年(1836)に三河国加茂郡大一揆、甲斐国郡内騒動と、万単位の農民が蜂起したことは幕閣を震撼させ、御三家・水戸斉昭をも恐怖させています(『戊戌封事』)」
「困窮した農村では逃散、哀訴を経て全国的な一揆・打ちこわしに発展します。とくに天保七年(1836)に三河国加茂郡大一揆、甲斐国郡内騒動と、万単位の農民が蜂起したことは幕閣を震撼させ、御三家・水戸斉昭をも恐怖させています(『戊戌封事』)」
しらたま![]() 「大坂には全国の米を集め、現物と先物取引で価格を安定させる <堂島米会所> がある。跡部奉行は江戸優先の幕命に従い、窮民の買い米を許さずせっせと廻米を江戸に送ったので、大坂町民の怨嗟を招いていた」
「大坂には全国の米を集め、現物と先物取引で価格を安定させる <堂島米会所> がある。跡部奉行は江戸優先の幕命に従い、窮民の買い米を許さずせっせと廻米を江戸に送ったので、大坂町民の怨嗟を招いていた」
菊池溶斎筆 大塩平八郎画像
あんみつ![]() 「大塩は与力になっていた養子格之助を通して跡部奉行に諫言しますが、かえって口出し無用と反発されました。さらに大塩は三井ら豪商に貧民救済を要請するも、彼らは廻米の手数料利権がありますから、そんなことより役人の接待で豪遊三昧です。いつの世も上流階級は浮世離れ...」
「大塩は与力になっていた養子格之助を通して跡部奉行に諫言しますが、かえって口出し無用と反発されました。さらに大塩は三井ら豪商に貧民救済を要請するも、彼らは廻米の手数料利権がありますから、そんなことより役人の接待で豪遊三昧です。いつの世も上流階級は浮世離れ...」
しらたま![]() 「天保八年(1837)二月、大塩は義憤のままに洗心洞の蔵書5万巻を売って1000両をつくり、貧農や部落民1万戸に1朱(現:約5000円)ずつ配った。同時に大砲や武器弾薬の調達を急ぎ、西町奉行堀伊賀守の市中巡見のすきに挙兵、船場に並ぶ豪商を打ちこわす計画を練る」
「天保八年(1837)二月、大塩は義憤のままに洗心洞の蔵書5万巻を売って1000両をつくり、貧農や部落民1万戸に1朱(現:約5000円)ずつ配った。同時に大砲や武器弾薬の調達を急ぎ、西町奉行堀伊賀守の市中巡見のすきに挙兵、船場に並ぶ豪商を打ちこわす計画を練る」
あんみつ![]() 「有名な大塩の檄文は、‟下民の苦天に通じ水を溢らすばかりなるに、諸役人責めを他に帰し、富商の驕奢淫逸は紂王長夜の宴にひとし。願わくばこれら禄盗の者どもを誅戮し、天照皇大神の時代に復さん” ですね。町人は読んでもたぶんわからなかったでしょうけど、貧農や被差別民約300人が参加しました」
「有名な大塩の檄文は、‟下民の苦天に通じ水を溢らすばかりなるに、諸役人責めを他に帰し、富商の驕奢淫逸は紂王長夜の宴にひとし。願わくばこれら禄盗の者どもを誅戮し、天照皇大神の時代に復さん” ですね。町人は読んでもたぶんわからなかったでしょうけど、貧農や被差別民約300人が参加しました」
しらたま![]() 「一党の同心ひとりが土壇場で裏切り密告したので、二月十九日の決起は8時間ほど実行を早めた。もっとも300人ではおのずから限界がある。大塩方も奉行所も大砲を打ち合い、豪商の屋敷など3389軒、大坂市街の1/5が焦土となった。乱自体は半日で鎮圧され、大塩と格之助は河内から大和へ逃亡。僧形となって大坂に戻り、油掛町の手拭仕入れ、三吉屋に匿われる」
「一党の同心ひとりが土壇場で裏切り密告したので、二月十九日の決起は8時間ほど実行を早めた。もっとも300人ではおのずから限界がある。大塩方も奉行所も大砲を打ち合い、豪商の屋敷など3389軒、大坂市街の1/5が焦土となった。乱自体は半日で鎮圧され、大塩と格之助は河内から大和へ逃亡。僧形となって大坂に戻り、油掛町の手拭仕入れ、三吉屋に匿われる」
あんみつ![]() 「騒ぎを知った大坂城代はずいぶんうろたえたようですね。指揮を執った跡部奉行は衆人の前で馬から落ち、笑いものになったとか。町人は焼けた家屋の復興で公共工事の仕事を得、大塩をありがたがったと言います。そもそも貧民に焼かれて困る財産なんてなかったですからね」
「騒ぎを知った大坂城代はずいぶんうろたえたようですね。指揮を執った跡部奉行は衆人の前で馬から落ち、笑いものになったとか。町人は焼けた家屋の復興で公共工事の仕事を得、大塩をありがたがったと言います。そもそも貧民に焼かれて困る財産なんてなかったですからね」
しらたま![]() 「逃亡した大塩親子が大坂に隠れ住んだのも、そういった事件を起こした自身の評判を知りたかったからだろう。40日ののち三吉屋に捕吏が踏み込んだので、大塩と格之助は火を放ち、格闘のすえ自刃。大塩45歳、格之助27歳。遺体は見せしめのため磔刑に処された」
「逃亡した大塩親子が大坂に隠れ住んだのも、そういった事件を起こした自身の評判を知りたかったからだろう。40日ののち三吉屋に捕吏が踏み込んだので、大塩と格之助は火を放ち、格闘のすえ自刃。大塩45歳、格之助27歳。遺体は見せしめのため磔刑に処された」
あんみつ![]() 「江戸に事件が報じられたのは一週間後。老中たちは遅くまで爾後策を協議するほど動揺しました。水戸斉昭も ‟大城の奸賊容易ならざる(公務員から反乱者が出るなんてただごとじゃない)” と嘆いています。鎮圧は早かったのに、農民一揆より幕臣の反旗がショックだったんですね」
「江戸に事件が報じられたのは一週間後。老中たちは遅くまで爾後策を協議するほど動揺しました。水戸斉昭も ‟大城の奸賊容易ならざる(公務員から反乱者が出るなんてただごとじゃない)” と嘆いています。鎮圧は早かったのに、農民一揆より幕臣の反旗がショックだったんですね」
しらたま![]() 「六月には越後柏崎で、国学者平田篤胤の高弟・生田 万(よろず)が大塩門人を称して陣屋に斬り込むなど各地で影響が残った。四月に家斉は退隠、徳川家慶が十二代将軍になっており、山積する政治課題に首相・水野忠邦が当たることになる。それじゃ、次にその水野老中の来歴を見てみよう」
「六月には越後柏崎で、国学者平田篤胤の高弟・生田 万(よろず)が大塩門人を称して陣屋に斬り込むなど各地で影響が残った。四月に家斉は退隠、徳川家慶が十二代将軍になっており、山積する政治課題に首相・水野忠邦が当たることになる。それじゃ、次にその水野老中の来歴を見てみよう」
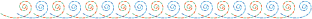
今回はここまでです。
天保の大飢饉の惨禍は農村の貧窮を招き、一揆打ちこわしは地方から都市に伝播。ついに幕臣大塩平八郎の乱を引き起こしました。
次回、水野忠邦青雲の要路 のおはなし。
それではごきげんよう![]()
![]() 。
。
