*10月18日付記事 の続きです。
R大学文学部史学科の院生・あんみつ君![]() は、今回はしらたま教授
は、今回はしらたま教授![]() との歴史トークで、テーマは徳川家斉の大御所時代。
との歴史トークで、テーマは徳川家斉の大御所時代。
本日は、三翁三佞人のおはなしです。

![]()
![]()
![]()
あんみつ![]() 「しらたま先生、文化十四年(1817)八月、老中・松平信明が現職のまま58歳で亡くなりました。盟友の牧野忠精もすでに辞任していたので、松平定信以来の <寛政の遺老> はこれで総退場です。将軍家斉は45歳の壮年になっていました」
「しらたま先生、文化十四年(1817)八月、老中・松平信明が現職のまま58歳で亡くなりました。盟友の牧野忠精もすでに辞任していたので、松平定信以来の <寛政の遺老> はこれで総退場です。将軍家斉は45歳の壮年になっていました」
しらたま![]() 「新しい首相は水野出羽守忠成(ただあきら,1762~1834)。三河譜代の家柄だが、浮沈があってこのときは沼津3万石とさほど大身ではなかった。彼自身は入り婿の養子だから、門閥ではなく個人として将軍家斉の信任を得たという意味では、かつての田沼意次と共通したものがある」
「新しい首相は水野出羽守忠成(ただあきら,1762~1834)。三河譜代の家柄だが、浮沈があってこのときは沼津3万石とさほど大身ではなかった。彼自身は入り婿の養子だから、門閥ではなく個人として将軍家斉の信任を得たという意味では、かつての田沼意次と共通したものがある」
あんみつ![]() 「家斉の持病だった、偏頭痛を治す特技があったらしいですね。頭痛と吐き気がするたびに、将軍になるはずだった家基の怨念と怖れていた家斉には、いちばん心強い側近です」
「家斉の持病だった、偏頭痛を治す特技があったらしいですね。頭痛と吐き気がするたびに、将軍になるはずだった家基の怨念と怖れていた家斉には、いちばん心強い側近です」
しらたま![]() 「偏頭痛の原因は一概にはわかっていないから、彼が何をやったのかは不明なんだが、生薬の本をみると、人によってはショウガで鎮吐作用が生ずるとあった。ショウガは家斉の大好物だったから、もしかしたら忠成が勧めたのかも知れない」
「偏頭痛の原因は一概にはわかっていないから、彼が何をやったのかは不明なんだが、生薬の本をみると、人によってはショウガで鎮吐作用が生ずるとあった。ショウガは家斉の大好物だったから、もしかしたら忠成が勧めたのかも知れない」
あんみつ![]() 「忠成といえば、家老の土方縫殿介(ひじかた・ぬいのすけ)が有名ですね。主君を出世させるためには幕閣の有力者と仲良くならなきゃいけない。そこで腹痛を装って面識のない大身の屋敷の門を叩いて休ませてもらい、後日、無礼のお詫びといって、莫大な贈りものをして取り入ったとか」
「忠成といえば、家老の土方縫殿介(ひじかた・ぬいのすけ)が有名ですね。主君を出世させるためには幕閣の有力者と仲良くならなきゃいけない。そこで腹痛を装って面識のない大身の屋敷の門を叩いて休ませてもらい、後日、無礼のお詫びといって、莫大な贈りものをして取り入ったとか」
しらたま![]() 「雨の日にわざとずぶ濡れになり、着替えを頼んで礼金をはずんだという話もある。とにかく相当カネを使ってコネを作り、寺社奉行から若年寄、老中首座にまで上り詰めたわけだ」
「雨の日にわざとずぶ濡れになり、着替えを頼んで礼金をはずんだという話もある。とにかく相当カネを使ってコネを作り、寺社奉行から若年寄、老中首座にまで上り詰めたわけだ」
あんみつ![]() 「当時の有名な附句に 『水の出てもとの田沼となりにける』 とあるくらい、世間に田沼意次の再来を思わせたんですね。以後、幕府の役職は政争・利権の具となり、お友だち内閣による情実や斟酌で政治が動かされるようになります」
「当時の有名な附句に 『水の出てもとの田沼となりにける』 とあるくらい、世間に田沼意次の再来を思わせたんですね。以後、幕府の役職は政争・利権の具となり、お友だち内閣による情実や斟酌で政治が動かされるようになります」
しらたま![]() 「忠成政権の腹心となったのは家老の土方と、若年寄の田沼意正。彼の父はあの田沼意次で、四男だったので水野家の養子に出されていた経歴があり、忠成とつながりがあった。そして林肥後守忠英(ただふさ)。彼も家斉の小姓として信頼され、旗本から大名にまで取り立てられた成り上がり者だ」
「忠成政権の腹心となったのは家老の土方と、若年寄の田沼意正。彼の父はあの田沼意次で、四男だったので水野家の養子に出されていた経歴があり、忠成とつながりがあった。そして林肥後守忠英(ただふさ)。彼も家斉の小姓として信頼され、旗本から大名にまで取り立てられた成り上がり者だ」
あんみつ![]() 「この林 忠英と水野美濃守忠篤、そして美濃部筑前守茂育(もちなる)は、家斉の側近として取り入った <三佞人> と呼ばれ、幕閣内外で悪評を受けました」
「この林 忠英と水野美濃守忠篤、そして美濃部筑前守茂育(もちなる)は、家斉の側近として取り入った <三佞人> と呼ばれ、幕閣内外で悪評を受けました」
しらたま![]() 「水野忠篤は叔母が家斉若かりしころの愛妾で、その縁で御側御用取次に任じられた。美濃部は将軍の日用品を管理する御小納戸頭取に過ぎないが、将軍の威を恃んで幅を利かせた中級旗本だ」
「水野忠篤は叔母が家斉若かりしころの愛妾で、その縁で御側御用取次に任じられた。美濃部は将軍の日用品を管理する御小納戸頭取に過ぎないが、将軍の威を恃んで幅を利かせた中級旗本だ」
あんみつ![]() 「老中とかでなく、まさに将軍のごく近辺、側近中の側近が幕閣を牛耳っていたんですね。その究極が中野播磨守清茂(1765~1842)でしょうか。家斉の小姓頭取でしかありませんが、下総中山の法華経寺の僧日啓の娘・お美代を養女にし、彼女が家斉の側室の中でトップクラスの寵愛を受けたことで大実力者にのし上がりました」
「老中とかでなく、まさに将軍のごく近辺、側近中の側近が幕閣を牛耳っていたんですね。その究極が中野播磨守清茂(1765~1842)でしょうか。家斉の小姓頭取でしかありませんが、下総中山の法華経寺の僧日啓の娘・お美代を養女にし、彼女が家斉の側室の中でトップクラスの寵愛を受けたことで大実力者にのし上がりました」
しらたま![]() 「本所向島にあった邸宅には大名や幕臣、大商人が山のような金品をもって “お願いごと” に上がったという。門前にはわざわざ中野への献上品をあつらえる店が出来たというから相当な羽振りだ。晩年は隠居剃髪して <石翁> と号し、引き続き自由に千代田の城に出入りしては家斉の遊び相手を務めたという」
「本所向島にあった邸宅には大名や幕臣、大商人が山のような金品をもって “お願いごと” に上がったという。門前にはわざわざ中野への献上品をあつらえる店が出来たというから相当な羽振りだ。晩年は隠居剃髪して <石翁> と号し、引き続き自由に千代田の城に出入りしては家斉の遊び相手を務めたという」
あんみつ![]() 「中野石翁に、穆翁こと家斉の実父・一橋治済、それに家斉夫人の父・島津重豪(しげひで)が号した栄翁を総称して <三翁> と呼ばれました。中級旗本の中野が将軍家や薩摩藩主と同列とは、いかに権勢を振るったかわかります」
「中野石翁に、穆翁こと家斉の実父・一橋治済、それに家斉夫人の父・島津重豪(しげひで)が号した栄翁を総称して <三翁> と呼ばれました。中級旗本の中野が将軍家や薩摩藩主と同列とは、いかに権勢を振るったかわかります」
しらたま![]() 「徳川将軍の正室が外様大名の大藩島津氏というのは少々奇異に思える。これはまだ家基健在だったころ、重豪と一橋治済のあいだで3歳の豊千代(家斉)と茂姫の婚約を決めていたからだ。重豪は将軍の義父として贅沢な暮らしに耽ったが、西洋文化に魅せられてオランダ語を覚え、シーボルトとの交流を愉しむ一面もあった。曾孫の島津斉彬を誰より愛したのは彼だ」
「徳川将軍の正室が外様大名の大藩島津氏というのは少々奇異に思える。これはまだ家基健在だったころ、重豪と一橋治済のあいだで3歳の豊千代(家斉)と茂姫の婚約を決めていたからだ。重豪は将軍の義父として贅沢な暮らしに耽ったが、西洋文化に魅せられてオランダ語を覚え、シーボルトとの交流を愉しむ一面もあった。曾孫の島津斉彬を誰より愛したのは彼だ」
あんみつ![]() 「将軍家斉の周辺はみな莫大な贈賄で贅を尽くしましたが、逆にいうとそれだけで、政治的な経綸はぜんぜんないんですね。権力を握ってあれをやろう、というんじゃなく、贅沢が維持出来ればいいという」
「将軍家斉の周辺はみな莫大な贈賄で贅を尽くしましたが、逆にいうとそれだけで、政治的な経綸はぜんぜんないんですね。権力を握ってあれをやろう、というんじゃなく、贅沢が維持出来ればいいという」
しらたま![]() 「三翁、三佞人まさに共通して君の言うとおりだ。権力が方法論じゃなく目的になっているんだな。中野石翁の栄達には冗談みたいな秘密があって、中野が家斉の遊び相手をしていた少年時代、木登りをしていて下に落ちて股間を強打、『陰をいたくやぶりて...年のさかりになりても世の中の道しるべくもあらず』 ということになってしまった。現代語にしなくてもわかるだろ(笑)」
「三翁、三佞人まさに共通して君の言うとおりだ。権力が方法論じゃなく目的になっているんだな。中野石翁の栄達には冗談みたいな秘密があって、中野が家斉の遊び相手をしていた少年時代、木登りをしていて下に落ちて股間を強打、『陰をいたくやぶりて...年のさかりになりても世の中の道しるべくもあらず』 ということになってしまった。現代語にしなくてもわかるだろ(笑)」
あんみつ![]() 「あー、はいはい。いや、笑っちゃ可哀想ですかね。中野は女性に興味がなく、大奥に入ることすら許されていたという理由がわかります。目の前でその惨事を見た家斉は、憐れに思って中野を重用し続けた、ということですかぁ」
「あー、はいはい。いや、笑っちゃ可哀想ですかね。中野は女性に興味がなく、大奥に入ることすら許されていたという理由がわかります。目の前でその惨事を見た家斉は、憐れに思って中野を重用し続けた、ということですかぁ」
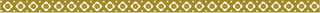
今回はここまでです。
寛政の遺老が退場したあとの徳川家斉後半の治世は、将軍近辺の寵臣が権力の中枢を握る金権政治でした。
次回は経済施策、錬金術とトリクルダウンのおはなし。
それではごきげんよう![]()
![]() 。
。