1.発達凸凹グレーゾーン高学年あるある「失敗を嫌がる」に困っていませんか
小学校3年生頃になると、
「以前できてきたこともやらなくなってきた」
「以前よりも「自分はダメだ」という発言が増えてきた」
といったお母さんの悩みが増えてきます。
そういえばうちの子もそうかも…と心当たりはありませんか?
個人差はありますが、平均的に小学校3年生頃は思春期に入る前のプレ思春期と呼ばれる時期。
発達凸凹グレーゾーンキッズは、プレ思春期に差し掛かると、自分自身を客観視できる脳が育ち始め、周りとの違いに気づき劣等感を抱くようになります。
うまくいかなくて叱責され続けている状態に、自分を見失い始める時期でもあります。
自分を見失ったまま思春期に入ってしまうと、たちまち立ち行かなくなり、
・声をかけても反抗してきて会話にならない
・感情的に怒る
・手をあげるようになる
など、子育ての難しさが増してしまいます。
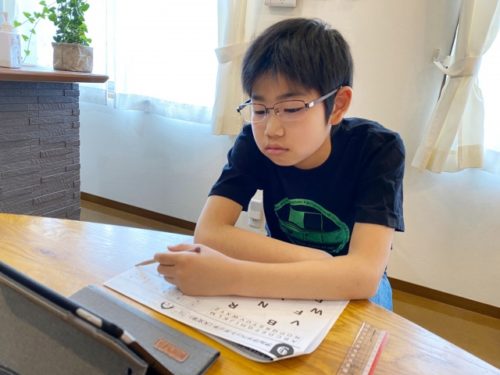
だから、思春期に入る前のプレ思春期までに、壁を乗り越える工夫や努力する力をつけて、思春期という「大人への成長ステップ」をしっかりサポートして自立に導いてあげたいと思います。
2.高学年ADHDキッズのチャレンジが減る理由
発達障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)や自閉症スペクトラム(ASD)のグレーゾーンの子が、高学年を迎えて、意欲的に動けなくなるのには理由があります。その理由を知って、お子さんの行動力を上手に引き出してあげましょう。
1つ目の理由は、ADHDキッズの「怒られすぎ」問題があります。
ADHDキッズは、行動面で先生やお母さんから注意されることがとても多いです。一見本人はケロっとしているように見えますが、怒られた記憶は、脳にネガティブな記憶として蓄積されていきます。
また、子どもの脳は、言葉の意味よりも表情や言葉の響きが先に処理される仕組みになっているため、マイナスなリアクションをしているとお母さんが伝えたい言葉が届きません。
高学年になるまでの間に怒られ、いつもお母さんに怖い表情で対応されるを経験を積みすぎると、自己肯定感が低下して、ネガティブ思考が強くなり、動けなくなるのです。
「どうせやってもできない」
「僕なんて…」
こんな発言が出てきたら要注意です。
2つ目の理由は「ママの焦り」です。
もうすぐ中学生になるお子さんの無気力な様子に焦って、
「しっかりしなさい!」
「どうしたいの?」
「ちゃんとしなさい!」

なんて声をかけてしまうのではないでしょうか?
この声かけ、実は私もよく使っていたんです。
ですが、これかえって裏目に出ます。自信を失い不安になった子は
「自分にはできそうもない」
「ママが期待するほどはできないかもしれない」
と、ますますチャレンジしなくなるのです。
中学生になると、グレーゾーンの子どもを取り巻く環境は厳しくなります。自主性を求められることも増えます。苦手なことにもチャレンジしなければいけない場面も増えていきます。
だから、中学生になる前が実は大切な時期!小学校高学年のうちに、子どもがネガティブ思考を手放して、前に進む工夫や努力ができる力を育てておいてあげましょう!
3.不安でネガティブ思考な息子が失敗を恐れない子になった!
ネガティブ思考を手放して、前に進む工夫や努力ができる力を、私は「壁を乗り越える力」と呼んでいます。
私が、発達科学コミュニケーションを学び実践し、「壁を乗り越える力」を手にした息子がどう変わったかををご紹介します。
私の小4になる息子は今、網を使って魚を捕ることにはまっていますが、安い網でいくら捕まえようと思っても、網が弱くて無理!と嘆いていました。
以前だったら、うまく行かないことがあると「もうやめた!」「もうやらない」と拗ねて、すぐに諦めてばかりいました。
ですが、今の息子はちょっとの失敗でくじけることはなくなりました。「もっとしっかりした立派な網があれば捕まえやすいのでは?」と考えて私に、もっと強い網を買ってもらえないかと、提案することができています。
また以前は、不安が強くて、一人で魚を取りに行くなんて絶対にしなかったのですが、今では一人でも魚を捕りに行ける行動力がつき、あれこれと工夫をして楽しめるようになりました。

こんなふうに何かうまくいかないことがあった時に、わからないことを自分で調べたり、聞いたりできる力を育ててあげられるといいですよね。
4.ママが「やらないこと」を決めると、ADHDグレーゾーンの子は動き出す
私が、息子の「壁を乗り越えるチカラ」伸ばすためにやったのは、たった1つ。「お母さんがやらないこと」を決めることです!
それは、お子さんに対して「マイナスなリアクション」をしない、ということ。
例えば、お子さんの行動に苛立っても、
「眉間にシワを寄せてしかめ面」
「ため息をつく」
「投げやりな言い方をする」
などのリアクションをしないということです。
否定的なリアクションを、上手に肯定的な関わりに変えてしまいましょう。やり方は簡単!
子どもの行動を言葉にして伝えるだけ。
・はみがきしているんだね
・洗濯物をカゴに入れてくれたんだね
・食器を片付けてくれてありがとう
何か「特別なこと」ができたときにするのが肯定ではありません。
お母さんがありのままの自分を認めてくれることで、子どもは自信を取り戻し、「やってみよう!」と動きだすことができるのです。
さらに、子どもがやっていることに興味関心を示してあげるのも効果的です。
「どんなゲームしてるの?」
「難しそうだね〜」
「こんなレベルまでいってるの⁉」
など、声をかけてあげてください。
子どもに寄り添ってあげることで信頼関係も生まれ、いろんなことを相談し合える親子になれますね。

発達障害グレーゾーンの子が、自信を失って不安になって身動きが取れなくなりやすいのが、小学校高学年という時期。
この時期にしっかりと子どもの自信を回復しておいてあげると、子どもは失敗を恐れずに行動できるようになります。
ちょっと苦手なことがあっても「どうやったらできるかなー?」と考えて、工夫してクリアできるようになりますよ!
執筆者:三浦由記子
(発達科学コミュニケーショントレーナー)