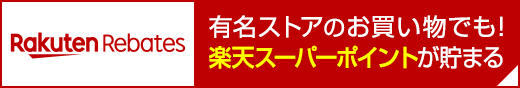新元号の由来にもなった万葉集
新元号である「令和(れいわ)」の発表の際、菅官房長官は万葉集が典拠であると発表しました。
その出典元は下記の通りです。
出典:「万葉集」巻五、梅花歌三十二首并せて序
初春令月、気淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香
[書き下し文]
初春(しょしゅん)の令月(れいげつ)にして、気淑(きよ)く風和(かぜやわら)ぎ、梅(うめ)は鏡前(きょうぜん)の粉(こ)を披(ひら)き、蘭(らん)は珮後(はいご)の香(こう)を薫(かお)らす。
解説
この序の筆者は大伴旅人とされており、旅人宅で梅の花を囲む雅宴で詠まれた歌32首に対する文です。
また、上記は新元号「令和」の出典元となった一部分ですが、全体としては下記のようになっています。
天平二年正月十三日に、師の老の宅に萃まりて、宴会を申く。
時に、初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす。
加之、曙の嶺に雲移り、松は羅を掛けて蓋を傾け、夕の岫に霧結び、鳥は殻に封めらえて林に迷ふ。
庭には新蝶舞ひ、空には古雁帰る。
ここに天を蓋をし、地を座とし、膝を促け觴を飛ばす。
言を一室の裏に忘れ、衿を煙霞の外に開く。
淡然と自ら放にし、快然と自ら足る。
若し翰苑にあらずは、何を以ちてか情をのべむ。
詩に落梅の篇を紀す。
古と今とそれ何そ異ならむ。
宜しく園の梅を賦して聊かに短詠を成すべし。
[現代文]
天平二年正月十三日に、長官の旅人宅に集まって宴会を開いた。
時あたかも新春の好き月、空気は美しく風はやわらかに、梅は美女の鏡の前に装う白粉の如きかおりをただよわせている。
のみならず明け方の山頂には雲が動き、松は薄絹のような雲をかずいてきぬがさを傾ける風情を示し、山のくぼみには霧がわだかまって、鳥は薄霧にこめられては林にまよい鳴いている。
庭には新たに蝶の姿を見かけ、空には年をこした雁が飛び去ろうとしている。
ここに天をきぬがさとし地を座として、人々は膝を近づけて酒杯をくみかわしている。
すでに一座はことばをかけ合う必要もなく睦(むつ)み、大自然に向かって胸襟を開きあっている。
淡々とそれぞれが心のおもむくままに振舞い、快くおのおのがみち足りている。
この心中を、筆にするのでなければ、どうしていい現しえよう。
中国でも多く落梅の詩篇がある。
古今異るはずとてなく、よろしく庭の梅をよんで、いささかの歌を作ろうではないか。



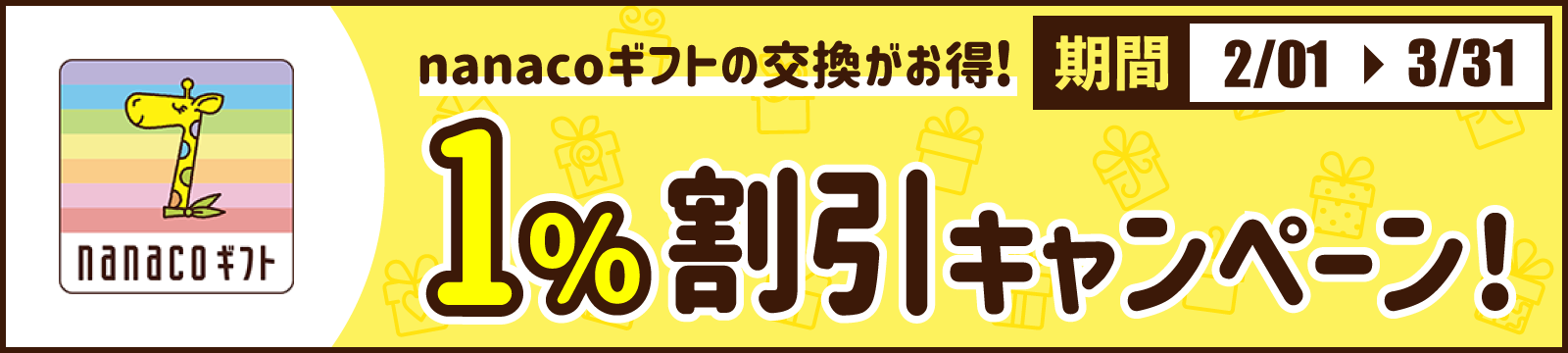
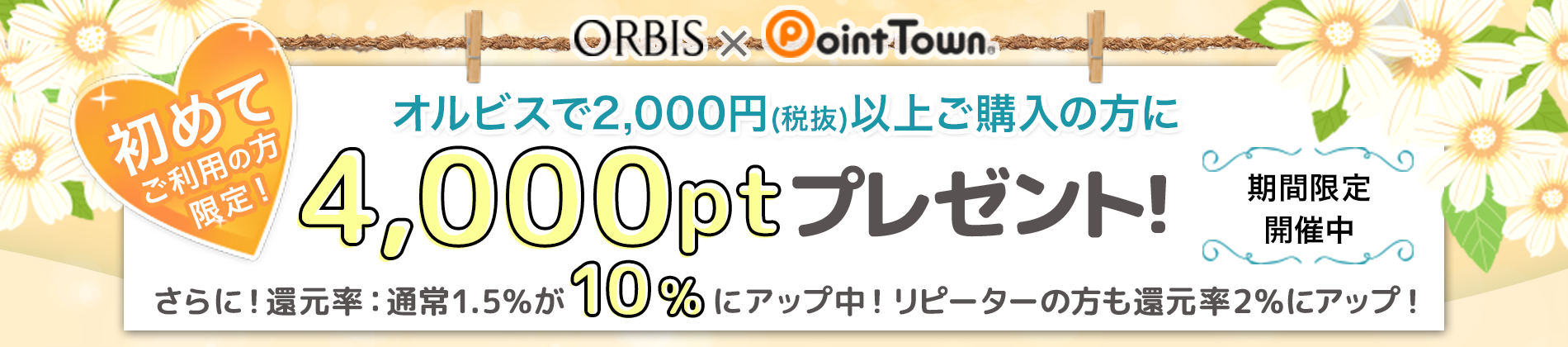

![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()

2019年3月19日(火)15:00〜4月4日(木)23:59