
グラズノフ - アレクサンドル・グラズノフ (Alexander Glazunov)
アレクサンドル・グラズノフ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アレクサーンドル・コンスタンティーノヴィチ・グラズノーフ(Алекса?ндр Константи?нович Глазуно?в ; Aleksandr Konstantinovich Glazunov, 1865年8月10日 - 1936年3月21日)はロシア帝国末期およびソビエト連邦建国期の作曲家・音楽教師・指揮者。ペテルブルク音楽院の院長を1906年から1917年にかけて務め、ペトログラード音楽院およびロシア革命後のレニングラード音楽院への改組を担った。1930年まで院長職を任されてはいたが、1928年にソ連を脱出してからというもの、二度と帰国しなかった[1]。任期中の門弟で最も有名な一人がショスタコーヴィチである。
グラズノフは、ロシア楽壇における民族主義(ペテルブルク楽派)と国際主義(モスクワ楽派)を巧みに融和させた点において重要である。グラズノフはバラキレフの国民楽派の直系であり、ボロディンの叙事詩的な壮大さに靡きながらも、その他多くの影響を吸収した。例えば、リムスキー=コルサコフの巧みな管弦楽法や、チャイコフスキーの抒情性、タネーエフの対位法の手腕などである。しかし、時として形式主義が霊感を翳めそうになったり、折衷主義が独創性の痕跡を作品中からすっかり拭い去りそうになったりするという弱点も見られる。プロコフィエフやショスタコーヴィチのような新進作曲家は、実のところグラズノフの作品は時代遅れだと看做していたが、それでもグラズノフが、変化と波瀾の時期において、依然として際立った名声と不動の影響力をもった芸術家であるということは認めていた
略歴
神童
サンクトペテルブルクの富裕な出版業者の家庭に生まれる(グラズノフの父親は、プーシキンの『エフゲニー・オネーギン』の版元であった)[3]。9歳でピアノの、13歳で作曲の学習を開始。ロシア五人組のかつての指導者バラキレフは、グラズノフ青年の才能を認め、その作品をリムスキー=コルサコフに注目させた。「バラキレフは、14歳か15歳の高校生の作品を、何気なく私のところに持ってきた。それがサーシャ・グラズノフの曲だった。あどけない手法で作曲された管弦楽曲だった。青年の才能は疑いようもなく明らかであった」とリムスキー=コルサコフは回想している[4]。バラキレフは、その後まもなく1879年12月に、グラズノフ青年をリムスキー=コルサコフに紹介した。
サンクトペテルブルクの富裕な出版業者の家庭に生まれる(グラズノフの父親は、プーシキンの『エフゲニー・オネーギン』の版元であった)[3]。9歳でピアノの、13歳で作曲の学習を開始。ロシア五人組のかつての指導者バラキレフは、グラズノフ青年の才能を認め、その作品をリムスキー=コルサコフに注目させた。「バラキレフは、14歳か15歳の高校生の作品を、何気なく私のところに持ってきた。それがサーシャ・グラズノフの曲だった。あどけない手法で作曲された管弦楽曲だった。青年の才能は疑いようもなく明らかであった」とリムスキー=コルサコフは回想している[4]。バラキレフは、その後まもなく1879年12月に、グラズノフ青年をリムスキー=コルサコフに紹介した。
リムスキー=コルサコフは、自分はグラズノフの個人教師であると考えていた[5]。「彼の音楽的な成長は、日ごとにではなく、文字通り時間ごとに進んだ[5]」とリムスキー=コルサコフは記している。二人の関係も変化した。1881年の春までに、リムスキー=コルサコフはグラズノフを門弟としてでなく、年少の同僚と看做すようになった[6]。このような発展は、リムスキー=コルサコフの側で、同年春に他界したムソルグスキーの精神的な代わりを見つけなければならないという念願から起こったのかもしれないが、同時に、グラズノフの最初の交響曲の進展を見守っていて起きたのかもしれない[6]。リムスキー=コルサコフはグラズノフの《交響曲 第1番「スラブ風」》の初演を指揮した。グラズノフが16歳のときである。なかんずくボロディンとウラディーミル・スターソフが作品と作曲者を激賞した。
ベリャーエフの庇護
イリヤ・レーピン作画によるベリャーエフ像 (1886年)褒め言葉よりも重要だったのは、グラズノフ作品の賛美者であり、中でもその一人が富裕な材木商人でアマチュア音楽家でもあったミトロファン・ベリャーエフであった。ベリャーエフはアナトーリ・リャードフによってグラズノフの音楽に引き合わされ[7]、この若者の音楽の行く手に激しい興味を掻き立てられて[8]、その興味を国民楽派の作曲家全員にも広げたのであった[7]。グラズノフは1884年にベリャーエフに西欧旅行に連れ出され、ヴァイマルで老巨匠フランツ・リストに出会い、同地で《交響曲 第1番「スラブ風」》を上演してもらっている
やはり1884年にベリャーエフは、音楽ホールとオーケストラを借り切って、グラズノフの《「スラブ風」交響曲》と最新作の管弦楽組曲を上演した[10]。リハーサルの成功に気を良くしたベリャーエフは、翌年のシーズンにグラズノフらの作品による公開演奏会を行うことを決心する[11]。この目論見は、1886年から1887年のシーズンに開会された、「ロシア交響楽演奏会」へと膨らんだ[12]。
1885年にベリャーエフは、ライプツィヒに自前の楽譜出版社を創設し、グラズノフやリャードフ、リムスキー=コルサコフ、ボロディンらの作品を自費で出版した。すると新進作曲家がベリャーエフの援助を懇願するようになった。提出された作品を選定してもらうため、ベリャーエフは、リャードフやリムスキー=コルサコフとともに出版社の顧問に就任するようグラズノフに依頼した[13]。ベリャーエフを囲んで結成された作曲家集団は、結局のところ「ベリャーエフ・サークル」として名をなすようになった
名声
グラズノフはやがて国際的な称賛を受けるようになる。それでも1890年から1891年まで創作上の行き詰まりを経験している。この期間を抜け出すと、新たに成熟期へと進み、1890年代に3つの交響曲、2つの弦楽四重奏曲、そしてバレエ音楽《ライモンダ》と《四季》を完成させた。1905年にペテルブルク音楽院の院長に選出されるまでの間グラズノフは創造力の頂点を極めた。この間の最も有名な作品に、《交響曲 第8番》と、《ヴァイオリン協奏曲》がある。この頃が国際的な名声の最高潮の時期でもあった。1907年5月17日にパリでロシア史演奏会の最終日を指揮し、オックスフォード大学とケンブリッジ大学からは名誉音楽博士に任ぜられている。作曲活動25周年の節目の年には、ペテルブルクとモスクワで、全曲自作のみの祝賀演奏会が開かれた[14]。
グラズノフはやがて国際的な称賛を受けるようになる。それでも1890年から1891年まで創作上の行き詰まりを経験している。この期間を抜け出すと、新たに成熟期へと進み、1890年代に3つの交響曲、2つの弦楽四重奏曲、そしてバレエ音楽《ライモンダ》と《四季》を完成させた。1905年にペテルブルク音楽院の院長に選出されるまでの間グラズノフは創造力の頂点を極めた。この間の最も有名な作品に、《交響曲 第8番》と、《ヴァイオリン協奏曲》がある。この頃が国際的な名声の最高潮の時期でもあった。1907年5月17日にパリでロシア史演奏会の最終日を指揮し、オックスフォード大学とケンブリッジ大学からは名誉音楽博士に任ぜられている。作曲活動25周年の節目の年には、ペテルブルクとモスクワで、全曲自作のみの祝賀演奏会が開かれた[14]。
指揮者グラズノフ
グラズノフは1888年に指揮者デビューを果たしている。その翌年には、パリ万博で自作の《交響曲 第2番》を指揮した[15]。1896年にロシア交響楽協会の指揮者に任命されてもいる。1897年には、ラフマニノフの《交響曲 第1番》の悲惨な初演を指揮した。後にラフマニノフ未亡人は、その時グラズノフは酔っているように見えたという。この申し立てを肯定することはできないものの、ショスタコーヴィチ曰く「机にアルコール1瓶を忍ばせておいて、講義の合間にちびりちびりと飲み干してしまう」ような男には、あながち無い話でもなさそうだ[16]。
グラズノフは1888年に指揮者デビューを果たしている。その翌年には、パリ万博で自作の《交響曲 第2番》を指揮した[15]。1896年にロシア交響楽協会の指揮者に任命されてもいる。1897年には、ラフマニノフの《交響曲 第1番》の悲惨な初演を指揮した。後にラフマニノフ未亡人は、その時グラズノフは酔っているように見えたという。この申し立てを肯定することはできないものの、ショスタコーヴィチ曰く「机にアルコール1瓶を忍ばせておいて、講義の合間にちびりちびりと飲み干してしまう」ような男には、あながち無い話でもなさそうだ[16]。
酔っ払っていたのであろうとなかろうと、グラズノフにはその交響曲に十分なリハーサルをつけることが出来なかったのであり、指揮法に熟達することはなかったものの、それでも指揮が大好きだった[17]。たとえ自分が指揮の才能には恵まれていないと承知していたにせよ、グラズノフは時おり自作を、特にバレエ《ライモンダ》を指揮した。時に冗談で、「私の作品を批判するのは構わないけど、私が名指揮者じゃないとか有名な音楽院の院長じゃないなんて言ったら、承知しないよ[18]」と言ったという。
第1次世界大戦とその後のロシア内戦の困難のさなかに、グラズノフは指揮者として活動を続けた。工場や会館、赤軍の駐屯地などでコンサートを指揮した。
ベートーヴェン没後百周年記念行事において、グラズノフは解説者ならびに指揮者として大役を果たした。ソ連を離れてからは、1928年にパリで自作の夜会を指揮した。これに続いてポルトガルやスペイン、フランス、イングランド、チェコスロバキア、ポーランド、オランダ、アメリカ合衆国でも指揮台に上った[19]。

グラズノフ:5つのノヴェレッテ/弦楽四重奏曲第5番(サンクトペテルブルク弦楽四重奏団)
GLAZUNOV, A.: 5 Novelettes / String Quartet No. 5 (St. Petersburg String Quartet)
このページのURL http://ml.naxos.jp/album/DE3262

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲/瞑想曲/四季(ロザンド/マレーシア・フィル/バーケルス)
GLAZUNOV: Violin Concerto / Meditation / The Seasons
このページのURL http://ml.naxos.jp/album/VXP-7907

グラズノフ:四季/バレエの情景
GLAZUNOV: Seasons (The) / Scenes de Ballet
このページのURL http://ml.naxos.jp/album/8.223136

グラズノフ:交響曲第8番/プーシキン生誕100年のカンタータ(ロシア国立響/ポリャンスキー)
GLAZUNOV: Symphony No. 8 / Cantata in Memory of Pushkin's 100th Birthday / Poeme lyrique
このページのURL http://ml.naxos.jp/album/CHAN9961
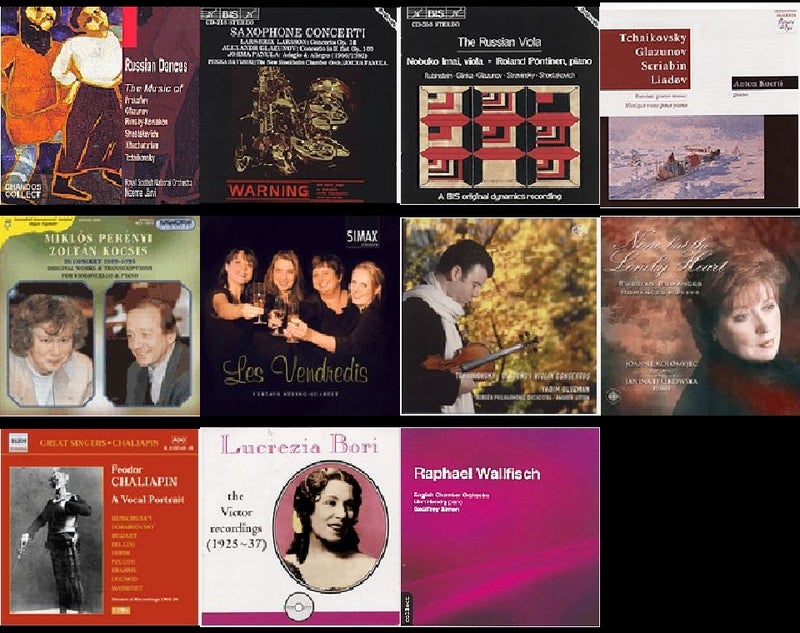
吟遊詩人の歌 Op. 71
Chant du menestrel, Op. 71
ラファエル・ウォルフィッシュ - Raphael Wallfisch (チェロ)
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 - London Philharmonic Orchestra
ブライデン・トムソン - Bryden Thomson (指揮者)
この作品のURL http://ml.naxos.jp/work/152632



