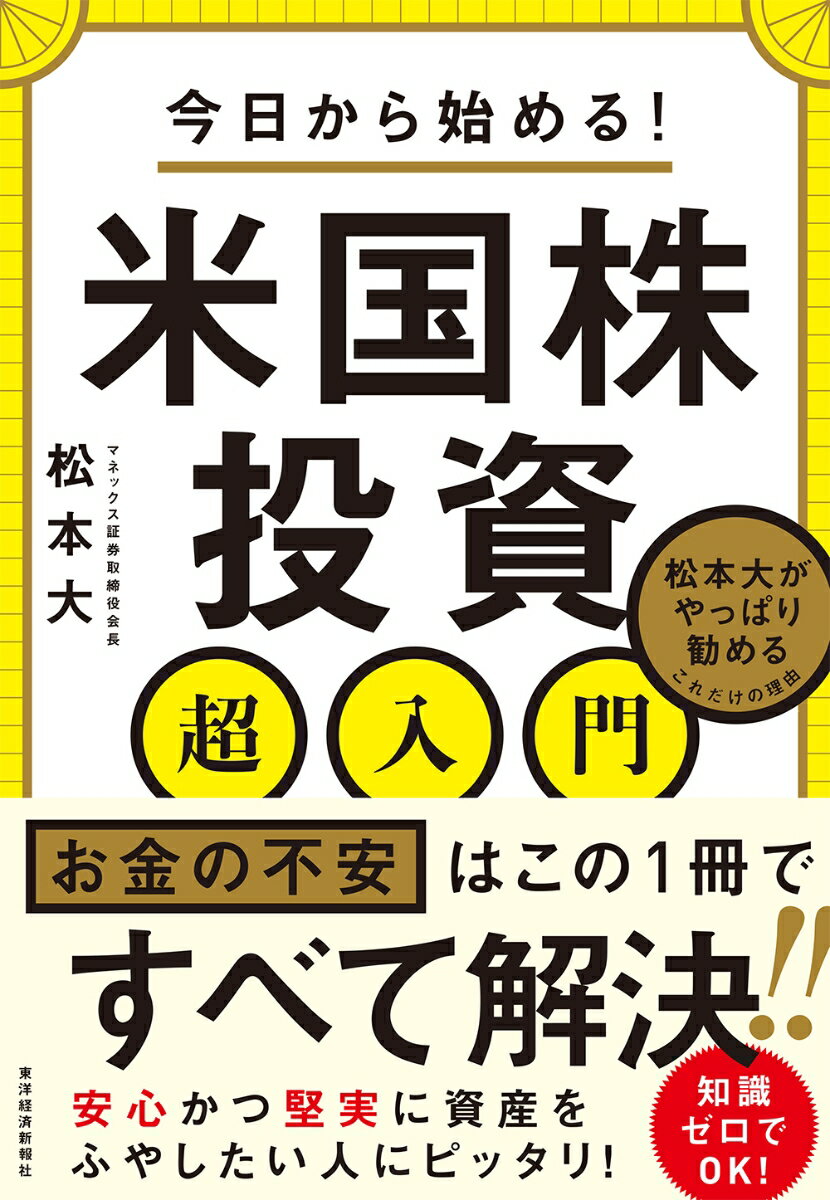ダウ平均株価の終値は前日比331・37ドル高の3万9387・76ドルでした。値上がりは7営業日連続です。
米の雇用指標が労働需給の緩みを示し、FRBが年後半に利下げに動くとの見方が広がり、買い優勢となりました。
9日発表の週間の米新規失業保険申請件数は23万1000件と、市場予想(21万4000件)を上回りました。労働市場の過熱感が薄れ、FRBが利下げに動きやすくなるとの観測を誘発しました。
米長期金利が4.4%台半ばと前日終値を下回る水準で推移し、株式の相対的な割高感が薄れました。
個別では、キャタピラー、ゴールドマン・サックスなど景気敏感株が上昇となり、シェブロンなども値を上げました。
一方、セールスフォース、IBMなどは値を下げました。また、8日に発表した四半期決算発表した英半導体設計のアーム・ホールディングスが続落となりました。それに関連してエヌビディアなども下落となりました。
ナスダック総合指数の終値は43・51ポイント高の1万6346・27でした。 S&P500の終値も26・41ポイント高の5214・08でした。
(ドル円)
ドル円は1㌦=155円台で推移しています。
介入観測に伴う先週の160円台前半から151円台後半への急落の半値戻しが156円付近ですが、その水準を試しそうな気配です。ただ、再度160円を積極的に目指そうという雰囲気はなく、来週の米インフレ指標まで一進一退となりそうです。
日銀は3月の会合で、マイナス金利政策の解除に踏み切りましたが、国債買い入れについては月間6兆円規模で継続することを決めていました。
これに対し、4月会合では「市場機能回復を志向し、減額することは選択肢だ」「どこかで削減の方向性を示すのが良い」など、国債買い入れの減額を巡り議論が本格化。日銀の国債保有量の圧縮など、量的引き締め(QT)も視野に入れるべきだとする意見もあった様です。
同会合では、声明文から「6兆円」という購入額の表記を削除し、実際の買い入れをある程度柔軟に行えるよう布石も打ちました。
日銀の植田総裁は会合後の記者会見で、円安の影響は限定的との考えを示し、市場では一段の金融正常化に慎重だと受け止められました。このため円安が加速し、円相場は一時1ドル=160円台まで下落しました。政府・日銀はその後、円買いの為替介入で対抗しました。
4月会合では、ある委員が「円安を背景に基調的な物価上昇率の上振れが続く場合には、正常化のペースが速まる可能性は十分にある」と指摘するなど急速な円安を警戒する声も多かった様です。為替の動向次第で、追加利上げや国債買い入れ減額などの正常化に向けたタイミングが前倒しされることもありそうで注意が必要です。
(原油)
WTIは前日比0.27ドル高の1バレル79.26ドルで取引を終えました。米中のエネルギー需要が拡大するとの期待が相場を支えました。一方、中東リスクへの過度の警戒が薄れる可能性が意識され、相場の上値は重い展開でした。
9日発表の中国の4月の輸入額が3カ月ぶりに増加に転じ、原油や天然ガスの輸入も増えました。米国では週間の米新規失業保険申請件数が市場予想を上回り、FRBの年後半の利下げが米景気や原油需要を支えるとの見方が強まりました。