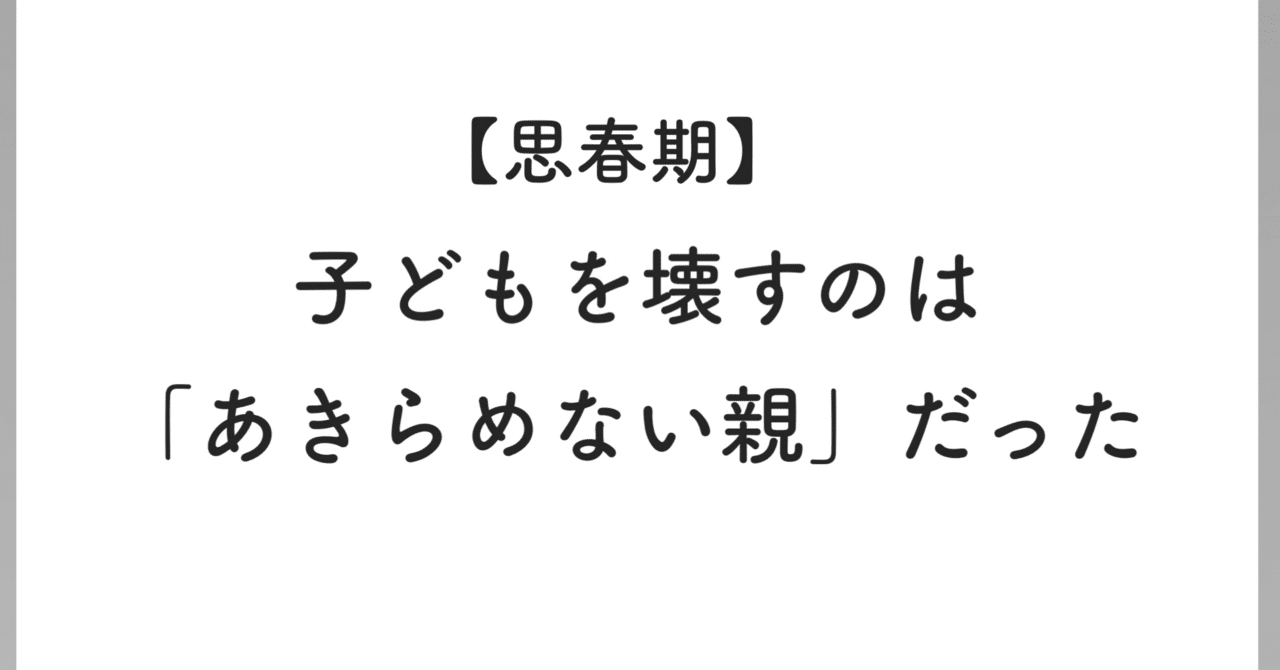【思春期】子どもを壊すのは「あきらめない親」だった──子育てに潜む“支配の愛”を手放すとき
「子どものために、最後まであきらめない」
その言葉ほど、多くの母親を苦しめてきた信念はありません。
思春期を迎えた子どもに対して、
努力を促し、助言をし、背中を押す。
けれどどれだけ手を尽くしても届かない瞬間があります。
そのとき私たちは、「まだ足りない」「もっと支えなければ」と自分を責めてしまうのです。
しかし“あきらめないこと”は本当に、愛の証なのでしょうか。
その背後には、「自分が関わり続けなければ、子どもは崩れてしまう」という深い不安と恐れが潜んでいることがあります。
母が「信じること」と「支配すること」の境界線を見失うとき、愛はいつの間にか、子どもの自立を阻む鎖へと変わります。
この記事では、“あきらめない愛”が生む誤解を解きほぐしながら、母性の本質を再定義していきます。
それは「見放すこと」ではなく、「手放す覚悟」である
親が「あきらめる」と聞くと、どこか敗北のニュアンスが漂います。
「もうこの子は無理だ」
「話しても意味がない」
そんなふうに聞こえてしまうのは、
私たちが「支配できる関係」こそが愛だと、どこかで信じてきたからではないでしょうか。
しかし思春期という時期は、「あきらめる」という言葉の意味そのものを、親に書き換えさせます。
それは子どもの人生に対して自分がコントロールを失うことを、愛として引き受けるという
静かな覚悟なのです。
「あきらめる」は、愛の成熟形
「あきらめる」という語は、元々「明らかに見る(明らむ)」という意味を持ちます。
つまり本来は「現実を直視すること」、あるいは「幻想を手放すこと」を指していました。
思春期の子育てにおいて、この語が持つ本義は実に鋭く突き刺さります。
親の中にある「理想の子ども像」。
こうあってほしい、ああするべき、こうすれば幸せになる。
そういった無意識の期待や恐れが、親子関係を締めつける鎖になるのです。
思春期は、子どもが親から離れようとするフェーズです。
これは反抗ではなく、「親の期待から自分を取り戻す」ための発達上の自然な動きです。
このとき親ができることは、
「期待」ではなく「信頼」に舵を切ることです。
「もうコントロールできない」と絶望するのではなく、
「もうコントロールする必要がない」と悟ることが、この「あきらめ」の本質なのです。
「あきらめない親」が、子どもを壊すとき
ここで逆説的な問いを置きたいと思います。
なぜ「あきらめない親」は、時に子どもを傷つけるのでしょうか。
それは「あきらめない」という言葉の裏に、
“自分の理想を最後まで押し通す”という、他者への支配欲が潜んでいることがあるからです。
✅ もっと頑張ればわかってもらえるはず
✅ 親として、最後まで戦うべきだ
✅ この子を見捨てるわけにはいかない
一見、愛に聞こえるこれらの言葉の奥には
「私の正しさを手放したくない」
「私が変わるより、子どもが変わってほしい」
という、親自身の“未完の課題”が隠れている場合があります。
つまり「あきらめないこと」が、親自身の幼さや不安の上に成り立っていることがあるのです。
このとき必要なのは、「信じて見守る」という名の放置ではありません。
そうではなく“自分の内面を見つめ直す”という意味での、親自身の自立なのです。
母が抱く「あきらめる」への誤解
多くの母親にとって、「あきらめる」は“愛をやめること”のように感じられます。
「私があきらめたら、この子は誰が支えるの?」
「見放すなんて、親失格じゃないか」
そんな罪悪感が、母の胸を締めつけます。
しかしこの“罪悪感”こそが、母の愛情の純度の証でもあるのです。
母は本能的に「つなぐ」存在です。
妊娠・出産・授乳という身体的な連続性の中で、“自分と子どもは一体”という感覚を持ちます。
だからこそ精神的な「切り離し」が必要な思春期になると、“あきらめる=切り捨てる”と誤解してしまうのです。
けれど本当の「あきらめ」とは、“見限る”ことではなく、“見届ける”ことです。
それは子どもが自分の足で立とうとする姿を、
口を出さずに、倒れてもなお立ち上がることを信じて見守る行為です。
つまり母が「あきらめる」とは、
「私の思い通りでなくても、この子の人生を信じる」という“覚悟の肯定”なのです。
「再解釈」としてのあきらめ:母の成熟への通過儀礼
あきらめとは母性の終わりではなく、母性の進化です。
それは「守る力」から「託す力」への転換。
子どもを包み込む愛から、子どもを外に送り出す愛への変化です。
心理学的に見れば、これは“母の分離不安”を乗り越えるプロセスでもあります。
子どもを失う恐れを抱えながらも、「信じて任せる」という姿勢を選ぶ。
その瞬間に母は“育てる人”から“見届ける人”へと、役割を更新するのです。
つまり「あきらめる」とは、母の自己変容の儀式であり、子どもの自立と同時に、母自身の精神的自立を意味します。
思春期の親子関係が本当に「対等」になるのは、
母が“支配”ではなく“信頼”を選んだときなのです。
「あきらめる」という美徳を、恐れずに選べるか
親として、どこまで介入すべきか。
どこからは信じて任せるべきか。
この線引きはいつもグレーで、いつも不安です。
けれどもしも「あきらめる」という行為が、
「あなたの人生を、あなたのものとして信じる」という親としての最後の贈り物だとしたらどうでしょうか。
私たちが「あきらめる」べきなのは、
子どもではなく、“親としての万能感”なのかもしれません。
「あきらめる」とは、愛のかたちを変えること
支えることから、見守ることへ。
教えることから、信じることへ。
育てることから、手放すことへ。
その変化に伴う痛みと静けさを、
どうか「敗北」ではなく「成熟」として、
引き受けてみてほしいのです。
思考の余白
ここに置く問いは、答えを導くためではなく、“母である前の自分”を静かに取り戻すための余白です。
✅ あなたが今「あきらめたくない」と感じているのは、本当に“子ども”のためでしょうか。
✅ それは“親としての自分”を守るためではないでしょうか。
✅ そしてもし「あきらめること」が、もっと深い信頼の表現だったとしたら、どう感じるでしょうか。
◎ここから先はnoteにて
母親であることに正解を求め続けてきた私たち。
「子どもを優先することが愛」
「我慢こそが母の強さ」
「子どもの幸せ=自分の幸せ」
そんな“美しい誤解”の中で、いつの間にか自分を見失っていく。
けれどその誤解は、母が未熟だから生まれたのではありません。
むしろ「愛しすぎた結果」として、無意識に形成されていった心理構造なのです。
ではなぜ私たちは“愛”の名のもとに自分を縛りつけてしまうのか。
どこで「支える」と「支配」の境界が曖昧になってしまうのか。
そして、どうすれば再び“母である前の私”として呼吸できるのか。
この先では
① 母性を「犠牲」ではなく「創造」として再定義する視点
② 支配と信頼の臨界点にある、親子の心理的境界線
③ 母の自己同一性(アイデンティティ)を回復するプロセス
について、発達心理学と家族力動の観点から深く掘り下げていきます。
母であることを“やめる”のではなく、
母である自分を“もう一度定義し直す”ために。
https://note.com/hapihapi7/n/n2629e28f0124