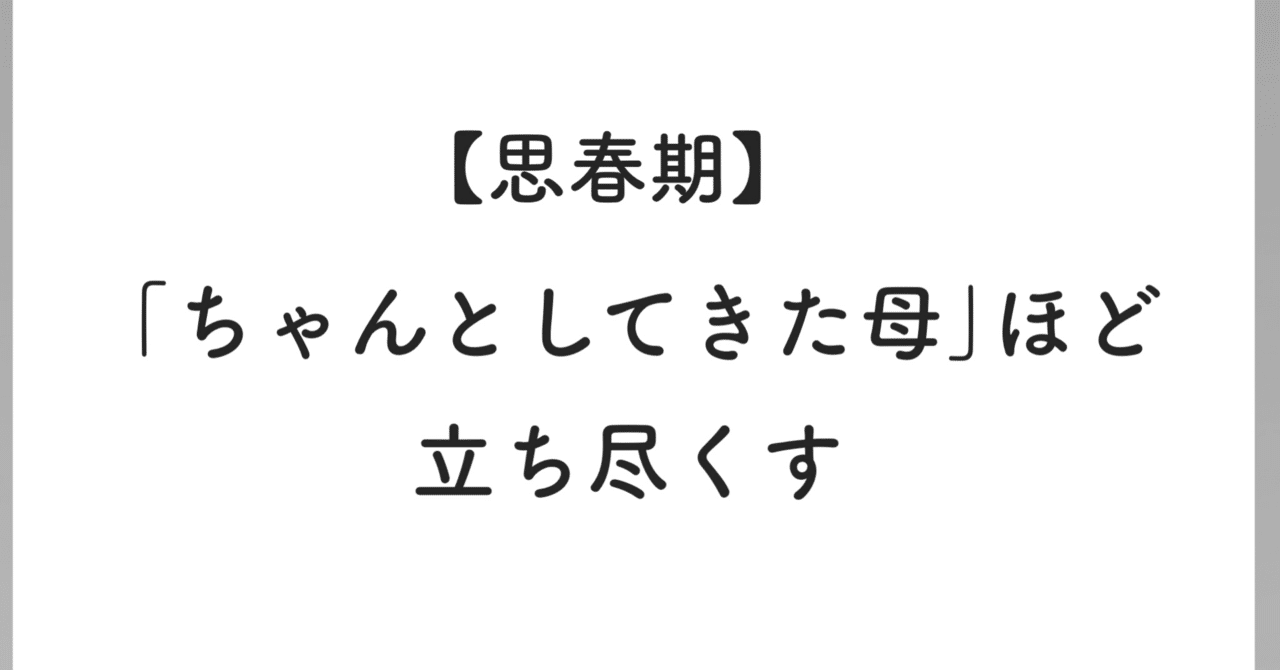⏫続きです…
9.まとめ|この苦しさが示しているもの
母は、もう次の段階に来ている
思春期の子育てで感じるこの苦しさは、
何かを間違えた結果ではありません。
むしろ、
一つの役割を生き切った人にだけ
訪れる局面です。
条件付きの世界で、空気を読み、
正しさを身につけ、関係を壊さないよう
自分を律してきた。
そのやり方で、
母は人生を守ってきました。
だから今、子どもの変化によって
その前提が揺らぐのは、自然なことです。
苦しいのは、
失敗しているからではありません。
次の段階に移行しようとしているからです。
思春期は、
子どもが親から離れる時期であると同時に、
母が「正しさに守られる側」から
「信頼で立つ側」へ移る通過儀礼でもあります。
ここを通らずに、
関係が成熟することはありません。
怒りが出る。
不安が噴き出す。
正したくなる自分に
嫌気がさす。
それらはすべて、これまでの生き方が
限界を迎えたサインです。
壊れているのではない。
更新が始まっている。
この視点に立てたとき、
母はもう「どうするべきか」を
一人で抱え込む位置にはいません。
見直すべきなのは、子どもではなく、
母が長年握ってきた
前提のほうだと分かるからです。
正しさを捨てる必要はありません。
ただ、それを振りかざさなくても
関係が成り立つ段階に来ているということ。
ここまで来た母は、もう十分にやっています。
そして、ここから先は
一人で考え続けるには少し重たい領域です。
◎この先へ進むために
ここまで、思春期の子どもを通して
母の中で起きている構造をできるだけ丁寧にほどいてきました。
けれど実際の関係は
もっと複雑で、もっと個別です。
子どものタイプによって、母の反応は変わります。
過去の体験によって、引き金の位置も違います。
この先のnote有料パートでは、
・ケース別に起こりやすい母の葛藤
・「境界」が崩れやすい場面
・感情が暴走しやすいポイントの見極め方
・正しさを使わずに関係を保つ視点
そうした部分を、さらに深く扱っていきます。
答えを与えるためではありません。
母自身が、自分の立ち位置を
見失わずにいられるために。
思春期は、親子関係の終わりではない。
条件付きでつながってきた関係から、
信頼で並び立つ関係へ移行するための時期です。
その入り口に立っている母へ。
この苦しさは、あなたがちゃんと生きてきた証です。
ここから先は、子どもへの関わり方を教える記事ではありません。
思春期という時期に、
母の「正しさ」や「信念」がなぜ揺さぶられるのか。
その揺れを、逃げずに見ていくための文章です。
読み終えたあと、
何かがすぐに解決するわけではないかもしれません。
ただ、
「これでよかったのか分からない」という問いの質が、確実に変わります。
https://note.com/hapihapi7/n/ne2f267afded1