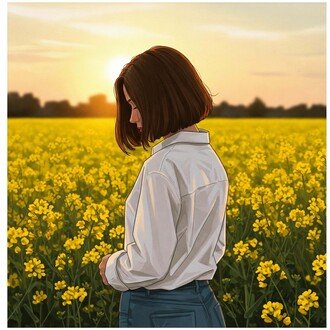母親の「私ばっかりやってる」は気のせいじゃない
母親の頭の中を占領する“見えない家事”の正体
母親に育児や家庭運営の責任が集中するのは、性格や努力の問題ではなく「社会の設計ミス」です。
本記事では、家事・育児におけるメンタルロードの実態と、母親が抱える構造的過負荷の背景を解説し、解決のための視点を提示します。
「夫婦で協力して子育てする時代」と言われるようになった現代。
しかし現実には、家庭運営の司令塔役を担うのは、依然として母親がほとんどです。
持ち物の準備、予定の把握、子どもの情緒面への配慮、夫や祖父母との調整。
表には見えないけれど絶え間なく続くその負担は、「メンタルロード(Mental Load)」と呼ばれる認知的労働です。
この記事では母親に見えない仕事が集中する背景と、それが「構造的過労」と呼ぶべき社会問題である理由を解説します。
タスクの「実行」ではなく、「全体把握と調整」の集中
近年は「夫婦で協力して子育てする時代」と言われるようになりました。
しかし現実を見ると、家庭運営における“司令塔”はほとんど母親に集中しています。
母親が担っているのは、単なる家事の分担ではなく、全体の把握・判断・調整・予測・感情管理といった広範で持続的な責任です。
たとえば
✅明日の持ち物や行事、子どもの体調と気分
✅習い事の送迎と家庭の夕食準備のタイミング
✅祖父母の関与や夫の帰宅時間との兼ね合い
✅子どもの情緒面に合わせた声かけや環境づくり
これらを「組み合わせて最適化する」作業を、母親が一手に引き受けています。
これは単なる負担ではなく「意思決定権と責任の不均衡」なのです。
メンタルロードとは何か|終わらない認知的労働
このような見えない負荷は「メンタルロード(Mental Load)」と呼ばれます。
簡単に言えば「常に何が必要かを考え続ける状態」です。
特徴は次の通りです
✅終わりがない(常に気にかけなければならない)
✅他者から見えない(何もしていないように見える)
✅失敗が許されにくい(小さな忘れが大きな問題になる)
✅引き継ぎが難しい(情報量が多く説明も負担になる)
この状態では精神的に休まる時間がなく、脳内は常に“家庭オペレーション”に占領されます。
肉体労働や時間労働とは異なる形で、母親のエネルギーをすり減らしていくのです。
なぜ母親に集中するのか|制度と文化の「設計ミス」
この状況は、母親の性格や能力の問題ではありません。
社会構造と文化的前提が「母親を主担当にするよう設計されている」からです。
① 制度が母親を“デフォルト担当”に設定している
・保育園・学校・医療機関・地域の連絡先は母親が基本
・PTAや地域行事も母親が主体で関与する前提
・「お母さん、お願いします」という社会的合図があらゆる場面に存在
② 家庭内情報が“属人化”している
母親だけが知っている情報が多く、共有されていないために責任が引き継げない。
・子どもの体質や好み、食事の注意点
・翌日の予定や保育園への伝達事項
・兄弟姉妹や夫のスケジュールとの調整
③ 「言わなきゃ動かない」仕組み
「言ってくれたらやる」というパートナーがいる場合、母親は「指示役」になります。
・頼み方を考える
・実行状況を確認する
・失敗時にフォローする
結果的に“任せること自体が仕事”になる逆説が生まれるのです。
構造的過労と人権問題としてのメンタルロード
家庭の仕事は「好きだから」「得意だから」と片づけられがちですが、実際は性別役割の固定化による強制労働です。
これを放置すると
・常に責任を背負い休めない
・感情労働が重なり慢性的なイライラや無力感が蓄積
・自分の時間を失い、社会から孤立する
・自尊感情が削られる
これは単なる「協力不足」ではありません。
母親が担わされているのは報酬のないフルタイム業務であり、無制限にオンコールで稼働する仕組みです。
人権の観点から見ても、これは搾取であり尊厳の侵害にあたります。
「母親だからできる」は免罪符にならない
母性神話に支えられた「母親は特別」「母親ならわかる」という言葉。
一見称賛のようでいて、実際には役割の固定化と自己犠牲の正当化を招きます。
・母親ならできて当然
・子どもを優先できるのが母親
・家庭の調和も感情コントロールも母親が中心
「できるから」「やってきたから」が「やるべき」に変換され、母親は逃げ道を失っていくのです。
“母親ひとりに背負わせない社会”へ
母親にタスクが集中するのは、その人の努力不足ではなく「社会の設計ミスの結果」です。
「任せられない」のではなく、任せた結果の失敗や回収がすべて母親に返ってくる設計だから、任せられないのです。
変えるべきは
・情報と責任を“構造的に”分担すること
・すべてを説明しなくても“察し合える関係”を築くこと
・「母親だから仕方ない」という前提を疑うこと
誰か一人に全体を押しつける構造は持続可能ではありません。
「母親だから頑張れる」ではなく、「母親であっても、ひとりでは無理」が当たり前になる社会へ。
そのための言語化を、ここから始めましょう。
🌱この記事を読んでくださった方へ
思春期の子育てを深掘りするメンバーシップを始めました。
月額¥500で有料記事の大半を読むことができます。
現在投稿している有料記事も随時追加していきますので、安心して続けてご利用いただけます。
ご参加お待ちしています🕊️