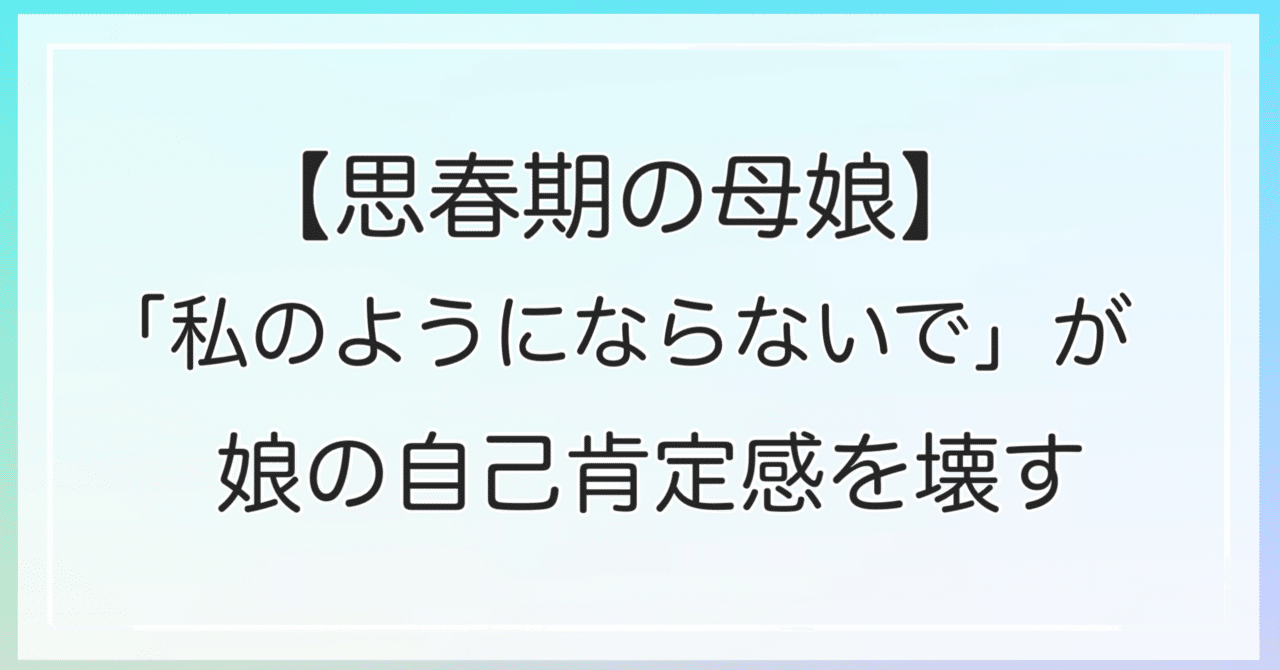子育ての落とし穴
親の「救いたい」が、なぜ子どもを苦しめるのか?
思春期の子育てで親が陥りやすい「救いたい」という心理。
その裏に潜む共依存のリスクと、子どもの自立を妨げないための見守り方を解説します。
はじめに
子育ては、親が子どもを愛し、守りたいと願う本能から始まります。
特に思春期の子どもが困難に直面したとき、親は「救ってあげなければ」という強い思いに駆られます。
しかしその「救済」の欲求こそが、親と子を「共依存」という関係に縛り付け、子どもの自立を妨げる危険な落とし穴となりうるのです。
⸻
なぜ親は子どもを「救いたい」と思うのか?
この思いの根底には、親自身の内面に潜む複雑な心理があります。
✅自己肯定感の維持
子どもの成功を自分の成功と同一視し、子どもの問題を解決することで「私は良い親だ」と感じたい。
✅未完了な課題の投影
親が過去に成し遂げられなかったことを子どもに重ね、子どもを救うことで間接的に自分の心を癒そうとする。
✅コントロール欲求
子どもの問題を先回りして解決することで「状況を掌握している」という安心感を得ようとする。
一見すると愛情のように見える「救いたい」という感情は、実は親自身の「依存」の表れでもあるのです。
⸻
思春期で「救い」から離脱させるべき理由
思春期は、子どもが親から精神的に自立し、自分のアイデンティティを確立する「第二の誕生」の時期です。
この時期に親が過度に介入し続けると、子どもは次のような悪循環に陥ります。
✅自己効力感の欠如
自分で解決する機会を奪われ「自分にはできない」と思いやすくなる。
✅自己決定能力の未発達
親の指示に慣れ、自分で考え選択し責任を持つ力が育たない。
✅健全な自己同一性の形成不全
親の期待に応えることが目的となり、「本当の自分」を見失う。
結果として、親と子は互いを必要とする「永遠の共依存」に陥る危険があります。
⸻
親の期待が「裏切り」になる理由
さらに複雑なのが、親の「過度な期待」です。
親が子どもに「こうなってほしい」と願うこと自体は自然ですが、その期待が現実と食い違うと、親は無意識に失望します。
この失望は、子どもにとって
「ありのままの自分では愛されない」
という強烈なメッセージとなります。
子どもは親を悲しませまいと自分を犠牲にしますが、もし親の理想から外れた道を選んだとき、親は「裏切られた」と感じ、子どもは罪悪感に苛まれるのです。
これは、親と子の間で「期待の分離」ができていないために起こる深刻なすれ違いです。
⸻
「信じて見守る」ための心得
思春期の子どもを真に自立させるには、親は「救う」ことから卒業し、「信じて見守る」という新しい愛情の形を学ぶ必要があります。
✅課題の分離
子どもの問題は子ども自身の課題。
親は解決策を与えるのではなく「伴走者」として見守る。
✅あるがままの受容
子どもの失敗や選択を含めて「そのまま」を受け入れる。
結果ではなくプロセスに目を向ける。
✅期待の自覚と手放し
「これは子どものためではなく私の期待だ」と自覚し、手放す努力をする。
✅「見守る」の再定義
困ったときにすぐに手を差し伸べるのではなく、「いつでも頼っていいよ」という安心感を示しつつ、自分で解決できる力を信じて待つ。
⸻
おわりに
思春期は、子どもが「親に救われる存在」から「自分の力で立つ存在」へ移行する大切な時期です。
その過程で親が学ぶべきは、「救うこと」から「信じて見守ること」への転換。
この離脱こそが、子どもの真の自立と、親自身の精神的な成長につながります。
子育ての「悩み」は、表面に見える子どもの態度や出来事だけではありません。
その奥には、心理や家族関係に根ざした“深い構造”があります。
私の記事では、子育てや思春期の親子関係をテーマに、「なぜそう感じるのか?」という視点を軸に、心理学・発達論・家族力動の知見から深く掘り下げて解説しています。
読むたびに、親としての視野が広がり、心が少し軽くなる文章をお届けします。