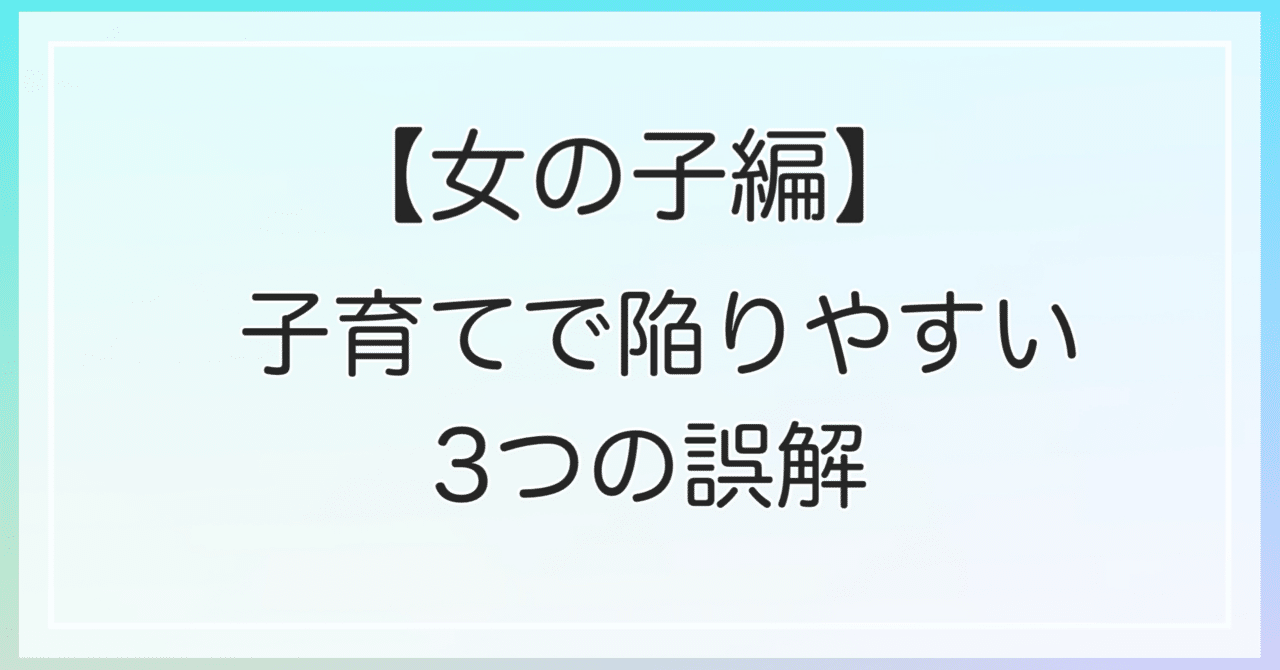「手放す=正解」の錯覚
思春期の自立を誤る親の盲点
手放すは手段にすぎない
「手放す」というのは、目的そのものではありません。
思春期の子どもが自立するということは、ただ距離を置くだけでは成り立ちません。
子どもが安心できる関係を保ちつつ距離を変えることが大切です。
多くの母親は「早く手を離すのが正しい」と考えがちですが、その裏には「もう育て終えた」と感じたい気持ちや、子どもに頼られるのが負担に感じてしまう気持ちが隠れています。
子どもがまだ戻る方法をはっきりと確認できていないのに距離を置くと、信頼関係が揺らいでしまいます。
自立の本当の意味を見つめる
思春期は「自分は誰なのか」を探し続ける時期です。
失敗を繰り返しながら、自分でできることを少しずつ増やしていきます。
その過程では、「困ったときに帰れる場所」があって初めて安心して挑戦できます。
人は自分が仲間の一員だと感じてこそ、自分の価値を実感できるものです。
母親が「もう大丈夫」と思い距離を置きたくなるのは、二つの理由が考えられます。
一つは「これで育て終えた」と自分に認めたい気持ち。
もう一つは、頼られて大変な思いをするのを避けたい気持ちです。
どちらも無意識に働きやすく、子どもの準備よりも自分の感情で決めてしまいがちです。
また、男の子と女の子では自立の感じ方に違いがあります。
男の子は外で挑戦しながら自分を試し、困ったときに「戻っていい場所があるかどうか」を無意識に確かめます。
女の子は人との関わりや感情を通して自分を知るため、お母さんとの距離が急に離れると「見捨てられた」と感じやすくなります。
どちらも「手放すタイミング」と「戻れる約束」が合っていないと、すれ違いが生まれます。
自立は関係性の再設計である
この問題は家庭だけでなく、会社の仕事の任せ方と似ています。
良いリーダーは、仕事を任せるときに「困ったら戻ってこられる仕組み」を作ります。
家庭でも同じで、子どもが安心して自分の力を試せるように、親は伴走しながら少しずつ距離を取ることが大切です。
具体的にはこうしたことが効果的です。
1. なぜ手放したいのかを振り返る
自分の気持ちが、子どもの準備に合っているか確かめます。
2. 戻るための約束を決める
困ったときにどうやって助けを求めるかを親子で話し合っておきます。
3. 少しずつ任せる範囲を広げる
いきなり全部を任せるのではなく、小さな挑戦から経験させます。
また、「早く自立させることが良い」という世間の価値観に振り回されず、それぞれの家族に合ったペースを大切にすることも忘れてはいけません。
考えるための問いを残す
以下の問いをじっくり考えてみてください。
すぐに答えを出す必要はありません。
問い続けることで、よりよい距離感が見えてきます。
✅「手放す」と思ったとき、それは本当に子どもの準備に基づいていますか?
✅その決断は、自分の安心や負担を減らしたい気持ちからではありませんか?
✅子どもが困ったときに戻れる約束を、しっかり共有できていますか?
✅距離を置くことで、子どもがどんな気持ちを持つか想像できますか?
✅10年後、親子の関係はどんな姿でありたいか。そのために今の距離感は適切ですか?
この問いは正解を示すものではなく、関係をよりよくするための小さな灯りです。
問いを抱えながら、日々の暮らしのなかで少しずつ確かめていくことが、真の自立への道しるべになります。
子育ての「悩み」は、表面に見える子どもの態度や出来事だけではありません。
その奥には、心理や家族関係に根ざした“深い構造”があります。
私の記事では、子育てや思春期の親子関係をテーマに、「なぜそう感じるのか?」という視点を軸に、心理学・発達論・家族力動の知見から深く掘り下げて解説しています。
読むたびに、親としての視野が広がり、心が少し軽くなる文章をお届けします。