さ~て、先日、ある資料を読んでいましたら、久し振りに岩手県盛岡市の『石割櫻』の事を目にしました。
小職の復習の意も込めて、今日は『石割櫻』に関して、少し調べて見ました。
以下、
に掲載されていた内容を転載させて頂きます。
尚、主旨が変わらない程度で、小職が書き換えれいます。
石割桜の守り人 藤村益治郎
石割桜の守り人 藤村益治郎
岩手の先人こぼれ話
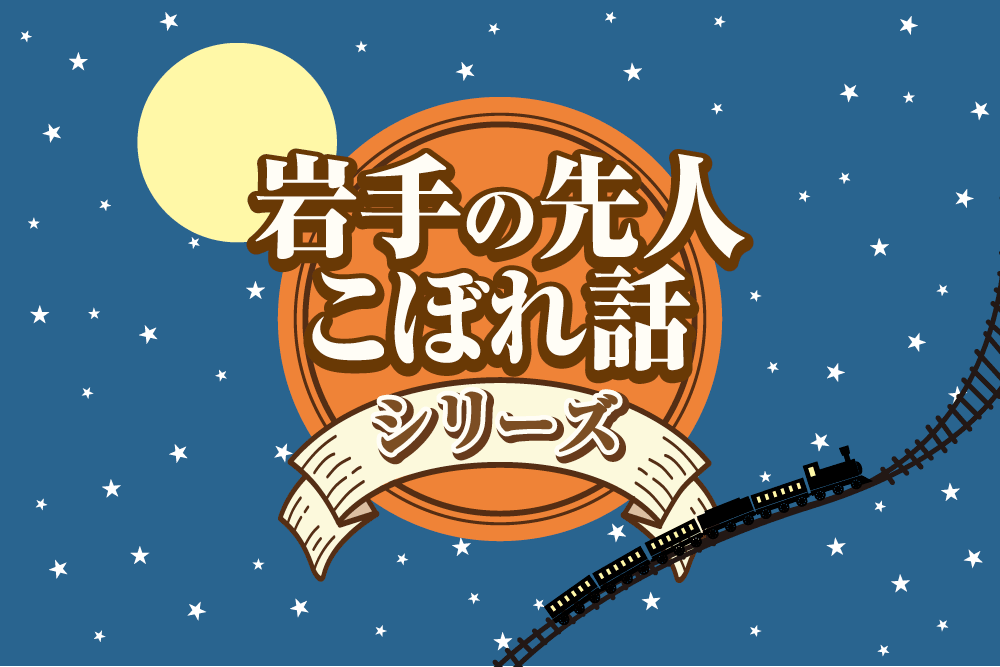
宮沢賢治学会 佐藤竜一・前副代表理事
毎年春美しい花を咲かせる盛岡地方裁判所の石割桜は、大正12年(1923年)、岩手県で初めて天然記念物に指定されました。全国に知られている石割桜ですが・・・火事にあった事を知る人は多く無いと思います。
昭和7年(1932年)9月2日、花屋町(現・本町)に住み父親(藤村治太郎)の下で庭師修行をしていた藤村益治郎(ふじむらますじろう)は、裁判所が火事だと聞き、急いで現場に駆け付けました。
すると半纏(はんてん)で必死に成って火の粉を消している父親の姿が目に入りました。思いは同じだったのです。
石割桜の消火に当たった二人の姿は岩手日報で大きく取り上げられ、存命が危ぶまれた石割桜は、父子が精魂(せいこん)込めて世話をした結果、一命を取り留めました。
それが縁で、益治郎は石割桜を守るのが自分の一生の仕事と思う様に成り、無償で世話をする様に成りました。
その仕事は子孫にも受け継がれています。
冬に成ると造園会社の豊香園(ほうこうえん)が冬囲いを行い、3月下旬にはその囲いが解かれます。
80年以上に渡るそうした作業のお蔭で、石割桜は生き続けているのです。

冬囲いをした石割桜
と言う事でした。藤村父子に感謝ですね。
そして、今日は、もうひとり人物に登場もらいます。
これも、またまた、先日、ある資料を読んでいましたら『三木勘兵衛』と言う人物に出会ったのです。
興味を持ちましたので、少し調べて見ました。
以下、デジタル版 日本人名大辞典+Plusに記載されていた内容を転載させて頂きます。
尚、主旨が変わらない程度で、小職が書き換えています。
播磨国則直(のりなお)村(現・兵庫県姫路市)の人。天保13年(1842年)から大津茂川の河口を干拓し、伊予国(現・愛媛県)、阿波国(現・徳島県)から無職の人々を集め、衣食住・牛馬を支給して開墾させた。
