さ~て、実際に見た事は無いモノの、どの様なモノかは知っている『木場の角乗』。
この『木場の角乗』が、江東区登録無形民俗文化財(民俗芸能)である事を、先日、はじめて知りました。
以下、江東区の公式ホームページに掲載されていた内容を転載させて頂きます。
尚、主旨が変わらない程度で、小職が書き換えています。
木場の角乗(きばのかくのり)
江東区登録無形民俗文化財(民俗芸能)/東京都指定無形民俗文化財(民俗芸能)
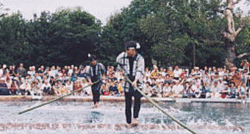
木場の角乗(きばのかくのり)は、江戸時代に木場の筏師(川並)が、水辺に浮かべた材木を、鳶口ひとつで乗りこなして筏に組む仕事の余技から発生しました。これに数々の技術が加わり、芸能として発達しました。
角乗に用いられる材木は、角材を使用するため、丸太乗りより技術を必要とします。
角乗の演技に合わせて、葛西囃子(かさいばやし)が速いテンポで、演奏されます。
(演目)
地乗り、相乗り、唐傘乗り、扇子乗り、手離し乗り、駒下駄乗り、足駄乗り、川蝉乗り、一本乗り、梯子乗り、三宝乗り、戻り駕籠乗り
と言う事でした。一度、見て見たいですね。
そして、先日、ふと思った事です。
〇〇ドクトリン(doctrine)と聞きますよね。
日本語での表現は?と思った次第です。
そこで、改めて調べて見ました。その結果『政治、外交、軍事などにおける基本原則』とありました。
正にその通りですね。
ところで、先日、新聞を読んでいました『鎌数』姓の方が登場。
由来に興味を持ちましたので、少し調べて見ました。
以下、『日本姓氏語源辞典』に掲載されていた内容を転載させて頂きます。
尚、主旨が変わらない程度で、小職が書き換えています。
福井県鯖江市戸口町にある浄土真宗の乗誓寺の僧侶による明治新姓。同寺の山号の鎌数山から、とありました。
では、本日の小職の予定です。
今日は、多くの時間、NPO法人事案(収益法人事案を含む)に伍します。
ただ、朝夕は、社会福祉法人に参ります。