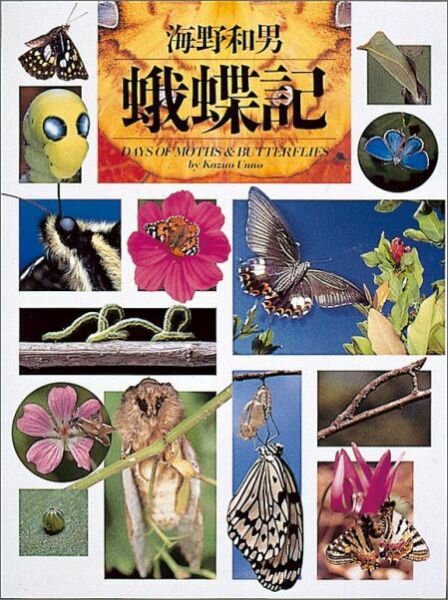先日、環境事業協会が主催する「親子向け講演会」に参加してきました。箕面昆虫館に掲示されていたポスターを見たのがきっかけです。昆虫館の先生方が登壇され、絶滅危惧種にまつわる興味深いお話をしてくださいました。
お話をされる先生も、会場の子どもたちも、昆虫好きの“むしとも”という感じで、なんとなく会場全体に一体感があるような空気が漂っていました。
講演の内容は、
-
ツシマウラボシシジミの生息域外保全の取り組み
-
箕面からいなくなってしまったギフチョウのお話
-
大阪に昔いたが今は見られなくなった昆虫の話
-
昆虫化石のお話
など、普段なかなか聞くことができない話ばかりで、内容もとても充実していました。子どもには少し難しい言葉もあったようですが(特に化石の部分)、写真をふんだんに使ったスライドを交えての説明だったので、とてもわかりやすかったです。
その中でも、私が特に惹かれたのはギフチョウについてのお話です。実物を見たことがなく、以前から少し気になっていたものの、どこに行けば見られるのかも分からずにいました。岐阜県で保護活動が行われているというニュースを見た記憶があるくらい。
でも調べてみると、実は宝塚の自然の家で飼育されていて、この時期には生体を見ることができるイベントがあるとのこと。早速行ってみることにしました!
宝塚と聞くと都会のイメージがありましたが、目的地へ向かうにつれてどんどん山の中へ入っていく道のりに、少し驚きました。
春の女神・ギフチョウの魅力
ギフチョウは、アゲハチョウ科に属する日本固有のチョウで、春先に現れることから「春の女神」とも呼ばれているそうです。しかし、環境の変化などの影響で生息地が減少し、各地で個体数が少なくなってきているといわれています。かつては箕面にも生息していたそうですが、今では見られなくなってしまったとのこと。
宝塚自然の家のイベントで初めて見たギフチョウは、縦じま模様の羽や、ふわふわとした体毛が印象的で、とても愛らしい姿をしていました。飛ぶのが少し苦手なのか、ゆったりと優雅に舞う様子が心に残りました。
ギフチョウ観察イベント
宝塚自然の家では、長年ギフチョウの保全活動に取り組んできた方々が、ギフチョウの生態や飼育方法について紹介してくださいました。私が参加した日には、運よく羽化したばかりのギフチョウを観察することができました。
図鑑やテレビ番組で見るのとはまったく違い、生きた昆虫を間近で見ると、“自然とのつながり”をリアルに実感できます。絶滅危惧種について学んだあとに、保全活動の具体的な取り組みや成果を目の当たりにすると、話がぐっと身近に感じられました。
ふだんは蝶を捕まえるのが大好きな子どもですが、今回は「貴重な蝶」であることをしっかり理解して、触れたりせずにじっと観察していました。ただ捕まえるだけが楽しいわけではないということを、少しずつ学んでいってくれたら嬉しいなと思います。
身近な自然に目を向けてみよう
このようなイベントに参加してみると、保全活動は専門家や団体だけでなく、私たち一人ひとりの関心や行動も大切なのだと感じます。絶滅危惧種の現状を知ることは、身近な昆虫や自然環境への関心を高めるきっかけにもなりますよね。
「ちょっと調べてみる」「イベントに参加してみる」「SNSで共有してみる」といった小さなアクションでも、継続していくことが大切だと思いました。