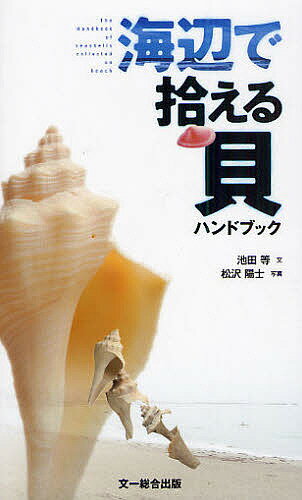こんにちは。
大阪市立自然史博物館で開催中の特別展「貝に沼る —日本の貝類学研究300年史—」を見に行ってきました。
「貝に沼る」というタイトルを聞いたとき、その意味がすぐにはわからず、「貝が沼にいる?」などと考えてしまいましたが、実際に展示を見て納得。
江戸時代から現代に至る日本の貝類学の歴史をたどる内容で、貝に魅了された研究者たちの情熱が伝わってくる展示でした。その研究の深さや歴史を知るにつれ、彼らがまさに“貝沼”にどっぷりはまってきたことが実感できました。
私が特に心惹かれた「貝に沼る」展の見どころ
江戸時代の貝類標本が圧巻!
展示室に入ってすぐ目を引くのが、今回の展示の目玉である木村蒹葭堂(きむら けんかどう)の貝類標本です。貝が美しく並べられた木箱はまるで宝石箱のようで、その繊細な作りに驚きました。「江戸時代にこんなに精巧な標本を作っていたなんて…!」と、思わず感心してしまいました。
彩色豊かな図鑑
貝類を扱った図鑑もとても印象的でした。標本も素晴らしいのですが、特にカラーで描かれた貝の美しさには目を奪われました。眺めているだけでも楽しいですね。
日本の領土拡大と貝類学
日本が台湾や南洋に領土を持っていた時代に採取された貝の標本や、統治領での貝類学の発展についての展示もありました。
そのなかで、特大のシャコガイの大きさにはびっくりしましたが、同時に、一緒に見ていた子供が「赤ちゃんがお昼寝できそう」と言っていたのが印象的でした。確かに、そのサイズ感はまるでベビーコットのようです。
(私は昔、シャコガイに足を挟まれて溺れる人の絵を見たことがあって、怖い貝だという印象を持っていたのですが、どうやらシャコガイに捕まるというのは非科学的な話らしいです)
大阪湾にこんなに貝が!?
大阪湾で採取された貝の標本がずらりと並び、その種類の豊富さに驚かされました。水質汚染の影響で生物が少ないイメージを持っていましたが、大阪湾の生態系の豊かさを知ることができました。
産業と貝—真珠・牡蠣の養殖も
真珠や牡蠣産業の歴史や養殖技術に関する展示もあり、特に御木本幸吉の真珠標本を間近で見られたのは貴重な体験でした。貝が経済や文化において重要な役割を果たしてきたことを実感できるコーナーでした。
ミヤイリガイと日本住血吸虫症の撲滅運動
日本住血吸虫症という恐ろしい寄生虫の中間宿主であるミヤイリガイの撲滅作戦について紹介され、当時の啓発ポスターや資料が掲示されていました。
「貝=のどかで美しいもの」というイメージが大きく覆される内容でした。
興味をひかれて、Wikipediaも見てみました。
大森貝塚と学芸員のユニークなコメント
縄文時代の遺跡「大森貝塚」から出土した貝の展示があり、当時の人々の食生活を垣間見ることができました。さらに、学芸員の先生の「おいしい」「固い」といった率直なコメントが添えられていたのが印象的で、思わずクスッとしてしまいました。
普段は食べる機会のない貝もたくさん含まれており、私も「どんな味がするのだろう?」と興味が湧きました。
貝の奥深さに魅了された!
貝の展示は主に「貝殻」が中心なので、最初は地味に感じるかもしれません。しかし、展示を通じて歴史や人との関わり、産業との結びつきを知ることで、貝の持つ奥深い魅力を実感しました。
「貝に沼る」展は5月6日まで開催中。研究者たちの熱意と探求心が随所にあふれ、思わず引き込まれる展示内容です。興味のある方は、ぜひ足を運んでみてください!
開催概要
- 会期:2025年2月22日(土)~5月6日(火・振替休日)
- 開館時間:
- 2月22日~28日:9:30~16:30(入館は16:00まで)
- 3月1日~5月6日:9:30~17:00(入館は16:30まで)
- 休館日:月曜日(ただし、月曜日が休日の場合はその翌平日)
- 観覧料:大人500円、高校生・大学生300円(中学生以下無料)
- 会場:大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール(長居公園内)
- URL:https://omnh.jp/tokuten/2025shells/