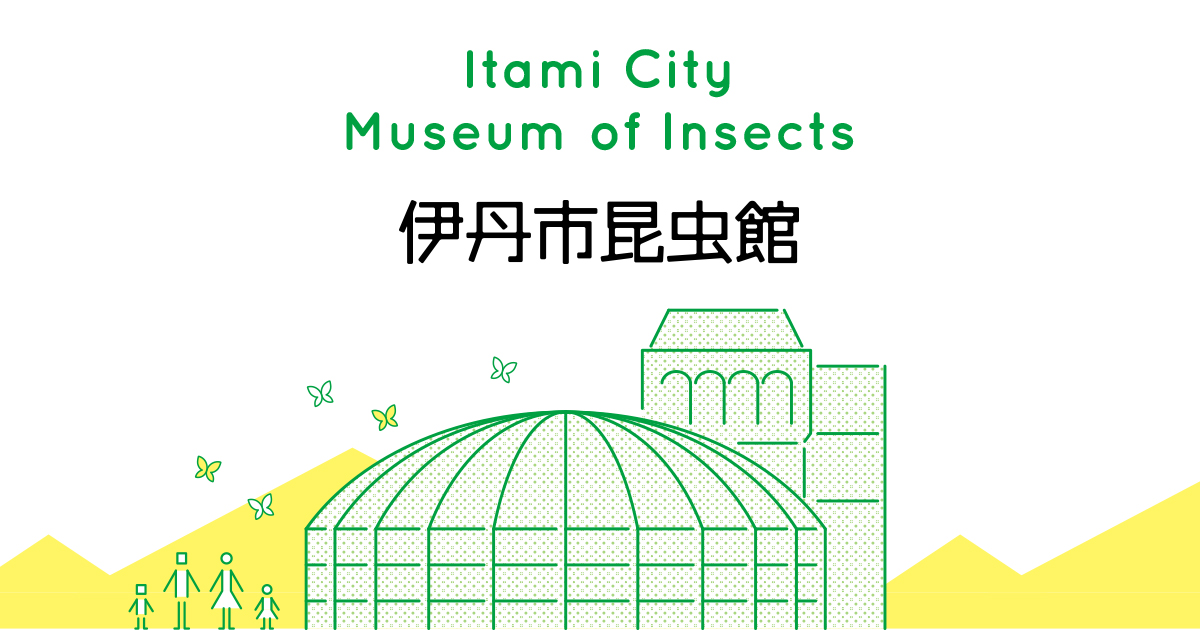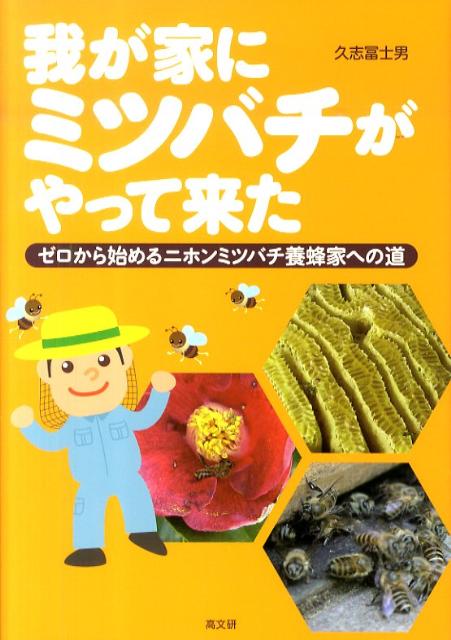先日、伊丹昆虫館で開催されたミツバチ観察会に参加してきました。
身近な存在として、ミツバチのことはある程度知っていたつもりでしたが、実際に見て・聞いて・体験すると、より理解が深まった気がします。 当日は屋外での観察もあり、少し暑さは感じたものの、それ以上に得るものが多い内容でした。
ハチの分類など
冒頭は先生のミニ講義からスタート。
ハチには草食と肉食の種類がいて、発達段階によって食性が異なるものもいるとのこと。
そういわれてみれば、一口にハチといっても、姿はいろいろですね。
江戸時代の本には「無能黒蜂」という言葉があるそうで、これは働かないオスのミツバチのこと。 観察対象としての歴史の長さに驚きました。
このほか、ハチの巣が持つ六角形のハニカム構造は軽くて強度が高く、建築や工業製品の設計にも応用されていることが紹介されていました。
熱殺蜂球とニホンミツバチの特性
スズメバチに対するニホンミツバチの防衛行動「熱殺蜂球(ねっさつほうきゅう)」についても説明がありました。
これは、ミツバチがスズメバチを取り囲んで体温を上げ、加熱して倒すというものです。
ただし、これはニホンミツバチにしか見られない行動で、セイヨウミツバチには備わっていないとのこと。
養蜂に用いられセイヨウミツバチがスズメバチの被害を受けやすい理由も、ここにあるようです。
ミツバチの巣の観察体験
続いて、実際の巣の観察体験。
防護服を着用し、顔部分がメッシュになったものを身につけたうえで、巣箱を間近に見せてもらいました。
巣板には多数の働き蜂が活動していて、女王蜂や幼虫の姿も確認できました。普段は近づくのにためらいがある存在ですが、丁寧な解説とともに、子どもでも観察しやすく、落ち着いて体験できるよう配慮されていました。
はちみつ採集と味見体験
体験の後半は、はちみつの採集と味見。
専用の遠心分離機で巣板を回転させ、蜜を取り出す作業もさせてもらいました。
取り出したばかりのはちみつは、とても香りがよく濃厚な味わい。
「スプーン1杯分の蜜を得るには、ミツバチが1000回ほど花と巣を往復する」と聞いてから味わうと、その一滴の重みが変わってきます。
ミツバチを飼うことについて
実は以前から「将来、趣味でミツバチを飼ってみたい」と考えていたのですが、今回の体験でそれが決して簡単ではないことも実感しました。
巣箱を設置すれば終わり、というわけにはいかず、健康管理や外敵対策など、手間も知識も必要です。
養蜂にはそれなりの責任と準備が求められるのだと改めて感じました。生き物を飼うというのは、やはり甘くないですね。
学習室で人気のミツバチ観察
今回の観察イベントでは屋上の巣箱を見せてもらいましたが、伊丹昆虫館の2階にある学習室にもミツバチの巣の常設観察コーナーがあり、透明な観察ケース越しに、働きバチたちが巣を出入りする様子を間近に見ることができます。
夏には、後ろ脚に花粉団子をつけたミツバチが次々と戻ってくる姿が印象的ですが、冬に訪れたときは、ミツバチたちはほとんど巣の中でじっとしていました。一年を通じて異なる活動の様子が観察できるので、何度訪れても楽しめる展示だと思います。
今回の観察会は、総じて、子どもと一緒に学べる非常に良い機会でした。私自身、子どものころにミツバチに刺された経験があり、少しだけ心配な気持ちもあったのですが、今回の観察を通して改めてその生態の面白さや見た目の愛らしさに気づかされました。