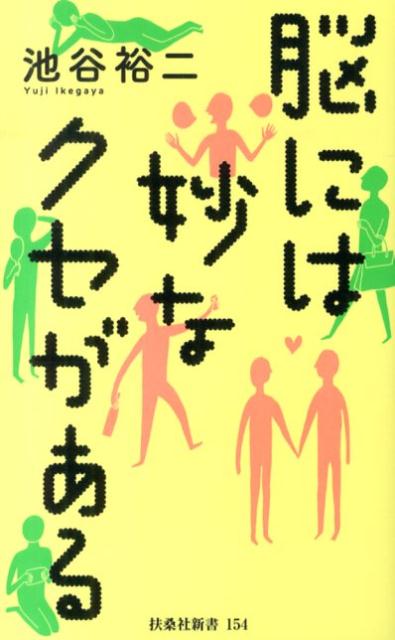こちらのブログ記事に
ちょこちょこと
書かせて頂いてきました
「脳には妙なクセがある」という本を
読み終えました
400ページ近くある
文庫本でしたが
章が細かく分かれていて
気になるところから読めますし
オモシロイと思う章は
沢山ありました
ブログ記事で
取り上げたのは
ごく一部ですが
他にも色々
ありました
★「もったいない」と思う気持ち
「痛そうな写真」を見て
「痛い~」と思うのと同じように
「物」を擬人化し
その「痛み」を
脳に投影する精神活動
つまり
「物に向けられた同情」が
「もったいない」の源で
日本人独特の感性が反映された
単語なのだそうです
(世界には「もったいない」という
意味をもつ単語は少ないらしい)
(p.66~67)
★幸福感は年齢によって変化する
どうやら
20歳以前までは高い幸福感
20歳を過ぎると一気に落ち込み
40代~50代が最低迷期(←いまここやん・・・)
これをすぎると
調査対象の最高齢
85歳までは徐々に
幸福感は増幅するらしい
(p.224)
★「自己認識した自分」と
「他者からみた自分」
仕事をした「つもり」になっている自分
けれども
実際はやれていない、だとか
自己評価に関する勘違いというのは
誰にでもある
人間は決して
自分のことを
自分では知り得ないつくりに
なっているのだと
(・・・まぁ確かに、自分の顔でさえ
鏡を使って初めてわかるんやしなぁ)
だから
無駄にもがかずに
素直に受け入れようという記述
(p.322)
★「幽体離脱」
脳のある部分を刺激すると
ベッドに寝ている自分の姿が
見えるのだという
とはいえ日常でも
例えばサッカー選手は
プレイ中に上空から
フィールドが見え
有効なパスのコースが
わかるのだという
こうした「俯瞰力」で
客観的に
自分の振る舞いを顧みる「反省」も
自己を離れて
他者の視点で自分を眺める能力があるから
私達は社会的に
成長出来るのだと
(p.354~355)
★身も心も痛むのは・・・
身体が痛い、と思うのと
心が傷ついた、と思うのとで
手足などの
身体が痛い時に活動するのと
同じ脳の部位が
心が痛いときにも活動したのだという
(p.368)
この本を読んでいると
人という生き物は
環境や習慣に
かなり影響されているのだなぁと
思いました
ここに書いてあること
全~部を理解することは
到底出来ないんだろうけど
その
妙なクセがあるという「脳」は
睡眠など
自分が本気で欲しているものは
教えてくれているのかも知れない
自分の身体や心(脳)が
求めるものに
「反応」しながら
その「反応」を促す元になる
習慣や環境を整えることは
心地よく生きる
ヒントになるのかもなぁと
思ったのでした