高専では電気科は強制的に取らされる資格ですね(笑)
『第二種電気工事士』について、自分の取得時の過程や体験談を記していきます。
そもそも電気工事士って何??
ビルや商店、一般住宅などの電気設備の安全を守るため、一般の人は電気工事を行ってはいけないんですよね。(危険ですので)ですが、電気工事士の資格を持っている場合は国から技術者として認められていることになりますね。よって電気工事士は電気工事してOKとなります。
第二種電気工事士になると何ができるか
資格を持っていれば、法律上
- 受電電圧が600ボルト以下であること
- 発電設備を設置する場合は合計で50kwを超えないこと
これらの条件を満たしていれば電気工事をしてOKとなっているんですね。具体例を挙げるなら屋内配線とかブレーカーの整備ですね。
つまりは「自分の住む家の電気配線の工事や導通、修理を業者に頼むことなく自分でできてしまう」んです。これってすごいことですよね!お金の節約にもなりますし、それに何よりかっこいいです。
試験について
受験料は9300円になります。(高いですね( ;∀;))
試験は年に2回 上期と下期に分かれています!ここで注意しなければならないのは1年のうち上期と下期どちらかしか受験できないんですよね。
また、試験自体も筆記試験と技能試験の二つに分かれます。これからそれらについて紹介していきます。
筆記試験の概要と対策について
試験問題は、一般問題(電気回路の計算問題や規格、法律など)、配線図問題の二つに大別されますね。計50問で試験時間は2時間、30問正答で合格です。つまりは60点以上取れればOK ってことですから楽勝ですね(笑)
しかも試験問題は全てマークシートの4択問題なので適当に書いても当たることもあります。
運任せはよくない。うん。
試験対策としては電気回路の計算問題では複数の公式を組み合わせて解く問題が多いのでしっかりと勉強しておく必要があります。
また、配線図の問題では、慣れないうちは単線図を複線図に直す過程に苦労しますので
参考書の購入をお勧めします。
 | 第二種電気工事士筆記試験模範解答集 平成28年版 1,296円 Amazon |
ちなみに僕はこの参考書を買って合格しました!10年分の過去問が収録されているのでがっちり勉強できておすすめです。用語解説や問題解説も豊富でした。
それ以外の問題については全て暗記で何とかなるので楽勝です!
技能試験の概要と対策について
試験問題はあらかじめ13種の単線図が公表されていてその中から一つが出題され、それを実際に配線する形になります。なのでしっかりと勉強しておけば安心ですね。試験時間は40分になります。
合格基準はないですwしかし、不合格基準があり、重大欠陥が一つでもある又は軽欠陥が3つ以上あれば不合格となります。
それから、試験を受けるにあたって注意しなければならないのが工具は持参しなければならないってことですかね。僕の場合は学校が貸してくれたのですが...
 | ホーザン(HOZAN) 電気工事士技能試験工具セット P-958VVFストリッパー P-737... 16,200円 Amazon |
Amazonでも売ってるのですが値段を見て(*_*)です。受験料よりも高いんですね。
試験の対策としてはやはり参考書の購入を強くお勧めしますね。
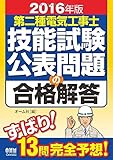 | 2016年版 第二種電気工事士技能試験 公表問題の合格解答 1,296円 Amazon |
僕が使ってた参考書になります。レイアウトがイマイチだな。って感じがしたのですが、試験に関することは全て網羅されているので頼りがいはありました。
参考書を参考にしながら公表問題を2,3周しておけば合格は間違いないと思います。
感想
僕の場合は筆記試験は試験2週間前にあわてて勉強を始めましたが無事合格。技能試験のほうはしっかりと一か月前から対策して合格できました。
第二種電気工事士は簡単に取れる割には実用性が高い資格ですので皆さんぜひトライしてみてください!応援してます!
