【#59 Singlemalt Xmas -Cheers to Amber Eyes- / Dec.25.0087】
UC0087.12.25、グラナダ。
エゥーゴとティターンズの騒乱は未だ混迷を極めている状態ではあるが、その不穏さの中でも、銃後の市井の営みは続いている。クリスマス——人類は西暦を捨てたにもかかわらず、やはりこの日は華やいだ空気を皆が味わう。
昨日、アンナから聞いた、UC0079の12月24日、ソロモン攻略戦の話を思い出す。今も、まだエゥーゴとティターンズの騒乱が落ち着いたわけではない。だが、8年前は本当に、こんなことを楽しむ余裕など、この宇宙にはなかったように思えた。
(戦地にいたから、そう感じただけか……?)
そんなことを考えながら、氷を伝って注がれていく、琥珀色の液体を見ていた。
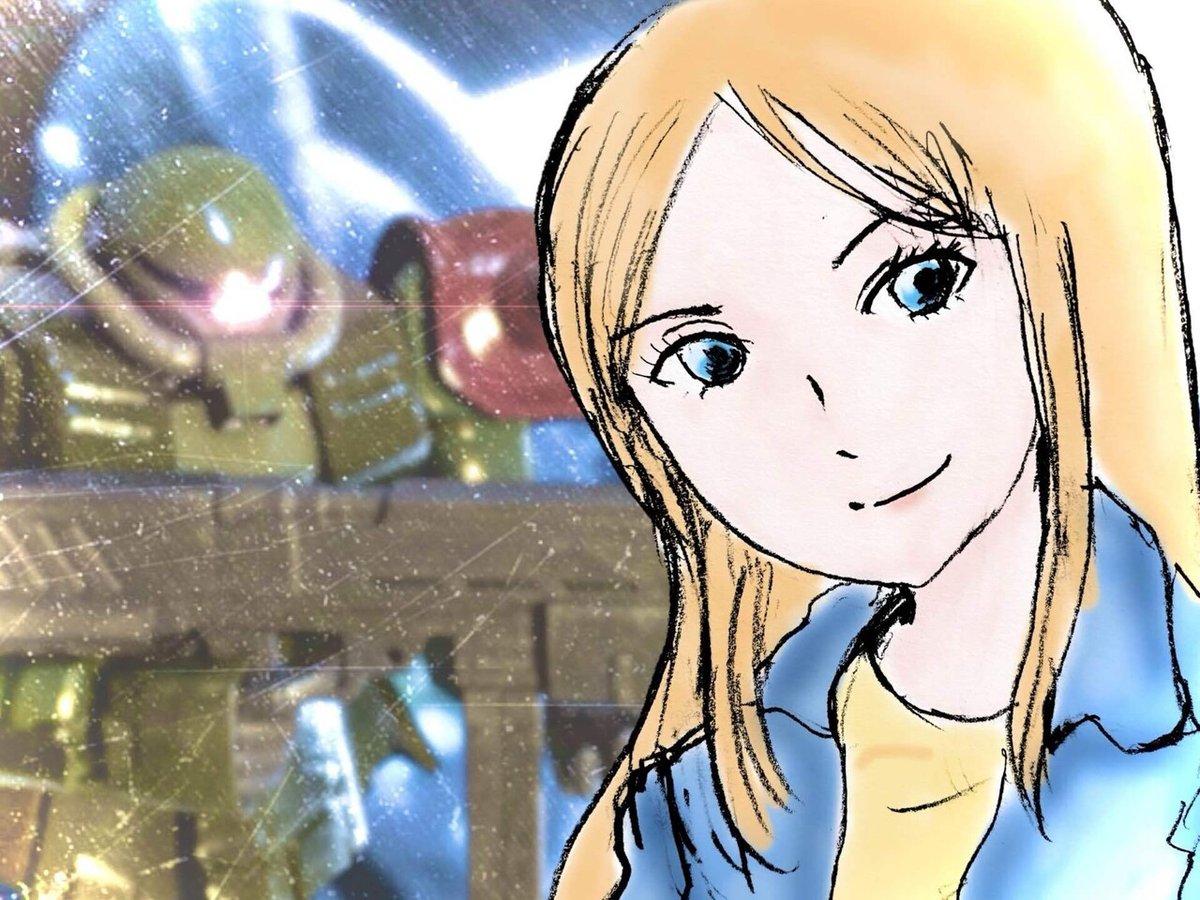
「……で、ジオンの捕虜?になっちゃって。民間人じゃないから、捕虜とは言わないのかな?まあいいや。食事がさ、すごい酷かった。」
グラナダの片隅にあるバーの、小さなステージの上では、ギターを抱えた亜麻色のロングストレートヘアーの女が、からからと笑いながら話している。
「若い軍人のカップルにお世話になってさ。彼氏の方はパイロット。彼女の方は、天使みたいに可愛らしい衛生兵だった。2人とも、生きているといいけど。」
やがて、軽快にギターをかき鳴らすと、美しい声で歌い始める。
「あれって……。」
ロックグラス同士をチンと合わせると、妻のキョウ・ミューラーが言う。
「例の”マリア”だろう。お忍びのライブかな。」
ヘント・ミューラーは、応えながら、ジャパニーズ・シングルモルトに一口、口を付ける。ステージ上にいるのは、1年戦争当時から人気のある、反戦シンガーの"マリア"だ。サイド5の航空宇宙祭でもステージがあった、宇宙世紀のスターだ。
昨日、アンナに呼び出されて行った士官クラブのバーとは違う、隠れ家のようなひっそりとしたバーだ。クリスマスの夜ともなると、さすがに予約を取っていないと入れない。席は当然満席だが、もともとひっそりとやるのがセールスポイントなので、"マリア"のようなスターが来ていても、客でパンパンということもない。
「こういう、落ち着いて、っていうのもいいわ。」
昨日、イブの夜は、キョウにチタ・ハヤミを交えた3人でささやかにホームパーティーをする予定が、結局仲間を皆呼んで、飲めや歌えの騒ぎになってしまった。グラナダにあるエゥーゴの居住区にある、世帯用コンパートメントでは手狭になり、結局上官のラッキー・ブライトマンの助けを借りて、空いていたミーティングルームを急遽抑えた。
「デラーズなんとかだ、エゥーゴだ、ティターンズだ……最近は、何?アクシズ?ハマーン……ハーン……だっけ?」
客からの指摘を受けて、え?違うの?と、声を上げている。
「ジオンの残党?まあ、なんでもいいよ。あたしに言わせれば、アイツらは揃いも揃って、みんな同じバカだから。」
"マリア"が、この宇宙で続く騒乱を痛烈に批判している。
「わたしたちも"バカ"の一員ですね。」
キョウは、苦笑いを浮かべながら、声を潜めて夫に囁いた。
「……どうかな、彼女のいつもの主張だと、わたしたちは除外されるのでは、と思ってしまうがな。」
ヘントの応えに、キョウは不思議そうに数度瞬きした。まあ、続きを聞いてごらん、と、ヘントは言う。ヘントは、割と"マリア"が好きだ。彼女の美しい歌声もだが、その主義主張に気骨があるのだ。
しかし、”マリア”は、一旦話をやめ、ジャズ調の曲を奏で始めた。
ウイスキーが好きだろう、と、相手に問いかけるようなフレーズから、曲は始まった。後ろに控えるジャズバンドの演奏も加わり、ムーディーな雰囲気がバーに充ちる。
「あ、この曲……。」
キョウが、振り返って、ステージを見る。
「覚えてる?」
「ええと……?」
ヘントが言葉を詰まらせると、覚えていないの?と、キョウは悪戯っぽく微笑む。
「すまん。」
「初めて、2人で飲んだとき。」

「……”ベルベット作戦”の時だな。中東の、ダマスカス。士官クラブ。」
「そう。」
キョウは満足そうに微笑んだ。
それは、さすがに覚えている。
一目惚れ、だった、と思う。まだオデッサにいた頃、部隊に着任の挨拶を述べる彼女の、凛とした空気に、堪らなく惹かれた。だが、彼女に好意を抱いていると、はっきりと自覚したのは、中東の作戦の合間に、ダマスカスで酒席を共にしたその時からだ。敵からの夜襲に2人で対応した後、士官クラブで飲んだ。
「3人で飲んでいたのに、イギー少尉がいつの間にか席を外して。」
キョウが楽しそうに話す。
「ああ、そうだったな。」
「その時も、この曲、流れていたわ。」
「そうだったか?」
「そうよ。」
歌詞は、”もう少し話をしよう”と語り掛けるような内容になっている。そうだ。この歌詞。思い出した。
「よく覚えているな。」
ヘントが感心して言うと、そりゃあそうよ、と、キョウは自信に満ちた顔で胸を張って見せる。
「わたし、あなたのこと、大好きだから。」
「……出たな、得意のストレート。」
ヘントが顔を赤らめると、つられて、キョウも赤くなった。
「そろそろ、よろしいですか?」
幸せそうに笑い合う2人に、バーテンが話し掛けてくる。
「ああ、頼む。」
「何?」
キョウは、半ば確信しながらも問い掛ける。ヘントは曖昧に応えたが、バーテンがカウンターの下をごそごそとやるのを見て、キョウは目を輝かせた。
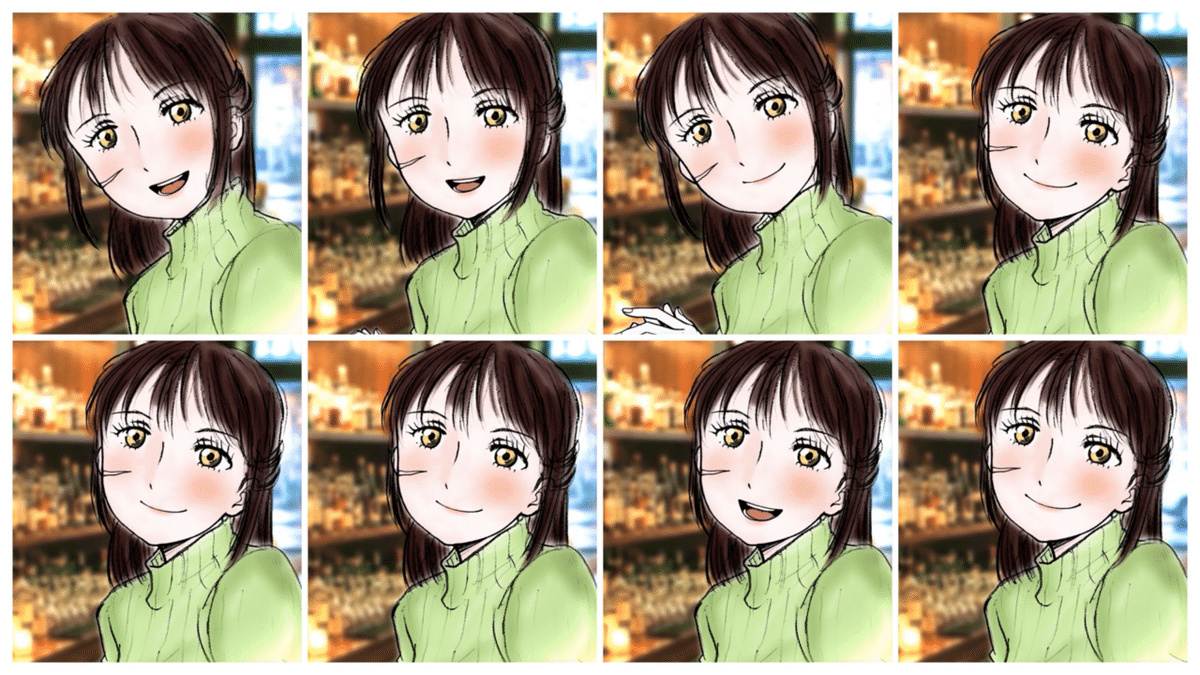
「粋なこと、しますね。」
「ど、どうだろうか……。」
しかし、バーテンがウンターの下から取り出した巨大な包みを見て、キョウはわずかに顔を引きつらせた。少し、想像と違っていた。
「……大人のプレゼントって、もっと、こう、小さな包みに入っているような……。」
え、と、ヘントは驚いたような声をあげる。
「もしかして、やらかしたか?」
少し、顔色が青ざめる。
「拝見します。青ざめるのは、それからでいいんじゃない?」
そんなヘントを見ながら、キョウはふふっと微笑み、包みを受け取る。大きさの割には意外と、軽い気がする。そして、丸い。
「開けてみても?」
「あ……ああ、もちろんだ。」
不安になったのだろう。目が泳いでいる。
そんな夫の様子をひととおり楽しんだ後、”マリア”の歌う軽快なクリスマスソングを聴きながら、キョウは包みを開けた。
中からは、大きな、丸い球体が表れた。球体の中央を横断するように、緩やかな曲線の溝。そして、チョンと、小さな楕円が2つ、瞳のように乗っている。
「これ……。」
瞳の楕円が、ピカっと光ると、ソイツは球体の上に付いた小さなハッチを2つ、パカッと開けて、パタパタと羽ばたかせるようにした。

「キョウ、ゲンキカ、キョウ!」
”ハロ”というペットロボットだった。
「……離れ離れだったときに、渡せれば、なんて思っていたが……。」
1年戦争の英雄、アムロ・レイが所持していたということで、戦後ちょっとした流行になったが、今は巷ではほとんど見ない。機械好きの間では未だ愛好されていると聞くくらいで、まあ、希少性がないことはない。
「"キッド"の助けも借りて、パーツをかき集めて、組んでみた。」
手製、というわけだ。まあ、特別……な、贈り物、とは、言えなくはないのか。
「この色……?」
カラーリングのカスタマイズは聞いたことがない。たしか元はライトグリーンのボディのはずだが、まるでウイスキーボトルのように、光沢のある深い茶色をしている。
「愛好家の間では、自分たちで思い入れのある色にすることが……その、ある、らしい。調べてみたら、”シングルモルト・カラー”というのがあったから……。」
ヘントは、自身なさげに応える。
「……可愛くないわ。」
キョウは、呆れたようにため息をついた。
「茶色いハロなんて、まるで煮玉子みたいじゃない。」
ところどころ入っているセールカラーも見ると、栗に見えなくもない。
「そ、そうか……渋くて良い色で、評判だと聞いたのだが……。」
ヘントは、目に見えて狼狽している。撃墜された時よりも焦っているかもしれない。
「愛好家の方々には、そうでしょうけど。」
そうか、と、少し寂しそうな顔をしてから、ヘントは言う。
「シングルモルト・カラー……君の瞳の色と同じだと思った。」
言い訳のように、けれど真剣に、ヘントが言った。
「君の瞳は、いつだって綺麗だ。」
そして、静かに続ける。
「だから、このハロも、俺には一番綺麗に見えた。」
その言葉に、キョウは思わず赤面する。この男は、こういうキザな台詞を、大真面目に、計算なしで言うから始末が悪い。
「あ、ハロだね、それ、懐かしいな、待ってたよ!」
"マリア"の声だ。いつの間にか曲が止まっている。"マリア"のライブは再び"トークタイム"に入ったらしい。ハロの出した声は存外大きく、小さく静かなバーには場違いなほど、人の気を引いてしまったのだ。
「オッス!マリア、オッス!」
「おっす!あたしのこと、知ってるか、お利口だね!」
"マリア"は気さくに返す。
「おい、ハロ、静かにしろ!」
ヘントは慌てたが、"マリア"はいいよ、と、笑う。