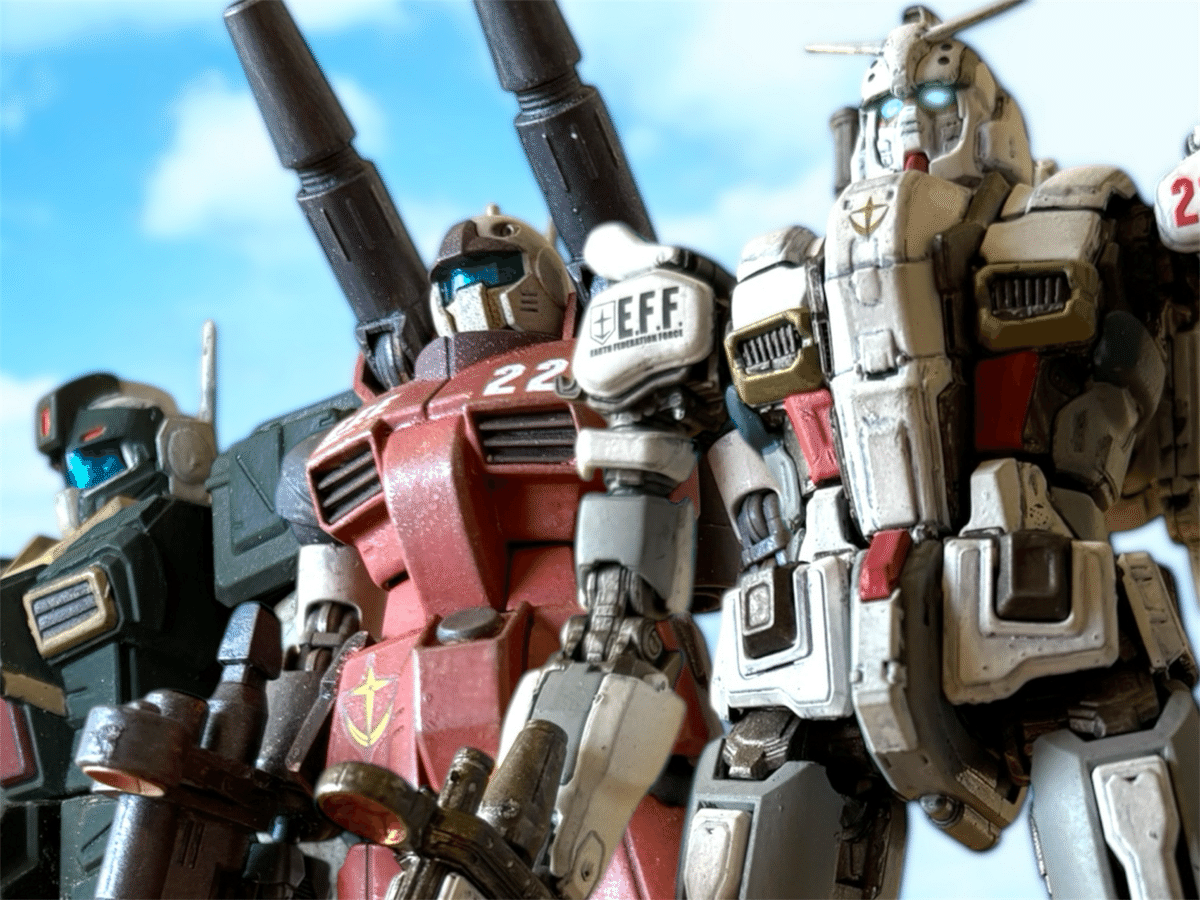
「基本戦法は“シングルモルト“でいく。中隊5個でそれぞれ仕掛けろ。」
明け方、出撃前のブリーフィングで、ラッキー・ブライトマン少佐が宣言する。先日の、シングルモルト作戦は、レバント侵攻第3軍内では、新戦法“シングルモルト“として定着した。
「先鋒はキョウ・ミヤギ曹長のガンキャノン。右翼をヘント・ミューラー少尉のガンダム、左翼をイギー・ドレイク少尉のジム。イギー少尉の中隊は、そのまま突出して、第4軍と合流してサラサールに突入しろ。その頃には“ロレンス“も突入しているはずだ。」
了解、と3人の息が揃う。
「後衛からはテッド少尉。ディーン中尉も、もう行けるな。すまんが、機体を遊ばせておく余裕はない。やってもらうぞ。」
敵の奇襲を受けてから、トラウマのためにコクピットに入れなかったディーン中尉も、今回の総攻撃には参加する。中尉は、青白い顔で、それでも、はっ!と切れのある返事をする。
「後衛はガンタンク隊を守りながら進軍。中尉と少尉のジムにはビームスプレーガンを持たせておけ。」
出撃は、120分後だ、と声を張り上げ、少佐は全軍に配置を命じた。
~~~~~~~~~~~~~~~

「おい、今度は撃ち落とされるなよ!」
仮設ハンガーに向かう道すがら、イギーがいつもの調子でヘントをからかう。
「善処するよ。」
「駄目です。善処ではなく、お約束を。」
静かに、だが、強く、確かな口調でミヤギが言う。
「サラサールを陥とせば、この方面の戦いは終わります。そうしたら、休暇を申請しましょう。その時は、ご一緒に。」
「はいはい、デートの約束ならお二人でどうぞ。」
「違います、イギー少尉もご一緒に。行き先はジャブローで。」
先日、ダマスカスのバーで話した身の上話。イギーの妻子がジャブローに疎開していることを言っているのだろう。ミヤギからの意外な提案に、ヘントもイギーも顔を見合わせたが、その後、2人でニッと笑った。
「次は、出撃を気にせず、朝まで飲みましょう。」
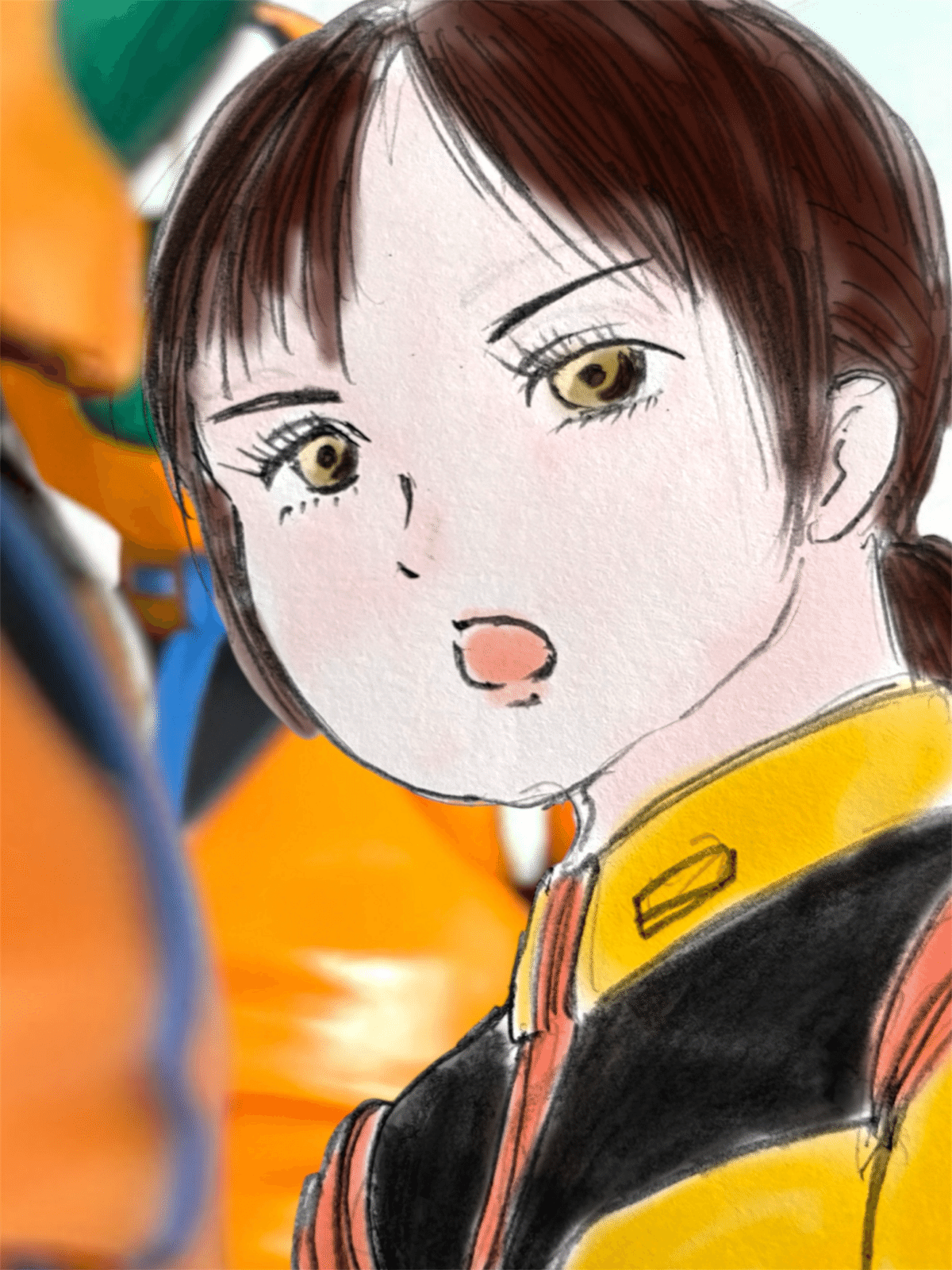
「なあ、曹長、出撃前にそういうの、縁起悪いんだぜ。」
イギーが楽しそうに応じる。
「何て言った?ほら、オールドムービーによくあるよなあ、ヘント?」
「"死亡フラグ"。」
「そう、それだ。」
「それこそ、くだらないジンクスです。人は——、」
ミヤギは、真剣だ。
「こういう時、人は、明日への約束が欲しくなるものです。この約束は、きっと、何があっても生き抜く力の源になる。」
だから、と、呼吸を置いた後、歩みを止め、2人の袖を掴んで顔を見る。
「必ず、お約束を。全員で生還しましょう。」
~~~~~~~~~~~~~~~
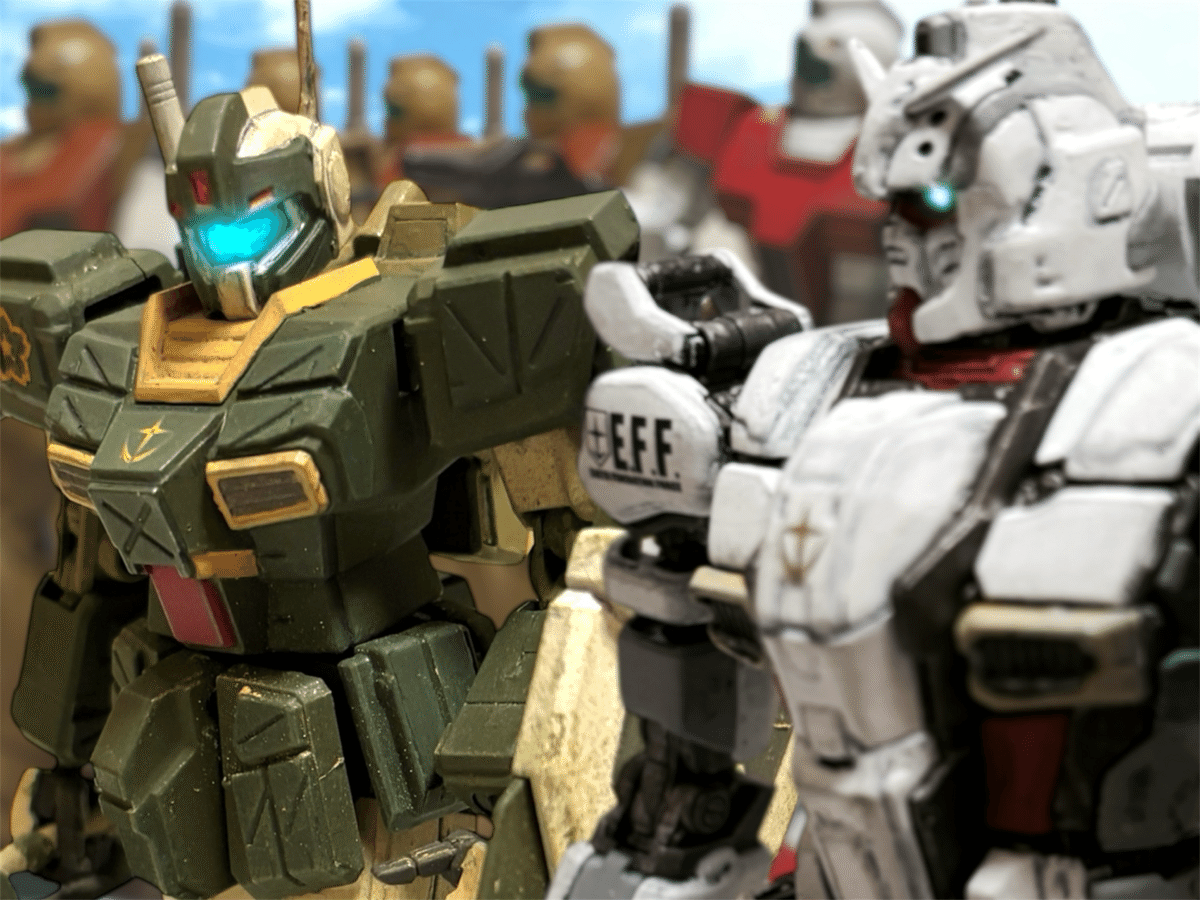
『要は俺らと飲んだのが、よほど楽しかったんだろう。可愛いところもあるやつじゃないか。』
ヘントの通信機に、機体に乗り込んだイギーから通信が入った。
「だから、直に言ってやればいいじゃないか。」
『嫌だね、そういうのはお前がやれ。』
じゃあ行くぞ、と、イギーは機体を歩ませ、中隊の集合地点へと向かう。最後に、通信を送ってきた。
『お前こそ、ちゃんと言ってやったんだろうな。この後、どっちかが死んじまっても知らねえぞ。』
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
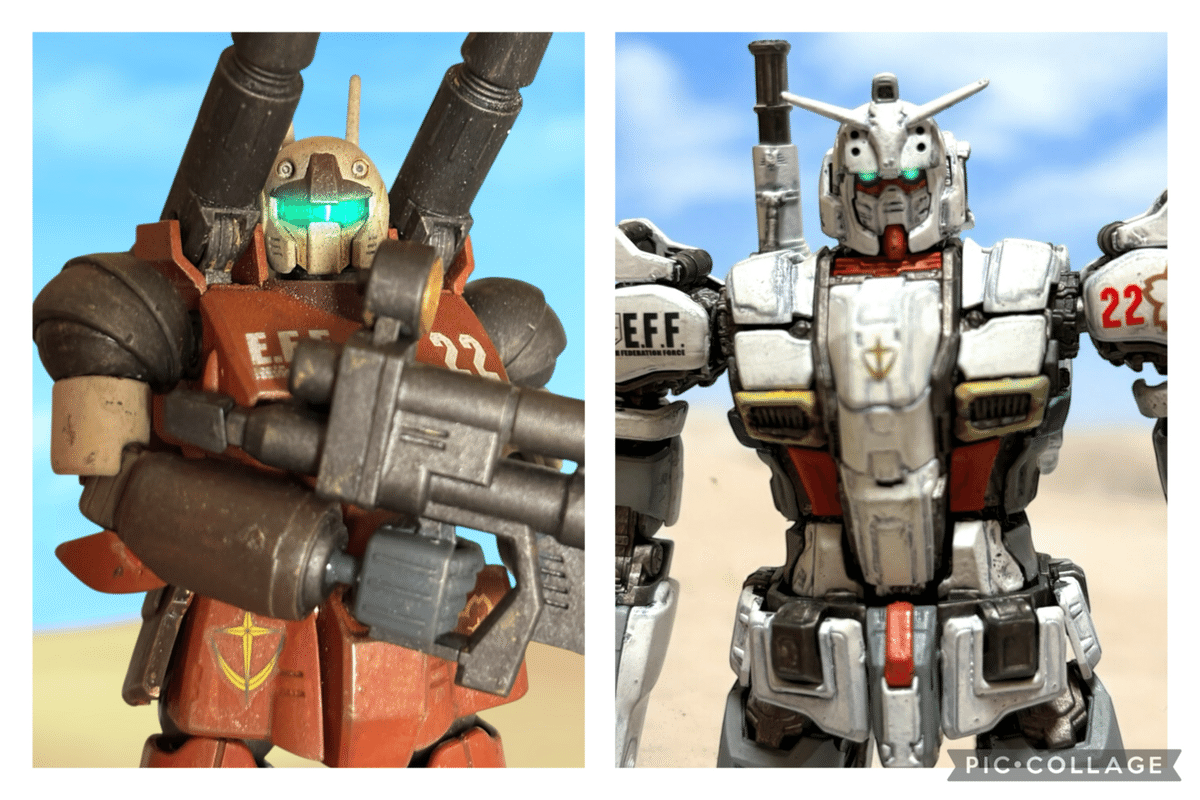
「ミヤギ曹長。」
イギーを見送った後、ミヤギにも個人通話で通信を送る。
「ダマスカスの夜襲や、ルトバでの"シングルモルト"で、君は目立った働きをしている。敵の戦力は、君のガンキャノンとガンタンク隊に向くと思う。」
覚悟の上です、とミヤギは返す。
「もちろんだ。だが、"シングルモルト"のときの敵も然り、やはりこの砂漠の敵は手強い。"血塗れの左腕"もまだ残っている。」
だから、と、少し躊躇った後、ヘントは続ける。
「君に危険が迫ったなら、俺を呼べ。もしその時は、作戦の全容よりも、俺は君を守ることを優先する。」
そこまでを告げ、ミヤギの返事を聞かず、ヘントは通信を切った。
~~~~~~~~~~~~~~~
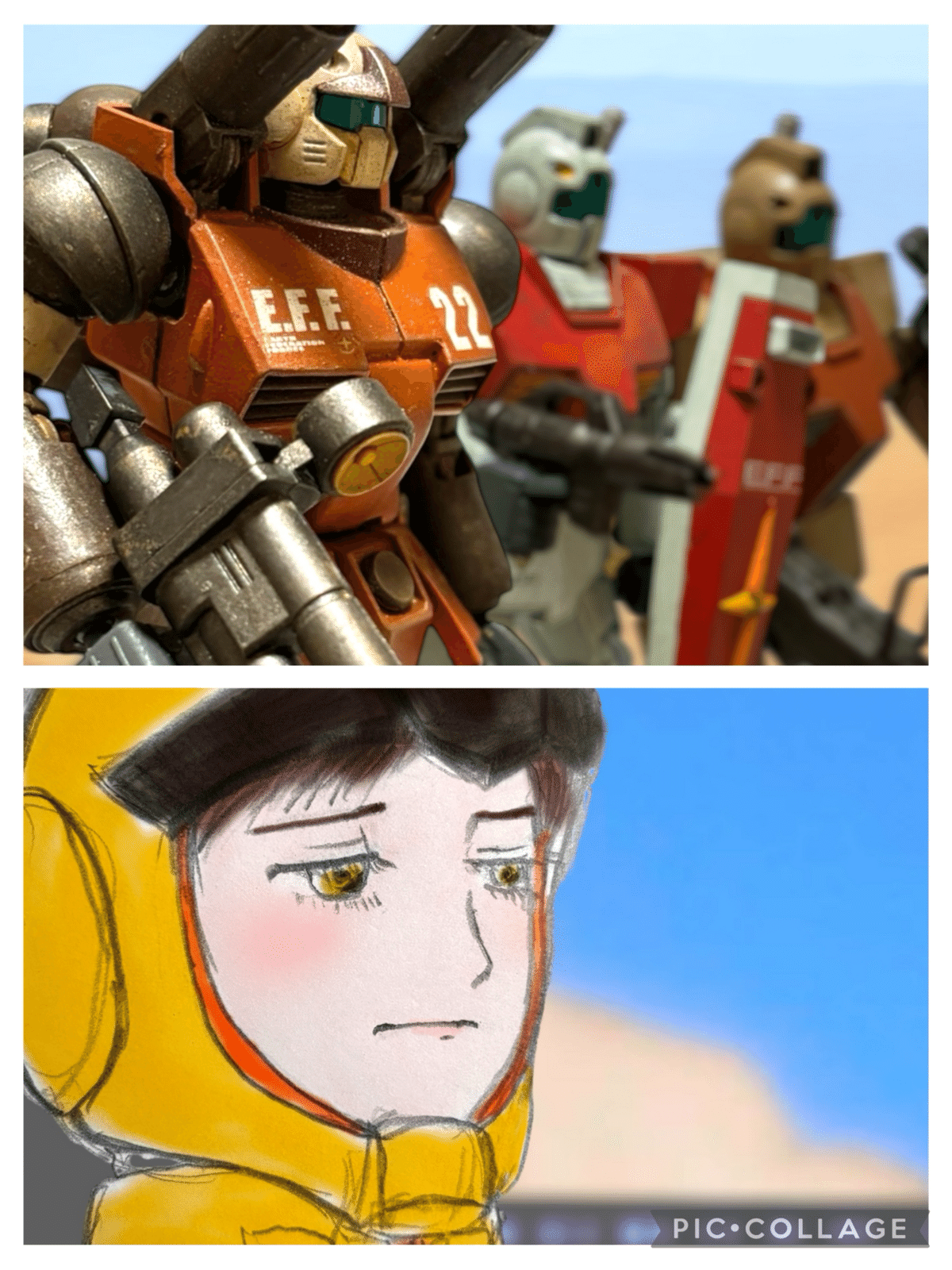
全軍が進軍する。既に、トルコから南下してきた第1軍と第2軍が、サラサールへ攻撃を始めているという。砂漠を突っ切て突入する予定の第4軍も、夜半には出撃している。いつもの物量戦術は、1、2、4軍がやってくれるのだ。自分たちは、最後のとどめに、"シングルモルト"戦法で突入し、敵のMSを殲滅する。
(俺を呼べ、って……どうやって。)
行軍中、ミヤギは、先ほどのヘントの通信にやや腹を立てていた。自分を心配してくれているのか。それとも、これまではっきりさせずにきた、自分への好意を、こんなタイミングで示しているのか。彼はいつも、言葉が足りない。
(わたしはニュータイプじゃない、って、言ったじゃないですか。)
人の心の中など、分かるはずもないのだ。思うことがあるなら、はっきり言葉にしてほしい。
(でも、はっきりさせずにって……それは、わたしも同じか。)️
昨日は、泣き止むまでずっと傍で待ってくれた。寄り添った言葉をくれたことも、衆人環視の中にもかかわらず、ああして付き合ってくれたくれたことも、うれしかった。けれど、ああまでして、互いにそれらしい言葉はなにも交わしていない。言ってしまうべきだったのだろうか。もしかしたら、今日の戦いでどちらかが、命を落としてしまうこともあり得るのだ。
例の稲妻が走る感覚の後、次いで、肌をつき刺すような、鋭いプレッシャーが全身を襲った。
「何っ……!?」
激しい、敵意というか、生の感情が、前方の砂塵の中から自分に向かってくるのを感じる。
「敵!?全機、警戒!」
率いている中隊に通信を送るが、レーダーはまだ敵機を捕捉していない。
『曹長?』
2番機が応じた瞬間、ミヤギの"予言"どおり、敵機の襲来を告げるアラートが全機に入る。遠く、砂塵の中に、巨人の影が見える。
(当たりだ!先頭の、あのキャノンだな!)
聞こえるはずのない敵の声が、聞こえた。あの時と同じだ。
(殺せ!)(殺せ!)(殺せ!)
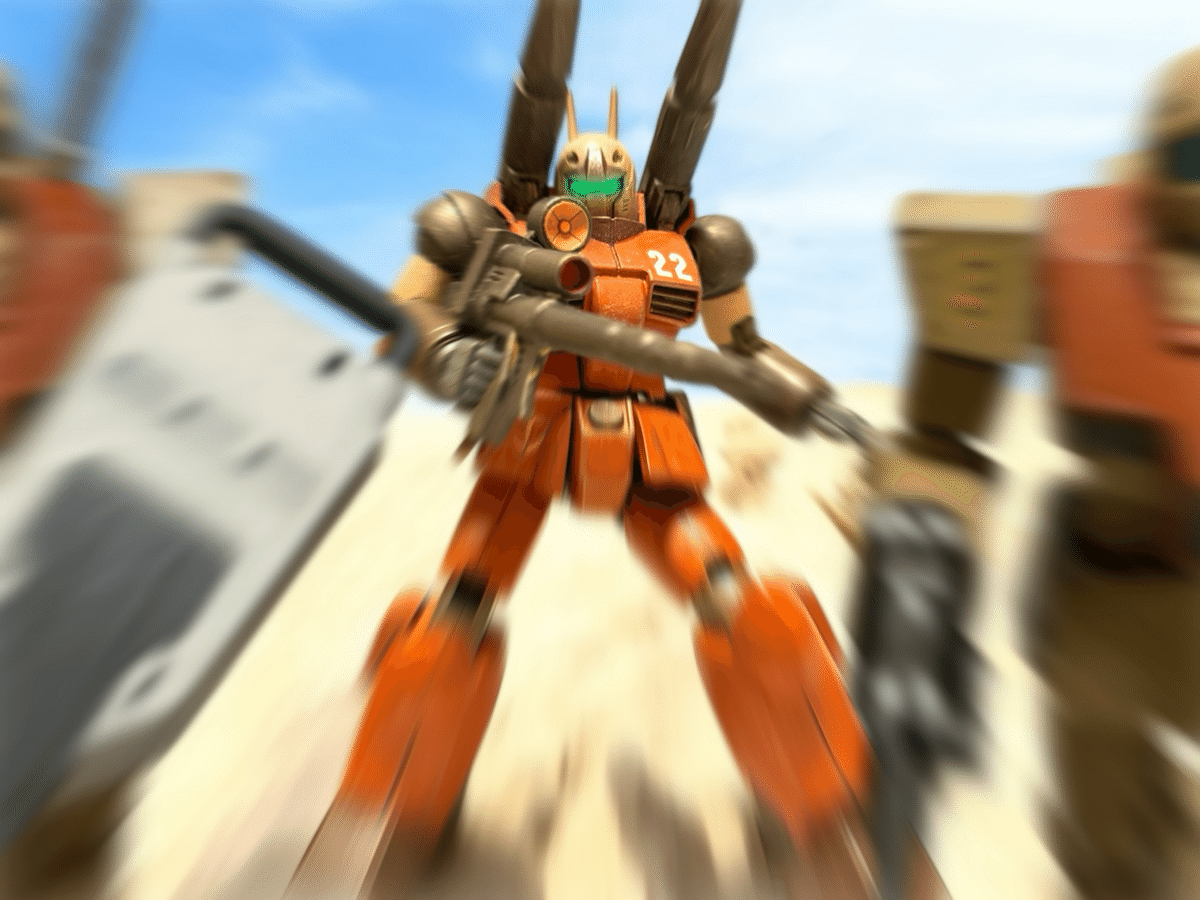
激しい殺意が、自分一人に向けられているのが分かる。
ミヤギは、思わず怯み、機体の歩を止めた。
『曹長!?』
追い越して行った中隊の先頭、2番機が、思わず振り返る。その間に、敵機は激しい砂塵をあげながらどんどん近づいてくる。
ミヤギは、自身が率いるこの中隊は、自分の先制攻撃こそが戦法の要と理解していた。が、会敵早々、その前提を崩してしまった。仲間が、そして、自分が危険にさらされると、直感が告げている。
「ヘント!」
君に危険が迫ったなら、と、彼は言った。今が、その時だ。だが、どうやって。彼は今、どこを進軍している。
右翼の後方から、更に1機、敵のザクの襲来を知らせるアラートが鳴り響いていた。
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
【To be continued...】