
人気ブログランキング 資格・スキルアップへ
にほんブログ村 資格ブログへ
るん♪りか語録/1月28日
偶然はない。すべて必然。
いいことも、悪いことも、すべて必要な経験。明日の糧。
難しくないけど、難しい試験
私が本屋さんで、ぱらぱらと社労士の過去問を見た時の印象は、簡単そうというものでした。
その時の比較対象は、司法試験。
高校の定期テストとの比較で言えば、社労士試験は難しいです。
どの試験と比較するかで、本人の感じる難易度というものが随分と違ってきます。
ですから、社労士試験が難しいかどうかの尺度は、人によって異なるということは、心にとめておいた方がいいかもしれません。
私の場合、労働基準法なら労働基準法の勉強をして、すぐそのところの過去問を解くと、そこそこ解けました。
それは、生命保険協会認定FP(トータルライフコンサルタント)やDCプランナー2級の試験で、引っかけ問題に対する免疫がついていたからだと思います。
初めて資格試験を受験される方でしたら、なかなか要領がつかめない場合もあるでしょう。
でも、繰り返し演習すれば、段々と慣れてきます。
私は、自分のことは棚上げして、繰り返しをお勧めしたいと思います。
繰り返しを避けるるん♪りか式短期集中は、コストパフォーンマンスの高さはウリですが、爪が甘いので、1点差落ちのリスクがあり、人にお勧めする自信はありません。
それはともかく、ある科目の勉強をして、その科目の問題を解くということには、何ら問題はありませんでした。
問題が生じたのは、10科目の勉強が一通り終わってから。
復習をせずに、次々と進んだため、どんどん忘れていたのですが、宅建や行政書士試験準備では経験しなかったあることに遭遇しました。
各科目の知識がゴチャゴチャになるということ。
似て非なるものが多い社労士試験ならではのことです。
「与託」と「預託」の一文字引っかけなど、宅建や行政書士試験にはない重箱の隅をつつく嫌らしさもあり。
一見、簡単に見える社労士試験問題です。
でも、思いのほか、合格答案を作るのは、大変。
要するに、確実な知識のキープがしんどいのです。
何故この程度のレベルの問題で、合格率が1桁なのか。
その謎が解けました。
問題そのものは、決して難しくはない。
でも、8月の第4日曜日の試験日に、必要に応じて的確にアウトプットできる状態にしておくのは、難しい。
といっても、択一式の方は、過去問+αの知識で、合格点がとれる問題です。
運に左右されることはないので、合格点未達であれば、知識不足か演習不足でしょう。
難しいのは、選択式です。
初学の頃は、選択式よりも択一式の方が難しく感じられました。
皆さん、そうだと思います。
でも、ある意味、合格ライン上の人が怖いのが、選択式と言えるでしょう。
毎年、合格点クリア、1科目だけ基準点未達という、選択式1点差落ちで涙を呑む不合格者は少なくありません。
あと1点のために、もう1年。
皆さんには、私のような失敗をしてほしくないと思っています。
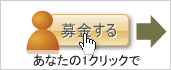 すべてはささやかなことから♪
すべてはささやかなことから♪清き1票を
 あなたにもいいことありますように
あなたにもいいことありますように
合格の桜咲くように 縁起のいい富士山

クリック① ↑ ↑ クリック② ↑ ↑
どうもありがとうございます。感謝のうちに
