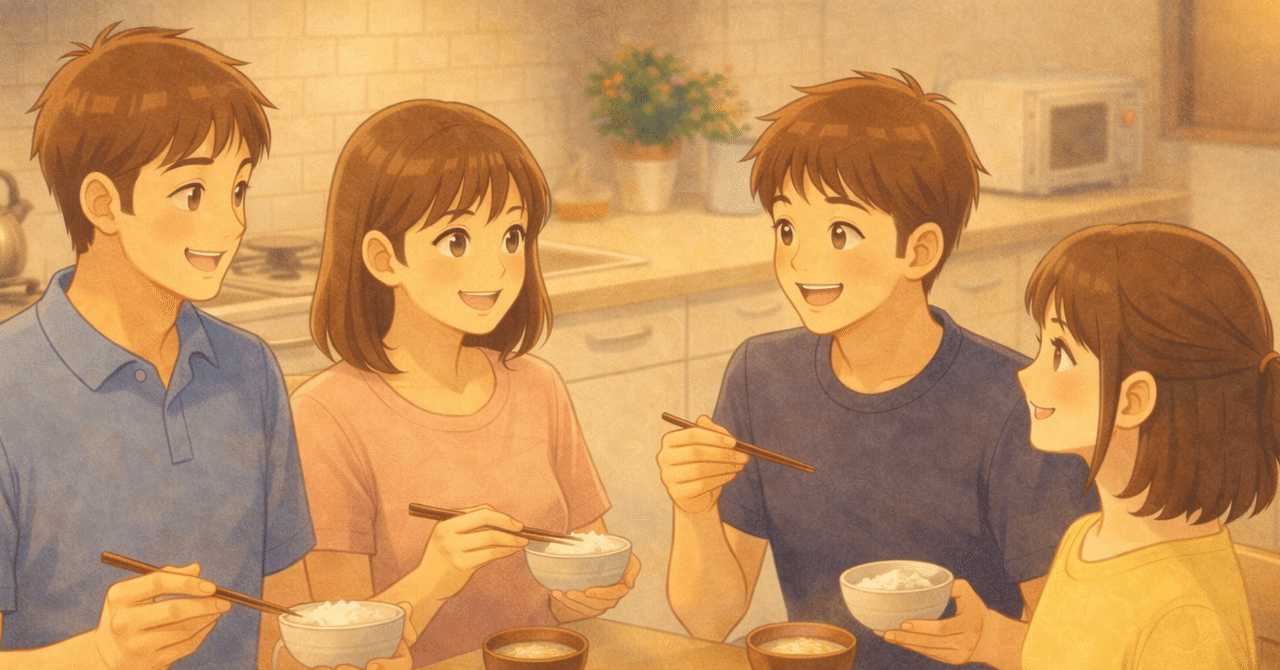千葉の郊外にある分譲マンションで暮らす田島一家は、どこにでもある40代の家族だった。
品質管理の仕事に誇りを持つ夫・恒一は、正しさを重んじるあまり、家でも職場でも「なぜそうしたのか」を問い続けていた。
だがその言葉は、いつの間にか人を追い詰め、妻・由美や同僚との距離を広げていた。
一方、パート先の市役所外郭団体でクレーム対応に悩んでいた由美は、ある一冊の本と出会う。
『なぜと聞かない質問術』。
そこに書かれていたのは、
- 人は理由を問われると心を閉ざす。
- 事実を聞かれると心を開く
という、静かな革命だった。
半信半疑で「なぜ?」をやめ、「いつ・何が・どのように」と聞くようになった由美の周囲は、少しずつ変わり始める。
職場ではクレームが感謝に変わり、家庭では冷え切っていた会話にぬくもりが戻る。
その変化に戸惑いながらも、恒一は自分の“正しさ”が人を遠ざけていたことに気づき始める。
問いを変えることで、人生は変えられる。
これは、事実を聞くことで家族と仕事を取り戻していく、40代夫婦の再生の物語である。
※本ページはプロモーションが含まれています
「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた 「なぜ」と聞かない質問術 [ 中田 豊一 ]
第1章 理論への心酔──「人生を変える一冊」との出会い
「答えを知った気になったとき、人は一番、見えなくなる。」
由美がその本を手に取ったのは、昼休みの薄暗い休憩室だった。📖
市役所の外郭団体で働く彼女は、今日も電話越しに謝っていた。
「申し訳ありません」
「確認いたします」
「担当に伝えます」
その言葉を何十回も繰り返すうちに、
自分の声がどこか遠くのもののように感じられていた。😮💨
そんなある日、机の隅に積まれた雑誌の中に、
一冊のビジネス書が紛れ込んでいたのを見つけた。
『なぜと聞かない質問術』。
「……なぜ、と聞かない?」
由美は思わず、つぶやいた。
クレーム対応で毎日のように浴びせられるのは、
「なぜ遅れたの」「なぜこうなったの」という言葉ばかりだ。
自分もまた、同じ言葉を使って相手を問い詰めている。
そのことに、ふと胸の奥がチクリとした。💭
ページをめくると、こう書いてあった。
- 人は理由を問われると、防御する。
- 事実を問われると、語り始める。
由美は、その一文の前で指を止めた。
まるで、今の自分を見透かされているような気がしたのだ。✨
その夜、マンションのリビングで、夫の恒一は黙ってテレビを見ていた。
仕事から帰ってきても、ほとんど口を開かない。
話しかけると、必ず「それは違う」「正しくはこうだ」と
理屈が返ってくる。
「今日ね、こんな本を読んだの」
由美がそっと差し出すと、恒一はちらりと表紙を見ただけで言った。
「また自己啓発?どうせ、感情論だろ」
その一言に、由美の胸が少し縮む。
彼女は黙って本を引っ込めた。
(この人は、正しさの中にいる。
でも……正しさって、こんなに寂しいものだったっけ)🌙
由美は、ページをめくりながら、ゆっくりと読み進めていった。
- なぜをやめ、いつ・どこで・何が起きたのかを聞く。
- 相手を評価せず、状況を一緒に見る。
それは、どこか祈りのような対話の仕方だった。🙏
翌日、由美は職場で初めて
“なぜを使わない”クレーム対応に挑戦した。
電話の向こうで、男性の声が荒れている。
「この書類、まだ届いてないんだけど!」
いつもなら、「なぜ届いていないのか」を
確認しようとしてしまう。
でも、由美は一瞬だけ呼吸を整えて、こう言った。
「いつ頃提出されたでしょうか?」
相手が一瞬、言葉に詰まるのが分かった。
「え……えっと、先週の木曜です」
「どの窓口で提出されましたか?」
「3番窓口……だったかな」
「ありがとうございます。こちらで確認しますね」
電話を切ったあと、由美の心臓は少し早く打っていた。
不思議と、相手は怒鳴らなかった。
むしろ、少し協力的だった。
(……これって、偶然?)💓
その日の帰り道、由美は自転車をこぎながら、
胸の奥がじんわり温かくなるのを感じていた。
何かが、ほんの少し動いた気がしたのだ。🚲
恒一が普段より遅く家に帰ってきた。
無言で食卓に座った恒一に、迷った末にこう聞いてみた。
「今日は、何時ごろ会社を出たの?」
恒一は驚いたように顔を上げた。
「……七時くらいだけど」
いつもの「なんで遅いの?」ではない。
ただの事実。
その空気の変化に、由美自身がいちばん驚いていた。
(もしかして……
この本、ただのノウハウじゃないのかもしれない)✨
理論に心酔するほどの確信ではない。
でも、小さな手応えが、確かに胸に残っていた。🌱
第2章 表面的な実践と高揚感──知識だけで無敵になった錯覚
「うまくいき始めた瞬間、人は一番、勘違いしやすい。」
由美の中で、何かが確かに変わり始めていた。✨
クレームの電話は、以前よりも静かに終わることが増えた。
「なぜ?」を使わずに、
「いつ・どこで・何が」を聞くだけで、
相手が落ち着く。
それが、何度か続いた。
(これ、効いてる……!)
心の奥で、小さなガッツポーズが生まれる。
まるで魔法の呪文を手に入れたような気分だった。🪄
職場でも、由美は少し誇らしかった。
同僚がクレームに疲れ切っている横で、彼女は淡々と事実を聞き、淡々と処理していく。
上司からも、「最近、対応が安定してるね」と言われた。
その言葉に、胸がふわりと浮く。
(やっぱり、このやり方が正しいんだ)😊
家でも、由美は“質問の人”になっていた。
「なんで宿題してないの?」と娘に言いそうになったとき、
ぐっとこらえて、こう言い換える。
「今日は、何時から勉強してたの?」
「宿題は、何ページあるの?」
娘は戸惑いながらも、ぽつぽつと答える。
その様子を見て、由美は内心でほくそ笑んだ。
(ほら、なぜを使わないだけで、こんなにスムーズ)🌱
恒一のことも、同じだった。
いつもなら、「なんでそんな言い方するの?」とぶつかっていた場面で、由美は事実質問を投げる。
「それって、いつの情報?」
「何で知ったの?TV? 雑誌?」
恒一は少し面食らいながらも、答えざるを得ない。
理屈の人間である彼にとって、事実を問われることは
居心地が悪くなかった。
由美は、心の中で小さく勝利を感じていた。
(これで、この人ともちゃんと話せる)✨
けれど、その高揚感は、知らず知らずのうちに
“慢心”に変わっていた。
職場で、ある年配の女性から強いクレームが入った。
「何度も説明してるのに、あなたたちは全然分かってくれない!」
由美は、いつもの調子で言った。
「いつ、どの窓口でお話しされましたか?」
「そんなことじゃなくて!」💢
女性の声が、さらに大きくなる。
由美は少し焦りながらも、続ける。
「どの書類を提出されましたか?」
だが、相手の怒りは収まらなかった。
「あなた、私の気持ち、分かってるの!?」😠
その瞬間、由美の胸に、冷たいものが落ちた。
(あれ……?
事実質問、効かない……?)💧
家でも、小さな歪みが生まれ始めていた。
由美は、家族の感情に寄り添う前に、つい“質問の型”を
当てはめてしまう。
「いつからそんな顔してるの?」
恒一は、少し疲れたように言った。
「……別に」
その言葉の奥にある何かを、由美は見ようとしなかった。
“正しい質問”をしている自分に、どこか酔っていたからだ。
(私はもう、うまくやれてる)😌
その錯覚が、静かに、次の挫折の準備をしていた。🌙
第3章 現実の壁と最初の挫折──本通りにいかない焦り
「正しいやり方が、いつも正しいとは限らない。」
その日、由美は職場のトイレで、しばらく動けずにいた。
洗面台の前で、蛇口から流れる水をただ見つめる。
胸の奥が、じんと痛んでいた。💧
さっきのクレーム対応が、どうしても頭から離れない。
事実質問を使った。
本に書いてある通りに聞いた。
なのに、相手は怒りを増し、最後には電話をガチャリと切った。
(……なんで?)😣
思わず、心の中で“なぜ”が浮かぶ。
それを打ち消すように、由美は小さく首を振った。
(違う。いつ、どこで、何が……)
だが、その問いに答えは出てこなかった。
ただ、胸の奥に残るのは、「失敗した」という
重たい感覚だけだった。😞
昼休み、由美は本を開いた。
ページの中の言葉は、昨日までより少し遠く感じる。
事実を聞けば、人は語り始める。
(語らなかったじゃない……)😔
由美は唇を噛んだ。
理論と現実のあいだに、思った以上に深い溝があることを、
初めて感じた。
家に帰ると、恒一が珍しくリビングに座っていた。
仕事でトラブルがあったらしい。
だが、由美はその空気を読むより先に、質問の型を当ててしまう。
「何時ごろ、問題が起きたの?」
「どの工程で?」
恒一は、少し苛立ったように答える。
「……いちいち、尋問みたいだな」
その言葉に、由美の胸がきゅっと縮んだ。
(尋問……?)😢
「そんなつもりじゃ……」
言いかけて、言葉が詰まる。
自分は“正しいやり方”をしているはずなのに、
なぜ、
こんなにも
距離ができるのか。
その夜、由美はベッドの中で、天井を見つめていた。
本の言葉が、頭の中で反響する。
(私は……
何を求めてたんだろう)💭
クレームを減らしたかった。
家族と穏やかに話したかった。
それなのに、気づけば「正しく質問する私」を守ることに
必死になっていた。
(本の通りにやれば、うまくいくって思ってた……)😔
涙が、静かにこぼれた。
失敗の痛みよりも、「信じていたものが揺らいだ」ことの方が、
ずっとつらかった。💔
翌日、職場でまた電話が鳴る。
由美は、受話器を取る前に、一瞬だけ目を閉じた。
(私は、相手を見てる?
それとも、本を見てる?)🤔
その問いに、答えは出なかった。
ただ、胸の奥に、かすかな不安と、そしてほんの少しの
覚悟が生まれていた。
正しいだけでは、足りない。
その現実に、由美は初めて正面からぶつかり始めていた。✨
第4章 人間関係の破綻──ノウハウを押し付け、孤立する描写
「正しさは、人を救うことも、切り離すこともできる。」
職場の空気が、少しずつ由美から離れていくのを、彼女は感じていた。😔
誰も露骨に避けるわけではない。
でも、雑談の輪に自然と入れてもらえなくなり、ランチの誘いも
減っていた。
(……気のせいかな)🤔
そう思おうとしたが、胸の奥がざわつく。
自分は、何か間違えたのだろうか。😟
ある日、同僚の佐藤が、クレームの対応に困っているのを見かけた。
声が震え、顔もこわばっている。
由美は、思わず口を出した。
「それ、なぜって聞いちゃダメだよ。
いつ、どこで、何がって聞くのが正しいの」
佐藤は、きょとんとした顔でこちらを見る。
「……え?」
「そのやり方じゃ、相手が反発するだけだよ」
自分でも驚くほど、言葉が強くなっていた。
“正しさ”を相手に押し付けるような言い方だった。😣
佐藤は、小さくうなずいたが、その目はどこか曇っていた。
その日の午後、由美は上司に呼ばれた。
「最近、周りと少しギクシャクしてるって声があるんだ」
胸が、どくんと鳴る。💓
「そんなつもりは……」
「君が悪いって話じゃない。
ただね、“正しいやり方”を押し付けられて、苦しく感じてる人も
いるみたいで」
由美は、何も言えなくなった。
(私は……
良かれと思って……)😢
その言葉が、喉の奥で詰まる。
“良かれ”が、誰かを傷つけることもある。
その現実を、初めて突きつけられた気がした。💧
家でも、同じことが起きていた。
夕食後のテーブルで、恒一がぽつりとこぼす。
「……最近さ、君と話すと、疲れる」
由美は、言葉を失った。😳
「どうして?」
「……いや、それだよ」
恒一は、少し苦笑する。
「いつも、正解が必要な質問が返ってくる。
でも、俺の気持ちは、どこにも行き場がない」
その言葉は、刃のように胸に刺さった。💔
由美は、何も言い返せなかった。
その夜、由美はソファに座り、本を閉じた。
ページの中の理論は、もう彼女を守ってくれなかった。
(私は……誰と話してたんだろう。
目の前の人?
それとも、本の中の正解?)🤯
孤独が、静かに広がっていく。
職場でも、家庭でも、自分の居場所が曖昧になっていた。
“正しい質問”を使っているはずなのに、
なぜ、こんなにも誰ともつながれないのか。😞
その答えを、由美はまだ見つけられずにいた。🌙
この記事の全文(続き)はnoteで公開しています