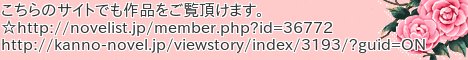☆登場人物 楊香蘭(ヤン・ヒャンラン) →イメージ女優 キム・ユジョン
15歳 宗州島で生まれ育つ。両親を亡くし、妓房の行首に引き取られ、養われる。
崔韓秀(チェ・ハンス) イメージ俳優→ チャ・ウヌ
23歳 都生まれの都育ち。名家の貴公子、哀しい過去を持つ。
第二話 花葬~かそう~
~遊女として女として。18世紀朝鮮を風のように駆け抜けた少女の生涯~
2024年夏、新シリーズ始動!
新連載 韓流時代小説
春望【春を待つ】~a certain marmeid 's love~
~朝鮮王朝期、本土から遠く離れた宗州島で繰り広げられるピュアで切なく、哀しい恋物語~
楊香蘭は15歳。6歳で両親を失い、二歳下の妹玉蘭と共に妓房に引き取られた。月日は流れ、美しい舞姫となった香蘭は、早くも男たちが水揚げさせて欲しいと殺到するほどの美少女に成長した。
香蘭には夢があった。それは、いつか相惚れとなった男に晴れて嫁ぐことだ。だが、いずれ妓生になる宿命の香蘭は、けして見てはならぬ夢であったー。
***********************************************
外は真夏のうだるような暑さで、蝉時雨がひっきりなしに聞こえている。少しは空気の入れ換えもした方が病人の身体には良いだろう。ミンサンが頷いたので、香蘭は立ち上がり、室に一つしかない両開きの窓を心もち開けた。
途端に外の新鮮な空気が流れ込んでくる。もっとも、八月初めの今は、生温かい大気だけれども。それでも、淀んだ空気よりはよほど良い。
窓からわずかに差し込む光が小卓の上の紫陽花を照らしている。ほの暗い室内の中で、花のある場所だけが光を放っているように見えた。
「タリムは香蘭のような友達がいて、幸せだった」
ミンサンが視線を室の片隅へと動かした。そこには簡易な祭壇がある。祭壇といっても、間に合わせの机に白木の位牌を乗せただけだ。その手前に線香立てがあるが、あまり線香を立てた形跡はなさそうだ。
そういえば、まだタリムに手向けの線香さえ供えていなかったー。香蘭は祭壇の前へ進み、線香に火を付けて立てた。白く細い煙が立ち上っている。
背中越しに、ミンサンの掠れ声が響いた。
「香蘭なら、この話をしてもタリムは許してくれるだろう。なぁ、タリムや」
在りし日の娘に呼びかけるような口調だ。香蘭はハッと振り向いた。ミンサンがこれから重要な話をしようとしているのが判ったからだ。
もしや、その話がタリムの自死の真相に繋がるものだとしたら。香蘭は急ぎミンサンの側に戻った。
「おじさん、話ってー」
物問いたげな眼を向ければ、ミンサンの眼からは、ひっきりなしに涙が流れていた。
駄目だ、こんなに辛い想いをしてまで、病人に話させることはできない。
「おじさん、無理に話さなくてもー」
しかし、ミンサンは強い意思を感じさせる物言いで言った。その双眸も炯々と光り、先刻までの瀕死の病人とは別人のようでさえある。
「いや、香蘭。むしろ俺はタリムのたった一人の友達だったお前に聞いて欲しいんだ」
「ー」
ここまで言われて聞かないわけにはゆかなかった。息を呑む香蘭の耳に、ミンサンの押し殺した声が響く。
「そうさな、あれは確か」
思い出すように眼を瞑り、また眼を開いて続ける。
「忘れもしねえ、六月最後の日だった。町へ用足しに出かけたタリムが夕方に戻ってきて、辛そうに厠で吐く気配がしていた」
タリムは病気だったのか? それを苦にして自害した? だが、そんなはずはないと思い直す。あんなに健康そうだった若い娘が何らかのー死を選ぶほどの重い病に取り憑かれていたとは信じがたい。
果たして、ミンサンの続く言葉は香蘭の咄嗟の考えを否定するものだった。
「俺は心配になって、厠まで様子を見にいったのさ」
ミンサンによれば、そのときは話はそれで終わったという。タリムは父を心配させまいとしてか、明るい笑顔で町の露店で買って食べた蒸し饅頭に食あたりしただけだと応えた。
が、翌日の昼下がり、隣村までタリムが用足しに出かけたのと入れ替わりに町から客があった。その客というのが、町どころか島中で名を知られた腕利きの産婆だったのだ。
「産婆?」
思わず声を上げた香蘭は、慌てて口を手のひらで押さえた。流石にここまでくれば、話の先行きは嫌でも見えてくる。
前日に厠で苦しげに吐いていたタリム。翌日、急に訪ねてきた町の産婆。
もしやー。
香蘭の予測は悪い意味で的中した。
ミンサンは振り絞るように言った。
「タリムは、娘は妊娠していたんだ」
「ーっ」
香蘭の打撃は生中ではなかった。想像していたのとそれが真実であったのだと聞いたのでは大きく違う。
「そんな、まさかタリムが」
香蘭は小さく息を吸い込み、両手で顔を覆った。熱い塊がこみ上げ、涙となって頬を濡らした。
その間もミンサンの話は続いた。
「有名な人だから、俺も名前は聞いたことはあるが、逢うのは初めてでな。産婆は五十ほどの年増だった。その人が言うには、タリムが前日、町の産婆を訪ねて診察して欲しいと頼んだそうだ」
それで妊娠が判明したのだろう。だとすれば、前日に厠で吐いていたのは、妊娠初期の悪阻だ。青海楼でも身籠もった妓生たちが悪阻で苦しげにしていたのを見たことはあった。
香蘭はかすかな希望を抱いた。
「おじさん、タリムのお腹の赤ちゃんはキョンボクさんの子どもじゃなかったの?」
けして褒められたことではないにせよ、将来を誓い合った、或いは婚約中の男女に祝言より先に子ができてしまうのは往々にしてある話だ。そういった場合、大抵は新婦のお腹が大きくなり目立つ前に、予定を早めて式を挙げるのが相場だ。
だがー。心のどこかでは違うと判っていた。もしキョンボクの子なら、世の大半のように祝言を早めれば良いだけの話だ。恐らくタリムはキョンボクではない他の男の種を宿した。
「産婆が言うには、産婆が妊娠だと告げると、タリムは堕胎して欲しいと頼み込んだ。だが、産婆は断ったと言うておったな。健康状態を知るために診察のときに色々と問診をしたら、タリムが体質的にかなり食べられん食物があると応えたそうで、強い堕胎薬を飲めば副作用が出て、生命に拘わる事態になるかもしれんと諭したそうだよ」
タリムの食物アレルギーなら、香蘭も知っていた。普通の子が食しても平気な食べ物ですら、少し口にしただけで身体中に赤い斑点が出て時には呼吸困難になりかけたこともあると話していた。
「では、子を堕ろす直接の処置をして欲しいとタリムが言うと、産婆は自分はそういう処置はしていないと応えた」