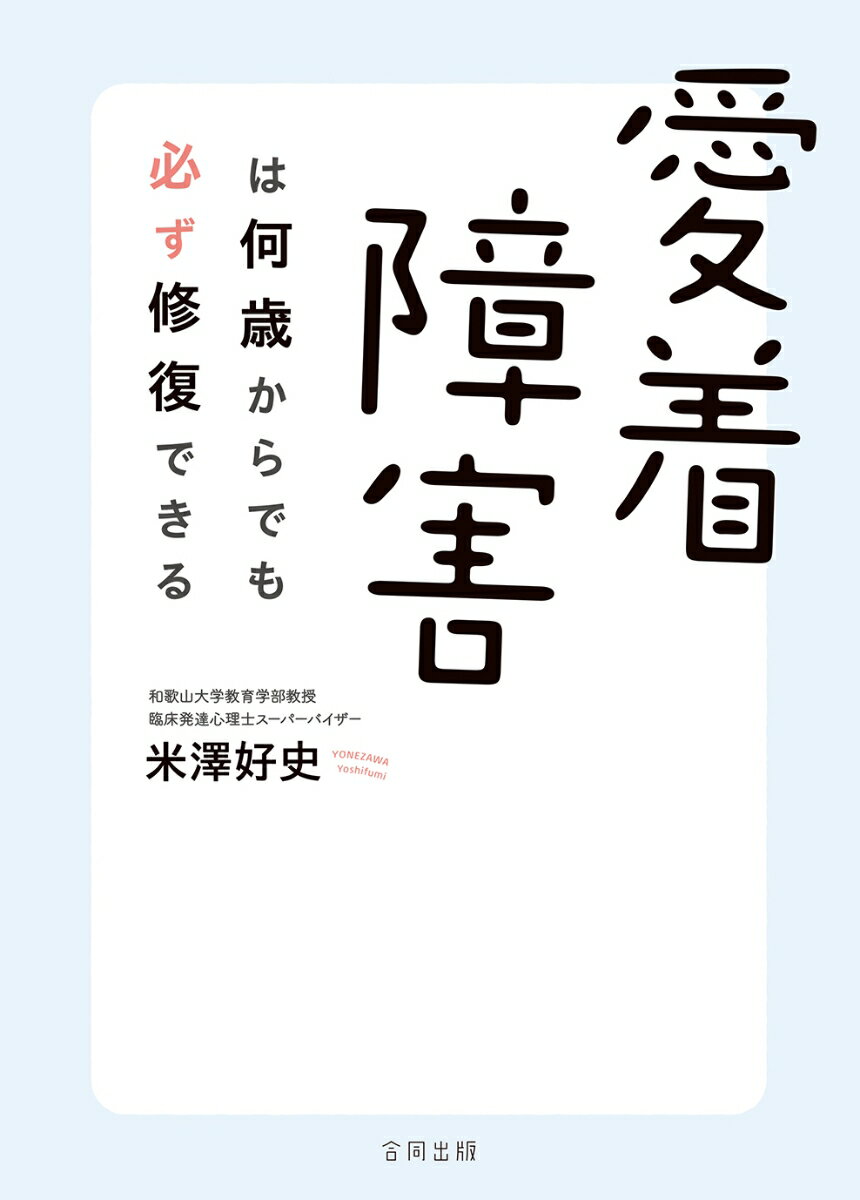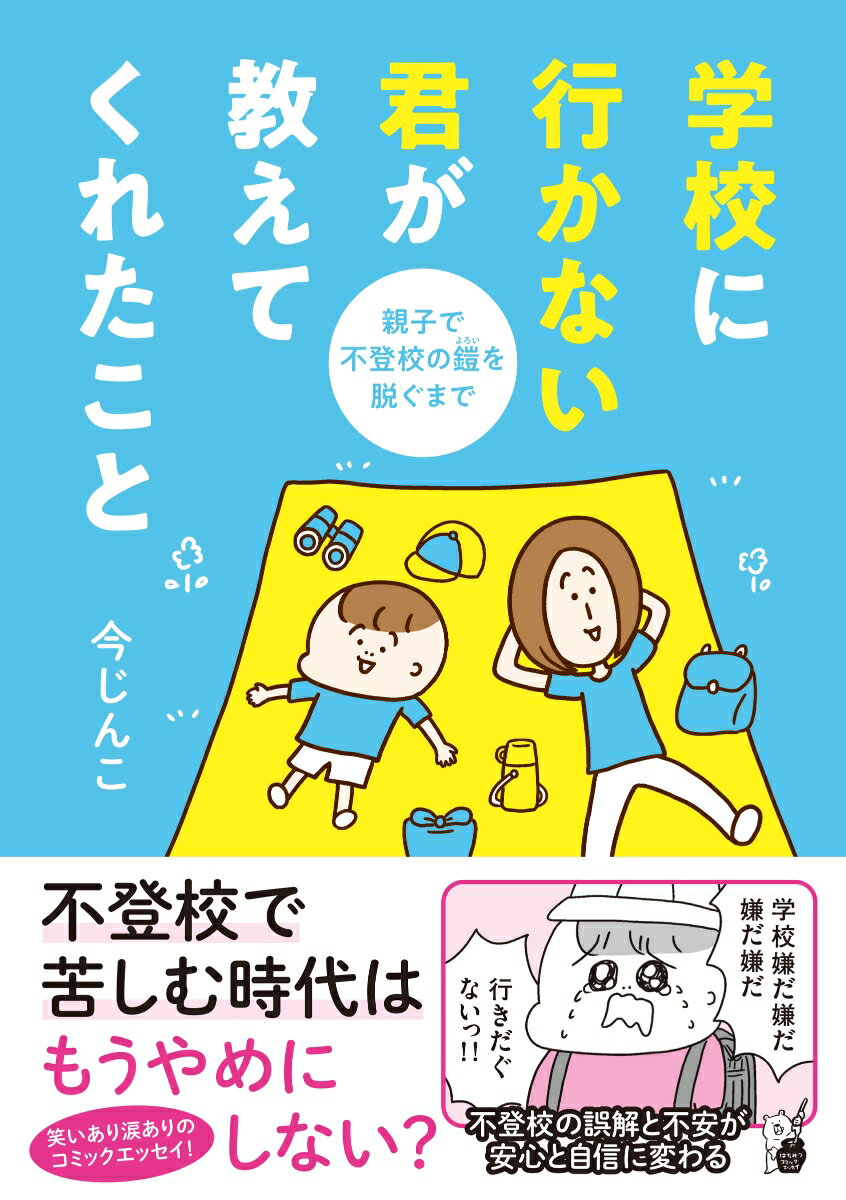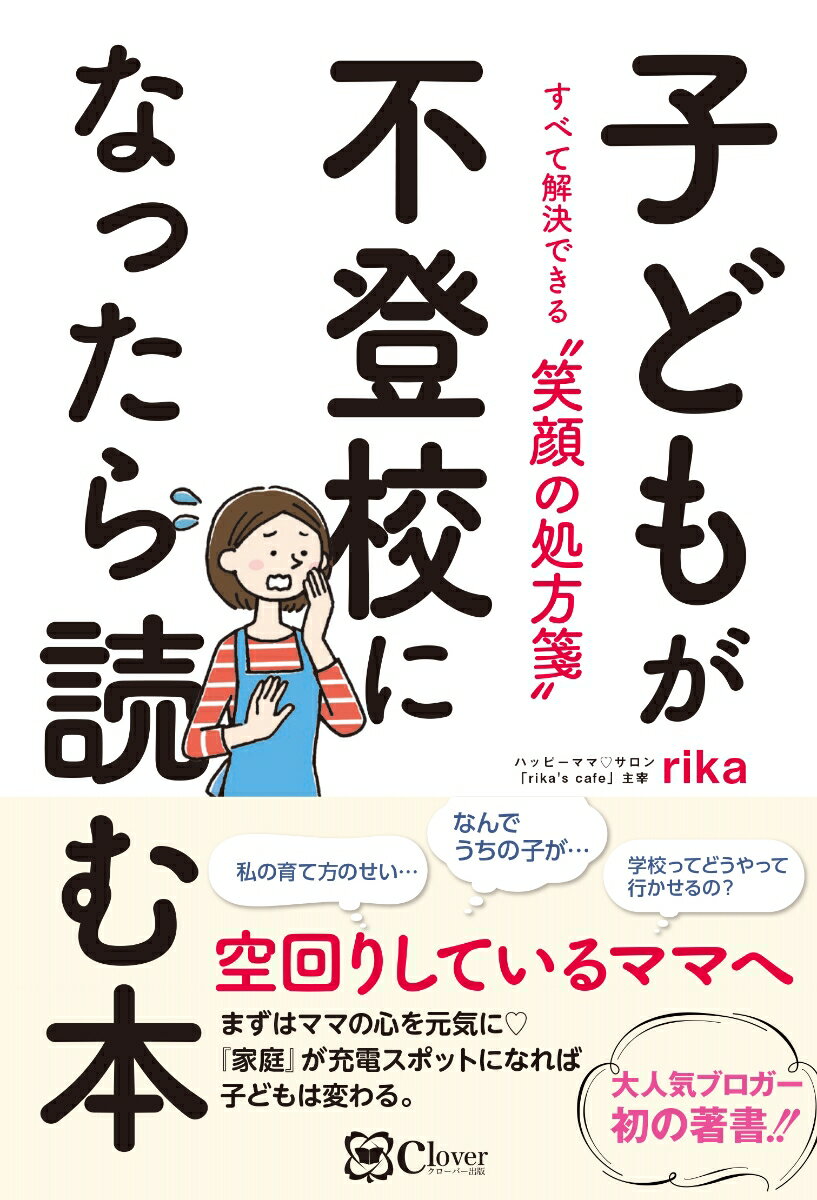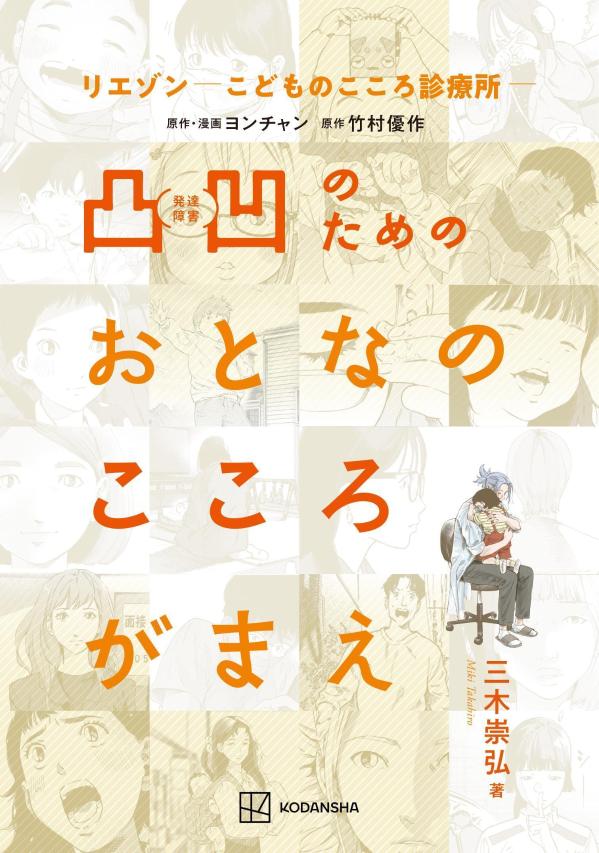ご訪問いただきありがとうございます。いいねやフォローも励みになります。
コメントもありがとうございます![]()
場面緘黙症のむすめ(4年生)は、特別支援学級に転籍してようやく居場所を見つけ本来の自分を取りもどしつつあります。話せる場所と人が増えてきました。
定型発達のむすこ(2年生)はまさに去年のむすめ状態で不登校真っ只中です。少しずつ外の世界に目が向き始めました。
わたしは『腐らない』をスローガンに日々奮闘しております。
場面緘黙症のむすめ(4年生)は、特別支援学級に転籍してようやく居場所を見つけ本来の自分を取りもどしつつあります。話せる場所と人が増えてきました。
定型発達のむすこ(2年生)はまさに去年のむすめ状態で不登校真っ只中です。少しずつ外の世界に目が向き始めました。
わたしは『腐らない』をスローガンに日々奮闘しております。
今日はケアマネとしての見地から書きます
わたしはケアマネとして介護が必要になった方の地域連携を担う仕事をしています。
この仕事をしていると色んな利用者さんや家族に出会います。
利用者さんを始め、その家族のサポートを行い、時には家庭の中まで入るのがケアマネの仕事です。
なので話しにくいお金の話や家族関係のことにも一歩踏み込んで話を聞くこともあります。
でね、必ずいます。
家庭に引きこもり(無職)の子どもを抱えた利用者さん。
俗に言う8050問題ってやつです。80代の親が50代の子どもの生活を支援しているんです。親の年金や貯蓄で子どもは生活しています。家事を担うのも親だったりします。
わたしの体感として、おそらく各ケアマネにつき数件はそういうケースを担当してるのではないでしょうか?
もちろん、もれなくわたしもそんなケースを担当してます
そういう家庭もパッと見はとても普通なので一見すると分かりません。親は必死に引きこもり(無職)の子どもを隠すので一歩踏み込まないと発見できません。
そしてそういう子どもを抱えた親(利用者)は常識的でそこそこ地位のある人だったりします。
いよいよ親も年老いてきて介護が必要になって行政(ケアマネ)とつながり、そこで引きこもり(無職)の子どもの世話をしていた事実を知るのです。
でも親が亡き後は引きこもり(無職)の子どもは自立して生きていかなければならないので、ケアマネとして見過ごすわけにもいきません。
だから就労支援を行ったり、精神疾患を疑う場合は病院受診を勧めるため、引きこもりの子どもと行政が繋がるよう支援を行います。
そしてそのほとんどが不登校の子どもなんかよりもうんと闇が深く困難事例です。
一昔前は発達障害や精神障害や不登校を隠す時代でしたからね。いかに日本が弱者に対して支援と理解の少ない国だったかが分かります。
親はまるで子どもの召使いのようです。子どもの顔色を伺いながら生活しています。
そして、そんな年老いた親達は自分の心配より、いつまで経っても50を過ぎた子どものことを心配して気を遣って生活しています。
そして決して我が子の事を悪くは言いません。ほとんどの親は『うちの子は凄く良い子だった』と言います。
もう不登校経験者の皆さんなら分かりますよね??
この闇の深さ!
過干渉な親に育てれられた『良い子』とは一体どのような子なのか。
もちろん裕福で財産のある家庭なら良いと思います。お金で解決できる事はたくさんありますから
でもそうではない一般的な家庭は本当に大変だと思います。
老後くらい心穏やかに過ごしたいですよね!!
我が家の50年後がそんなことにならないために、わたしも過干渉と心配癖を手放していこうと思います

そして不登校を選択し心を守った我が子は、きっと50年後の未来も守ったんだと思います
お読みいただきありがとうございました