肩鍵盤断裂の手術から4か月
手術した病院で リハビリを続けていますが
現在の状態は 右腕は 支えなしでは
いいときで、やっと90度くらいまで上がるくらい
普段は まだその半分くらい![]()
右手の中指、薬指、小指の腫れは
かなりよくはなったものの まだ痛みは残っていて
ぎゅっと握るには力がうまく入りません。
タオルなどを絞ることはできません。
重いもの(1キロ程度)は
手首が痛くてしっかり持てません。
しゃがんでしまうと 痛くて手が付けないので 一人で立ち上がるのに めちゃくちゃ苦労します![]()
しばらくその場で もがくことになります![]()
リハビリの先生は この手術後は
まず6か月を目標に しっかり腕が上まで上がる程度には
したいということでしたが
私の場合 介護保険を使っているため(要支援2)
手術後は 150日が限度なんだそうです。
そういうこと 知らなかった~![]()
できるだけ リハビリの予定を入れていただけるようにお願いをしてはいるのですが一週間に一度がやっとです。
となると あと 病院で受けられるのは 4,5回かな。
主治医に相談してみたけど
介護保険を辞めるか 自費リハビリしかないですとのこと![]()
あとは 自主トレと 介護保険で行っているデイケアでの
リハビリのみです。
少しずつ 筋トレも取り入れ始めていますが
上まで腕が上がるようになるには まだまだ時間がかかりそうです![]()
あと一か月
病院のリハビリも 自主トレも頑張らなくちゃ![]()
肩の手術って 時間かかるんだなぁ・・・
ネットで調べてみました。
2023.6.14
『リハビリ難民』200万人超え?原因と対策!需要高まる【自費リハビリ】
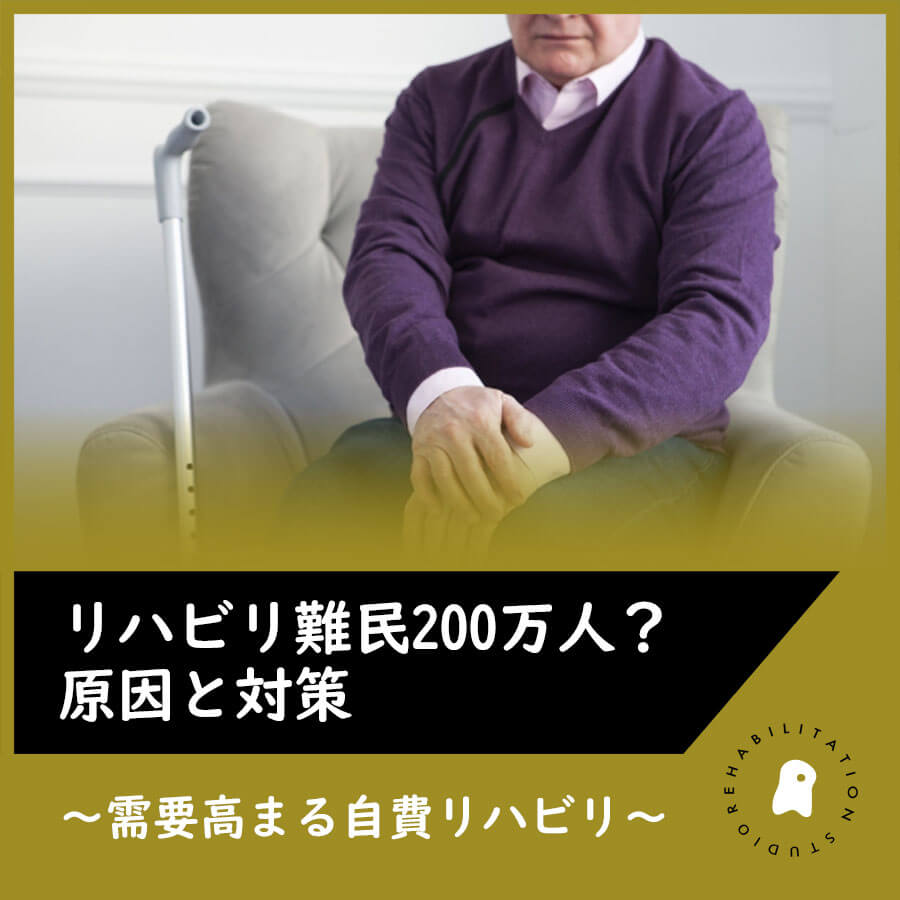
「リハビリを受けたいのに受けられない…」「リハビリ施設が少ない…」などの声を耳にし、メディアでも『リハビリ難民200万人以上』との報道がありました。
そもそも、“リハビリ難民”とは?
「リハビリ難民について詳しく知りたい!」や「もしかして、自分や家族がリハビリ難民かも…?」と気になっている、あなたのためにリハビリ難民増加の原因と今後の対策について、わかりやすくお伝えします。
—–
リハビリ難民とは:リハビリをしたくても、できない人たち
リハビリ難民増加の原因:日本の保険制度「6ヵ月の壁」
- 医療保険…日数の制限
- 介護保険…質と量の制限
リハビリ難民への対策:「自費リハビリ」という新たな選択肢のご提案
—–
この記事を通して、リハビリ難民とは何か、リハビリ難民が増えた原因と今後の対策について紹介します。ぜひ最後までお読みください。
リハビリ難民とは?
リハビリ難民とは「心とカラダが生活する上で最も適した状態になるための手段であるリハビリが、ある事情で受けられない・リハビリをしたくてもできない人たち」を表現していると考えられます。
リハビリの語源は、『ラテン語のre(再び)+hadilis(適した)すなわち「再び適した状態になること」「本来あるべき状態への回復」』
(引用:人体の構造と機能および疾病 P179~リハビリテーションの定義・目的)
リハビリとは、心と身体が生活する上で最も適した状態になるための手段を提供することを目指しています。
「難民」の言葉は様々な事情で行き場を失った人を「難民」という言葉で、比喩(ひゆ)的に表現しているようです。
リハビリ難民増加の原因!「6ヵ月の壁」?
リハビリ難民増加の原因を調べてみると、2006年の社会保険診療報酬等の改定が影響しているようです。
リハビリの在り方や施設基準が変わり、リハビリテーションの日数制限が導入されました。(日数制限については後ほど改めて説明します)
例えば、脳卒中後の機能回復は一般的に発症し1ヶ月~3ヶ月程度でスムーズまたは徐々に回復が期待されます。
約6ヵ月を過ぎると大きな変化が見られなくなる、俗にいう「6ヵ月の壁」と言われています。
6ヵ月の壁が、「長時間のリハビリは効果がない…」につながり、先述のとおり診療報酬改定でリハビリに上限期間が設けられました。
その結果、リハビリを受けたくても受けられない人たちが増加。
「リハビリ難民」という表現がメディアで取り上げられ、人々の記憶に残りました。
保険適用のリハビリは日数制限がある
先述のとおり保険適用のリハビリに日数制限が設けられました。
具体的には、下記の表のとおりです。
余談ですが、このような背景には日本の少子化拡大と超高齢化社会があげられます。
保険制度を支える労働力は減少し、健康保険や介護保険の財源不足。
保険制度そのものが危うい状態となり、医療報酬・介護報酬が削減され、結果としてリハビリ期間の制限に影響した…という見方もあるようです。
介護保険のリハビリは質と量の制限がある
公的介護保険は40歳未満対象外、また比較的軽度なリハビリが主流。
介護保険を利用するためには、申請・認定が必要になります。
認定の度合いによって受けられるサービスに違いがあり、全ての人にとって満足のいく内容とはいかず…。
また、リハビリ施設ではリハビリの専門家が不足していたり、個別の機能訓練時間が短時間だったりと、リハビリの質と量が制限されているようです。
介護保険について詳しくはこちら↓
【介護保険】とは?目的や受けられるサービス・制度のしくみを徹底解説!
リハビリによる改善の可能性が知られていない現状
前述で6ヵ月の壁について触れました。
一般的には、6ヵ月を過ぎるとリハビリによる大きな改善は見られないと言われています。
調べていくと個人差はありますが、ゼロではない・変化することは可能だという考え方もあります。
変化を期待するために大切なこととして、意味のある介入や適切な指導を受けることと同時に、
「確かな見通し」
「確かな見通しに向けて、今の課題は何か」
上記を当事者や家族、リハビリ担当者と共有することを重要視している専門家もいます。
しかし、リハビリによる改善の可能性が世の中に知られていないのが現状です。
リハビリの種類や目的について詳しくはこちら↓
【リハビリの種類と目的】高齢者が介護付き施設を選ぶコツ
医療保険?介護保険?日本の保険制度について
日本の保険制度について簡単に復習しましょう。
保険制度には医療保険と介護保険のふたつに分けられます。
医療保険と介護保険のリハビリに違いについて詳しくはこちら↓
リハビリできない?医療保険と介護保険のリハビリの違いについて
医療保険
医療保険には、公的と民間がありますが、ここでは公的な医療保険についてお話します。
- [健康保険]:会社員や公務員(それらの扶養家族含む)
- [国民健康保険]:自営業・自由業‥
- [後期高齢者医療保険制度]:75歳以上
医療保険では、 治療・訓練によってカラダの機能回復を目的として リハビリを行います。
介護保険
介護保険は、対象の年齢になると自動的に保険料が徴収される仕組みです。
40歳に達し条件が揃うと利用可能になります。
介護サービスを利用するためには、市区町村の要介護認定を申請・下記のいずれかの認定を受ける必要があります。
- [要介護]:1~5
- [要支援]:1・2
年齢や介護認定基準によって利用できる内容は変わります。
医療保険では、治療・訓練によってカラダの機能回復をリハビリの目的としているのに対し、介護保険では、日常の生活全般を捉え、生活の質(QOL:Quality of life)の維持・向上を目的としています。
介護保険の使い方について詳しくはこちら↓
介護保険制度のしくみとは?申請の流れ~使い方と利用できる3つのサービス