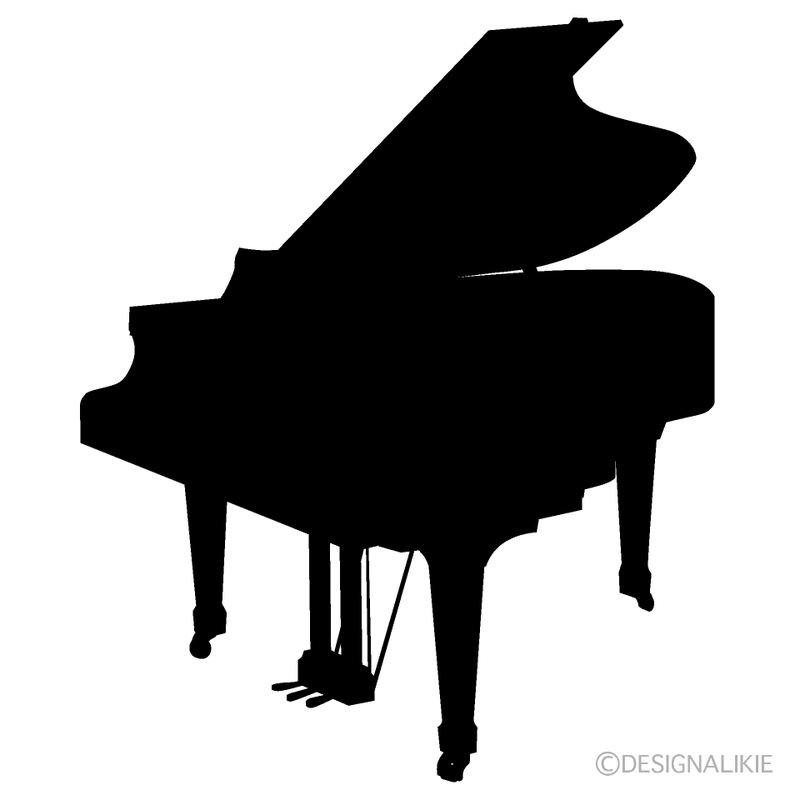(フジコ・ヘミング -- 難聴のピアニスト -- ⑩/㉒)
The winters were harsh. People caught colds that lasted until spring. Fujiko, joints stiff, woke one morning with a fever. Sneezes racked her body, but instead of loosening the congestion behind her nose, they wrung out what little strength the fever hadn’t made off with. Doctors were few and far between; antibiotics, a black market luxury. Fujiko burrowed under her blankets, soaking her bed in sweat, hoping to grind the fever down. But the heat seared her for days, and when it finally abandoned her, it took a hostage — she was deaf in the right ear.
She thought she would suffocate in grief. She played, but the music no longer swelled with the full, round richness it had before. For weeks, Fujiko squared off against the piano; funneling her senses into her fingers, probing the keys for the sound that the fever had abducted. She didn’t stop until she wrested the music back, its nuances even more lush than they had been before. She was ready.
She debuted when she was seventeen. Kreutzer arranged the program: Chopin and Rachmaninoff. Fujiko stood in the wings, battling the anxiety clawing her stomach. The audience murmured in the darkness. Crouched on the stage, the gleaming piano waited. She strode across the floor, bowed, and before the last of the applause died down, began to play.
冬は過酷で、いったん風邪を引くと春まで長びいた。ある朝フジコは目覚めると、関節が痛く、熱があった。鼻の奥のつまりは解消されないまま、くしゃみの嵐に見舞われ、発熱のさなかに残っていたわずかな体力さえも搾り取られた。医師が不足していた時代で、周囲に医者はいなかった。抗生物質は闇市で高額で取引されていた。汗でびしょ濡れになったふとんの上で毛布にくるまり、熱が下がるのをフジコは祈った。しかし、高熱が何日も体を焼き尽くして、ようやく収まった時には、命と引き換えのものを奪って行った。フジコは右の耳が聴こえなくなったのだ。
悲しみで息が詰まりそうだった。ピアノを弾いても、音は以前のようには広がらず、豊潤な響きを失っていた。何週間もピアノと向き合った。感覚を指先に集中させ、熱が奪った音を求めて鍵盤を手探りした。音を取り戻すまでやめなかった。音には以前よりも深みができた。準備は整った。
フジコは17歳でデビューした。クロイツァーが演目を決めた。ショパンとラフマニノフだった。フジコは舞台袖で出番を待つあいだ、胃を締め付ける不安と闘った。暗闇で観衆がざわついている。ステージにはきらめくピアノが佇み、フジコを待っていた。大股で歩くと、一礼して、最後の拍手が鳴りやむ前に、演奏を始めた。