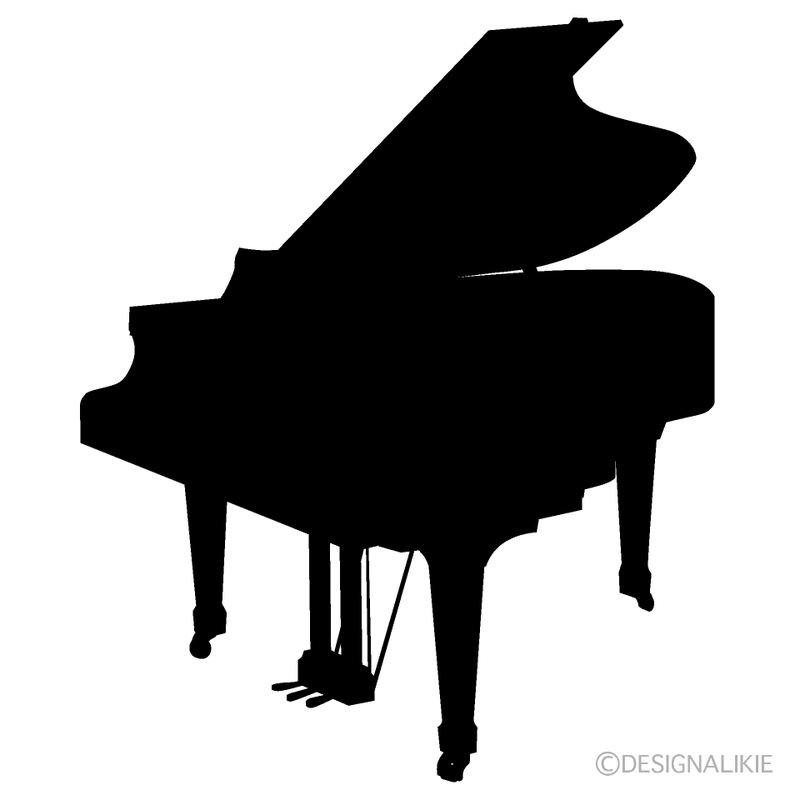(フジコ・ヘミング -- 難聴のピアニスト -- ③/㉒)
The drafty house Toako and the children lived in looked more like a barracks than a home. Her parents sent her a small allowance, but she had to teach piano to feed her children. Fujiko bore the brunt of her mother’s frustration: “Your father might have doted on you when other people were around,” Toako told her, “but you should know he never bought you a present.” Toako couldn’t address her daughter without tagging her with an epithet: “Bring me that brush off the table,” she’d say. “You mean this one?” Fujiko would ask. “No, the other one, stupid.” But there were good days, when Toako would reminisce about Berlin. Fujiko, remembering how pleasant their life had been there, vowed in her heart to return someday.
The postcards came with the kanji OH TSUKI blocked in thick strokes, the only characters Fritz knew. “I’ll send for you when I get enough money,” he had written, perhaps meaning it. One afternoon the telephone rang. Toako’s face darkened and she thrust the phone at Fujiko: “He wants to talk to you.” Fujiko held the heavy black receiver with both hands and listened to her father’s voice scratch out his love for her. “Hang up!” Toako shouted, but Fujiko didn’t stop talking until her mother yanked the phone from her fingers.
投網子と子供たちの住む家は隙間風が吹き抜け、家というよりもバラックのようだった。彼女の両親からわずかな仕送りがあったが、子供たちを食べさせるために投網子はピアノを教えねばならず、フジコは母親のフラストレーションのはけ口となることに耐えた。「おまえの父親は他人の前ではおまえを溺愛したけど、おまえにおもちゃ一つ買ってきたことなんてなかったよ」と母はフジコに言った。そして、決まって罵声を浴びせかけるのだ。「テーブルからあのブラシを取って来て」と投網子が言い、「これ?」とフジコが聞くと、「違う。別のだよ、バカ」というありさまだった。しかし、投網子がベルリンの思い出話を語るようないい日もあった。フジコはそこでの楽しかった生活を思いながら、いつか必ず戻ることを胸に誓った。
「大月」という漢字が太線で囲まれたポストカードが届くようになった。ジョスタが唯一知っていた漢字である。おそらく「十分なお金ができたら送ります」という意味のことが書かれていたのだろう。ある午後、電話が鳴った。投網子の顔が険しくなり、「おまえと話したいんだって」と言うと、電話をフジコに押し付けた。フジコは重く黒い受話器を両手で持つと、父の声が彼女への愛をせつなく語るのを聞いた。「切れ!」と投網子は叫んだが、フジコは母が彼女の指から受話器をもぎ取るまで話すのをやめなかった。