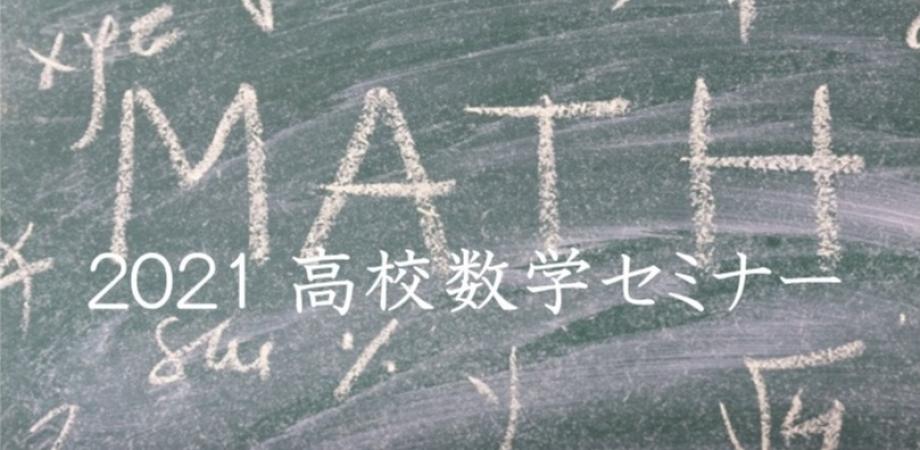いつもご覧いただき、ありがとうございます。
昨日の続きです。
昨日の研修会の後半では、大阪星光学院の教頭先生より
ご講演がありました。
生徒の「ノートのとらなさ」に危惧をされていて、
自分でじっくり考えることができない生徒が増えていることに
警鐘を鳴らしておりました。
本校の生徒もそうで、あとでiPadか何かで板書の写真を撮ればいい、
とか
教科書に書いてあるからいい、
とか
あとで自分で勉強する
とか
色々こじつけはできるのですが、書くことの目的が「自分で考えること」であることを
認識しなければ、まずいと思います。
私たちも、ただ教科書に書いていることを板書しただけであったり、
答えだけを書くように指示をしてしまうと、生徒は何のためにノートを
とるのか分かりません。
教頭先生は、「生徒に手を動かさせる重要性」を強調されていました。
オンラインの授業で明確になったのは、「一方的な授業では生徒の頭に残らない」
からどんどん参加しなくなる、ということでした。
つまり、参加型にしなければ、生徒を引きつけることは難しいのです。
その工夫の1つがアプリケーションで式や図形を触らせて動かさせることや
折り紙等のツールで手を動かして発見事項を増やすことです。
今日の空き時間では、アプリの使い方をずっと見ていました。
明日からでもできることを探して、生徒が考えるような授業を
提供できるように努力しています。