まさうさ4コマまんが♥︎わたくしのすきなもの♥フランスうさぎ
まんがデザイン無料課題*ヒマつぶしにどうぞ→
★ まんが&デザイン教室 masausa美術→
★はじめましての方はこちらから→
★はじめましての方はこちらから→★
・・・・・・・・・
昨年末のこと
カレンダーの郵送も終わって
一息ついていたら…

お客さまの
マニアなリクエストには
応えるのがモットー!!
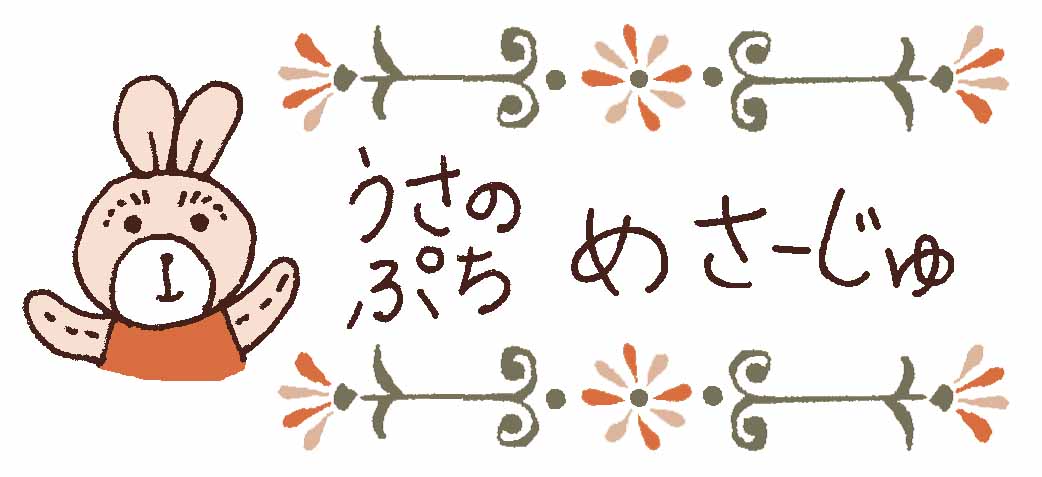
現代フランス語は
古代ラテン語から派生しているから!
そのリクエスト
受けて立ちました!

ということで
1月はこんな感じになりました

さすがラテン語
風格ありますわ!
そして
表紙はいつもながらの
フランス語

masausaカレンダー2022
古風なラテン語と
みかんな生活

愛するポテトフライ→★
蚊取り線香の危険性について→★
はじめましての方はこちらから→★

