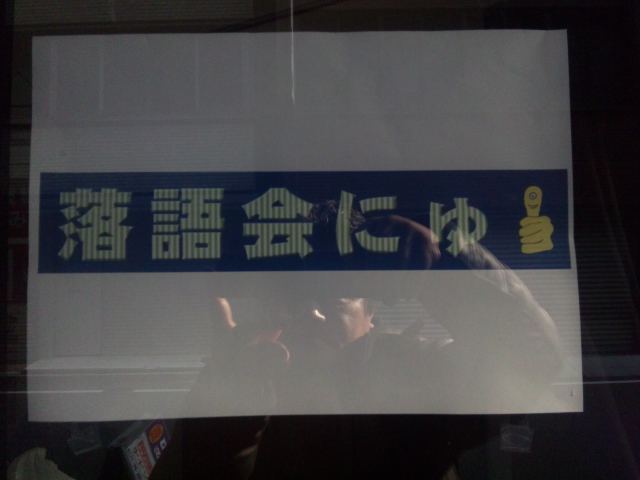
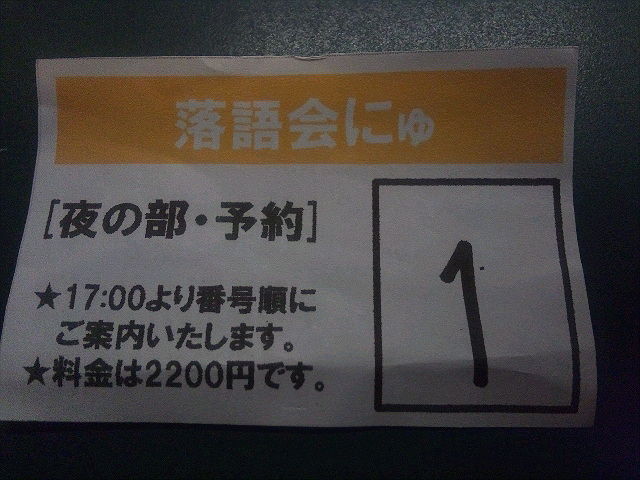
三遊亭圓丈師匠と柳家小ゑん師匠が、無限落語をリニューアルして新しい新作落語の会を立ち上げました。
その名も、落語会「にゅ」
名付け親は、圓丈師匠で、最初は落語会「の」にしようとしたらしいが、大反対されて「にゅ」に。
何なんですか?「にゅ」と周囲に訊ねられて、圓丈師匠「いゃー、なんとなく。意味は無い」と言っておりました。
そんな「にゅ」の旗揚げ公演なんで、本当なら昼夜通しにしたかったけど、昼は馬桜師匠の「圓朝座」が在ったので夜の部だけ。
圓朝座がハネた後に、黒門町から日本橋まで銀座線で移動。14:25に着いたら1番でした。
そんな落語会「にゅ」、夜の部は、こんな内容でした。
・ダブルクリック…わん丈
・オープニングトーク
・鼬の留吉…白鳥
・二月下旬…彦いち
・万歩計…圓丈
仲入り
・あの頃のエース…喬太郎
・電気系中学生日記…小ゑん
0.初めてのダブルクリック/わん丈
やっと名前を覚えました、わん丈くん。顔が犬っぽいから「ワン!」なのか?
是非、二つ目になるときは名前を国際的に「バウワウ丈」と改めて欲しい。
さて、新しい着物で登場したわん丈くん。黄土色に灰色の細い線が入っている。
本人も言ってましたが、まるで“とろろ昆布”みたいな着物でした。
しかも、前座の分際で“釈台”を置いて座ります。上方落語のケン台ではなく立派な釈台を。
何をするのか?まさか、川柳師匠を真似てアグラで落語?師匠圓丈を真似てカンニングペーパー?
違いました。これをパソコン机に見立てた新作落語を披露しました。
結構、斬新で面白い動きが入る落語で、上下の横の動きだけでなく、縱の動きがふんだんに入るのです。
わん丈くん!君は完璧に、たん丈を越えている。毎回、「にゅ」では、ネタ卸しすると言うので、楽しみにします。
早々と、正しい演目が「にゅ」のサイトにアップされていました。
1.オープニングトーク
圓丈チルドレン大集合と言う事で、会場は超満員!
白鳥さんは青森から、朝東北新幹線で移動して、師匠圓丈さんの浅草のトリを“代バネ”してからの参加!
彦いちも仙台から、喬太郎も三重県からの朝移動で秋川で「木久扇・雲助・喬太郎の会」をやっての参加でした。
昼の部は「実験落語会」、夜の部は「応用落語会」のメンバーですねと、小ゑん師匠が振ると、
池袋の文芸坐ルピリエでの「応用落語」の話題に。
最初の応用落語で、圓丈師匠が披露した根多が『臨死体験売り』
「♪りんしー♪りんしー、臨死体験はいらんかぇー、えー臨死屋でござい」と売り歩く噺。
そして、トリで登場し、その臨死体験の噺のマクラ、開口一番に圓丈師匠が言った言葉が、
「オイ!てめぇーら、応用落語だと言う前に、君たちは基礎がなっとらん!!」と、怒ったそうです。
まだ、白鳥も喬太郎も彦いちも前座で、確かに応用じゃねぇーよと思ったそうです。
でも、そんな中から圓丈チルドレンたちは、SWAへと育って行ったのです。圓丈師匠の背中を見て。新作落語中高の祖です。
2.新イタチの留吉/白鳥
圓丈作『イタチの留吉』、この噺の白鳥バージョンです。
かなりの破壊力です。なぜ、最近やらなかったのか?不思議なくらいですが、分かる気もします。
圓丈師匠のイタチは、師匠の親戚に小言幸兵衛みたいな元ヤクザの叔父さんが居て、その人を題材に作った作品なんです。
そして、白鳥さんのはと言うと親戚にヤクザも小言幸兵衛も居ないので、
似たようなキャラクターはないか?探したら居たんですねぇー亡くなった先代の志ん馬師匠が。
つまり、白鳥版『イタチの留吉』は、先の志ん馬師匠をモデルにした落語の小言幸兵衛みたいな人の噺なんです。
白鳥さんは前座時代に、志ん馬師匠から数多くの小言&説教を喰らっています。
お茶がぬるい!馬のションベンみたいな物を飲ませるな!逆に熱すぎると今度は、舌が火傷して落語ができねぇー!
また、いきなり着物を肩に掛けるな!こんな重いもんを不意に掛けたら倒れるじゃねぇーか、声を掛けてから置け!バカ野郎。
そして極めつけが、志ん馬師匠がネタ帳を見ていたら、目の悪い白鳥さんがネタ帳を踏んで破く事件があった。
その時、志ん馬師匠が言った言葉が「お前は、宮戸川か?!本が破れて読めませんでしたにして、下がるつもりか?」
古典落語を全く知らない白鳥さんが、キョトンとしていると志ん馬師匠が、更に小言を畳み掛ける!
「さては?お前、やかんだなぁ?」これを聞いた白鳥さん、「夜間じゃありません、昼です、全日の高校をちゃんと出て大学も卒業しています」と返した。
すると、烈火の如く怒った志ん馬師匠が「その夜間じゃねぇーバカ。ものを知らずに『やかん』の八公みたいに隠居にものを訊ねる野郎のこった!覚えとけ!」と言われる。
そんな古典落語を題材に小言を云い捲るイタチ亭留吉の噺で、なかなか笑えます。
ただ、少し古典落語の解釈を白鳥さんが間違ったり勘違いして応用している部分があるので、圓丈師匠や喬太郎に直して貰うと完璧です。
留吉がマクドナルドでやる『Mac調べ』や秋葉原のメイド喫茶での『居残りメイド喫茶』は白鳥さんにしかできません。
ハッピーセットのポケモンのオマケを、恐くて強いけど優しいんだぜポケモン。
そう子供に教えられて、それはポケモンじゃなくて「橘家文左衛門」じゃないのかい?!は、個人的に受けました。
3.二月下旬/彦いち
この噺は、SWAで1回聴いていますね。SWAメンバー同士が他人の根多をベースに自分テーストの噺を作る企画で。
この『二月下旬』は、喬太郎の『八月下旬』と言う噺がベースに成っていて、
原作は夏休みの宿題がテーマなんだけど、彦いちの『二月下旬』は、卒業文集がテーマに成っています。
さて、この日のマクラで、BS11の番組企画で「子供落語会」が開催されるとかで、
彦いちがサポートしている中学3年生の女子が予選を突破して本選に出ることになった。
そこで、その子から台本を書いたので直しを入れて下さい!と頼まれて、
それは『だくだく』の改作で、乙女の部屋を絵描き志望の叔父様が絵で飾り付けてくれた所へ泥棒が入る噺だった。
台本を直したら、是非、声合わせもどこかでと頼まれたから、それを渋谷の喫茶でやることに。
すると、ジロジロ周りの客が観るらしいんですよ。そうしているうちに、
女の子がいきなり落語の本息で「叔父様!私の部屋にクローゼットやベランダを絵で描いて下さい!」と喋り出すんで、益々、観られてしまう。
また、彦いちも返さないわけにはいかないので、絵描きの叔父さんで「分かった!つたない絵だが描いてやろう。」と答える。凄く恥ずかしい渋谷での公開稽古だったらしい。
さて、本題の『二月下旬』。彦いち師匠、卒業文集の噺だから、まず、自分が卒業文集に何を書いたのか?調べたそうです。
流石に覚えてませんよね、中学の卒業文集とか。そして、調べてビックリするんです。
全員で寄せ書き風に円グラフみたいな枠が与えられていて、
クラスの男子25人くらいに与えられた円の2/3ぐらいを彦いち師匠が占有して、
書いていた言葉が「テロリスト おさむ」(何か事件を起こすとやばい文集です)
そんなテロリストおさむに恐縮して、高校の卒業文集を見ると、こちらは各個人に均等な枠が与えられていて、
1ページを4分割した1コマに各自好きな事を、まぉ、だいたいが将来の夢や学園生活の思い出がビッシリ綴られていた。
そんな中の彦いちのページには、1行だけ、真ん中に大きく「天上天下唯我独尊」と書かれていたそうです。
記憶にない!
そんな事を言って本編へ。父親が30年前に出さなかった卒業文集の原稿を恩師に渡す。その旅に小学6年生の息子が同行する。
これがなかなかの珍道中でいい。電車の旅なんだけど色んな人物と触れ合う親子。
笑いのポイントは、父親が「電車の中では、子供らしく行儀よくしなさい!」と言うと、子供が「分かった、子供らしくだね」と、
いきなり初天神の金坊みたいに成って「団子買って!良い子にしてたから団子買ってくれよ!」と、叫び出すのは笑いました。
更に、昔の所謂、ニューミュージックの歌詞に準えて人生を語る中年女性が登場します。このキャラクターがまた、彦いちらしい。
で、一番笑ったのが金原亭馬遊師匠の裸に成って失敗した武勇伝でした。
また、この女が中島みゆきの歌に「私は刃物に成って貴方の中で折れたい」って歌詞があり、
人間の体内で刃物に成って折れてみたい!なんて言って、大衆の心を鷲掴みにしたのは、中島みゆきと大石内蔵助の二人だけよ!のフレーズ私は好きです。
そしてそして最後に田舎者の男性が登場し、「半蔵門線に乗って、乗り換えた記憶がないのに、今、田園都市線に成ってるのヨ!!なぜ?」も大好きです。
4.万歩計/圓丈
わん丈くんが使った釈台が再び置かれて圓丈師匠の登場。
毎度、無限落語以降おなじみの「作れるけど覚えられない」と言って、明らかにカンペが釈台に仕込まれていました。
万歩計
圓丈師匠は、4,800円もする万歩計を持っているそうです。しかも、ゴルフ仕様の万歩計。
何がゴルフ仕様かと言うと、歩幅を登録すると歩数だけでなくメートルでも歩測できる。
更に、ボタンを押すと!“ポチっ”あら不思議、さっきまでのメートル表示がヤードに早変わり。
バカ野郎ぉ~
機能はこれだけなんで、作っていた会社はつぶれて在庫が、1つ600円でバッタに売られていたから圓丈師匠、3個も買ったらしい。
今回は、そんな万歩計に纏わる噺でした。咄家というものは、弟子入りし真打に上がる前に師匠に死なれると大変辛い目に合う。
特に、入門まもない前座の時だと、それはそれは可哀想な扱いを、引き取られた一門で受ける。
「弟子にして下さい!」「一生付いて行きます!」そう誓った師匠じゃない師匠を、親代わりに敬わないといけなくなる。
だから、普段から健康管理で師匠が使っている万歩計の値が気になって…
そんな二人の弟子、一番丈と二番丈が、師匠思い過ぎて、どんどん変な方に向かう噺です。
まずまず、「覚えていない」と言いながら、できる圓丈師匠でした。ネタ卸しなら充分なデキでした。
寄席で重ねたら、面白くなる一席でした。
5.あの頃のエース/喬太郎
マクラで、三重から今日は移動でした!と言って「中尾ミエのミエじゃありませんよ。」と言う喬太郎。
らしいギャグですね。若い喬太郎ファンには、まるで通じず、ポカンとされていましたが、50才以上のファンには受けてました。
「中尾ミエ落語会」そんな仕事が在ったら、やりたいなぁーは、意味不明でしたけどね。
三重から秋川へ移動するのに、近鉄特急がいまだにタバコが吸えるのに感謝する喫煙者の喬太郎。
近鉄/宇治山田~名古屋→東海道新幹線/名古屋~新横浜→横浜線/新横浜~八王子→八高線/八王子~拝島→五日市線/拝島~秋川。
そんな鉄道マニアの小ゑん師匠や駒次くんが喜びそうな移動をして、やった仕事が「木久扇・雲助・喬太郎 三人会」
どいう視点で集めた三人なんですかね?意味不明と言うか、ギャラの予算があって、人気者を基準に適当に選んだのか?
そんな秋川で、今どきな女子中学生から「すいません、公衆電話の使い方が分からないので教えて下さい!」と言われて、
剛力彩芽みたいな可愛らしい子だったから、トキメキながら教えたそうです。嬉しかったみたいですよ、女子中学生に声掛けられて、役に立ったのが。
また、この話を楽屋でしたら小ゑん師匠が「あんちゃん、その子公衆電話を全く知らないんだから、
『ハイ、まずスカートを捲って、ブラウスのボタンを外して』と、脱がしてみたら良かったのに…」と、まるで変態オヤジ丸出しな答えに閉口したそうです。
客席も、喬太郎の暴露で小ゑんに対して「イヤー」の悲鳴が起きました。
私は、「♪公衆電話のぉーチラシを剥がしぃー」と、東京ホテトル音頭を歌いながら教えて欲しかった。
更に更に話は、秋川から神田まで電車一本で移動できるが遠い話から、二代三平夫婦のエピソードへ。この話は、藪さんのブログに書いたから割愛します。
ここから、昔のテレビの話へ。おかあさんといっしょなんて番組は、親子三代くらい見ている。
その中のショートドラマに『試し酒』を題材に作られた話が有った話をして、世代を越えて真に面白いものは伝わるって話を振ってから『あの頃のエース』へ。
三回でした私はこの噺。かなり進化しました。最初は、「道具七品/ハンカチ落とし/ウルトラマンエース」から作られた三題噺でした。
二回に、この三題噺を作った池袋演芸場の会から10日後くらいに、国立の扇辰・喬太郎の会で聴いた。
この時までは、三題噺の道具七品とハンカチ落としを生かして、噺全体のバランスが良く成っていました。
しかし、バランスが良くなった代わりに、メインテーマの「あの頃のエース」がボヤけてしまっていました。
そして、今回は大胆に構成をいじって、「あの頃のエース」が引き立つ一席に仕上がりました。
尺もちょど良くなった!また、聞きたいですね。更に良くなる予感がします。
6.ハンダの涙/小ゑん
この日の夜の部は、小ゑん師匠がトリでした。
高座に上がるなり、そんなに普通の落語会では満足できないんですか?皆さん。
そう言って、喬太郎にも困ったもんだと、公衆電話の件を軽く愚痴る。
この日の夜の部は、小ゑん師匠がトリでした。
高座に上がるなり、そんなに普通の落語会では満足できないんですか?皆さん。
そう言って、喬太郎にも困ったもんだと、公衆電話の件を軽く愚痴る。
汚らわしい事は言ってない!!
心で思っただけで、口にはしていなかったつもりなのに… と云っておりましたw
更に、会の名前が「にゅ」になった事に触れて、
前の“無限落語”も打ち上げで呑み屋を予約すると、
もう一度お願いします、と、聞き返されたけど、
今度の「にゅ」は、電話じゃ無理!メールで予約しないと…
なので、今回は“やなぎや”で予約した、と、云ってました。
そして、またまた小生が太巻糸ハンダをプレゼントした話をマクラで!!
喜んでもらえたのが、ヒシヒシと伝わって、悪い気はしません!!
また、何か素敵なエレキ系エンジニアグッズを差し入れしよう。
分かる相手にピンポイントで喜んで貰えると、プレゼントって楽しいですね。
さて、マクラは、目白小さんに入門したて、みの助だった時代の話に。
修行中は、でしゃばったまねはせず、謙虚に修行しろ!と言われたので、
まだ内弟子になって三日目、師匠の家のアンテナが突風に煽られて、
“ステー”が折れてアンテナが傾いていたそうです。
小さん師匠が「TVが映らねぇーなぁー」と、ぼやいて、電気屋に頼もうとするので、
みの助さん「師匠、私は電気屋のせがれで、父親の手伝いでアンテナ修理には慣れています、
私が見たところ、“ステー”が外れて傾いただけです、簡単に直せます!!」
すると、小さん師匠「本当かぁ? 屋根の上だぞ、高いけど大丈夫か?」と半信半疑、
「いえいえ、慣れています、簡単です、電気工事師の免許も持っています」
ここまでの会話を、遊びに来ていた現在の小はん師匠、
当時は、三木助師匠のところから移って、さん弥だった頃ですね。
そのさん弥さんが聞いていて、
「おいおい、あんちゃん!すげぇーね、ステーなんて符丁が出て、
これが本当の、ステー(師弟)関係ってか?!」とチャチャを入れたそうです。
三日目ですからねぇ、みの助さん。この一言に、
「プロは違うなぁー、笑点はやらせじゃない!本もんだぁー」
と、純粋に思ったそうです。
そんなバカ話をしていると、師匠は出掛けて、
みの助さんは、屋根に上がってサササッとアンテナを直して、
ステーも新しく張り直して、テレビも微調整しておいて、
テレビとアンテナの間の同軸もシッカリ繋ぎ直してネ。
翌日、師匠がテレビを点けて、「直った!直った!」と喜んで、
みの助さんを呼んで、「てぇーしたもんだ、手出せ」と云われて、
手を出すと、「ほら、手間だ」と、ご祝儀袋に銭を入れてくれたそうです。
それから、さん弥さん&師匠のクチコミで、みの助は電気修理ができる!
と、協会の評判になるのですが、それには理由がありまして、
小ゑん師匠;みの助が入門する前にも、秋葉原の電気屋の息子が居たんですよね。
それは、柳家小袁治師匠、当時は、柳家マコト。
このマコトさんが、電気屋のせがれったって、ただ電球を卸していた電気屋のせがれ。
だから、まったく電気工事や修理はできない。けど、電気屋の息子だからと頼まれる。
すると、このマコトさん、どんな不調の家電製品も、
「あぁ、これは接触不良ですね」と見立てるらしいのです。
お前は、二番番頭の善六さんの女房の父親か?!(長い)
ある日、師匠の家のラジオが壊れて、マコトさんが例によって「接触不良」で片付けて、
それで電気屋が呼ばれて、ラジオのある部屋に行ってみると、
単にコンセントが抜けていただけだったという。そんなマコトさんの後だから、
いろんな師匠が、これを直して、あれを直してと、みの助さんの所に相談に来たそうです。
そんな噂が、ついに立川談志の耳にも入り、みの助さん。
談志師匠の練馬の家のステレオを直しに行くことに。
スピーカーが鳴らねぇーんだ。小三治がスイッチBOXを作ってくれて、
一階のステレオを、二階でも聞けるようにしてあるんだけど、
一階は鳴るけど、二階は最近鳴らなくなったのよ。
そう言われて案内されて行ってみると、明らかに手作りのスイッチBOXがある。
中を開けてスイッチの接点とケーブルのハンダ付け状態を見た瞬間!!
みの助さんには、「あっ!これだ」と分かったそうです。
所謂、専門用語で言う “天ぷら”
つまり、天ぷらの衣のように、ハンダが接点やケーブルの芯線に馴染んでないのです。
これを業界では、“ハンダが濡れていない”と表現します。
そこで、スイッチBOXをハンダし直して修理完了です。
心の中で『小三治に勝った!』と、思ったそうです。
すると、談志師匠が お礼に何か好きなネタを言えて、後日稽古してやる。
そう言われたので、『野ざらし』をお願いします、と、『野ざらし』を習ったそうです。
その時に、入門して間もない小太郎、後の四代目・三木助が来ていて、
彼も何か好きなネタをと言われて最初『寄合酒』と言ったもんだから、
できない!と言わない談志師匠が、むきになって『寄合酒』をやる。
でも続かない、結局、ネタを変えることになって、みの助さんが小太郎に、
「『雑俳』って言え」と小声で教えて、『雑俳』に。すると…
今度は、大得意ですよ。昔、凄い勢いでやってました45分くらい。
しかも、誰もやらない『雪てん』まで全部やってましたね。
詳しくは、薮さんのブログを見てください、『雑俳』が紹介されています。
余談ですが、この“みの助・小太郎”と、談志のやりとりは録音されて、
後日、ドキュメンタリー立川談志という山本益博がレコードに収められています。
CD化されていないので、このLPは10万円以上しますね。
そんな談志師匠の想い出話から、今度は、目白の小さん師匠の想い出へ。
小さん師匠が携帯電話を初めて持たされた時のエピソードは有名ですよね。
中華料理屋で、プライベートで食事をしていて、
携帯電話が鳴って、それが馬風師匠からの電話で、
「もしもし、馬風です」と声が聞こえたら、
「おいおい、俺がここに居るってよく分かったなぁーお前、誰に聞いた!?」
と、小さん師匠は言ったそうです。
このエピソードを、最初にマクラで使ったのは小ゑん師匠だそうです。
また、補聴器の話も傑作ですね。
小さん師匠、晩年補聴器を使っていて、高座前に外して上がるんです。
すると、マイクとスピーカーが近いからハウリングを起こして“ビービー”音が出る。
電源を切らないと煩いんだけど、補聴器の電源スイッチは小さくて、
小さん師匠のマムシの頭みたいな指では押せない。
だから、普段はリモコンのスイッチで消すのです。しかし、…
この日は、目白の自宅に忘れて来て、困っている。
小ゑん師匠が、「師匠、リモコンないんですかぁー しょうがないなぁー」と、切ってやろうとすると、
「待て、家に電話して娘にリモコンで切れ!って云う」、そう言ったそうです。
そんなぁ、鉄人28号のリモコンじゃないんだから、電波届かないよ。
また、ある日、「師匠、補聴器したまま、高座に上がっていいんじゃないですか?」
って、誰かに言われて、そうだなぁー客の反応も敏感に分かるかな?
と、付けたまんま上がった事もあるそうです。
そしたら、がっかりした表情で下りてきて、「ダメだ、俺の声が煩い」だって。
そんな長い長いマクラを16分振って、『ハンダの涙』へ。
この噺は、中学生の電気オタクの少年が、憧れの彼女に、
父親から買ってもらったステレオの配線が分からないので、
家に来て、配線して欲しい!と頼まれるお話です。
実にありそうな甘酸っぱい青春の物語なんだけど、
小ゑん師匠のアキバテーストの演出で実に気持ち悪い展開です。
私は好きですけど、女性落語ファンは殆ど引いてました。
また、これでもか?!とマニアックですからねぇーーー
真空管アンプがまだ全盛で、コンポーネントステレオの走りの時代です。
「にゅ」の旗揚げ公演、どれも興味深く、素晴らしい作品ばかりでした。
最初のわん丈くんから、トリの小ゑん師匠まで大満足でした。
最初のわん丈くんから、トリの小ゑん師匠まで大満足でした。