広瀬和生さんが企画されている落語会、「この落語家を訊け!」の第六弾です。
一之輔、三三、白酒、兼好、文左衛門と続いて、喬太郎が六人目でした。
私は、兼好さんの会続いて、二回目の参加です。
この後は、柳亭市馬、立川志らくで、七回、八回が予定されております。
私も、続けて行く予定です。
一之輔、三三、白酒、兼好、文左衛門と続いて、喬太郎が六人目でした。
私は、兼好さんの会続いて、二回目の参加です。
この後は、柳亭市馬、立川志らくで、七回、八回が予定されております。
私も、続けて行く予定です。
さて、そんな「この落語家を訊け!柳家喬太郎」 こんな内容でした。
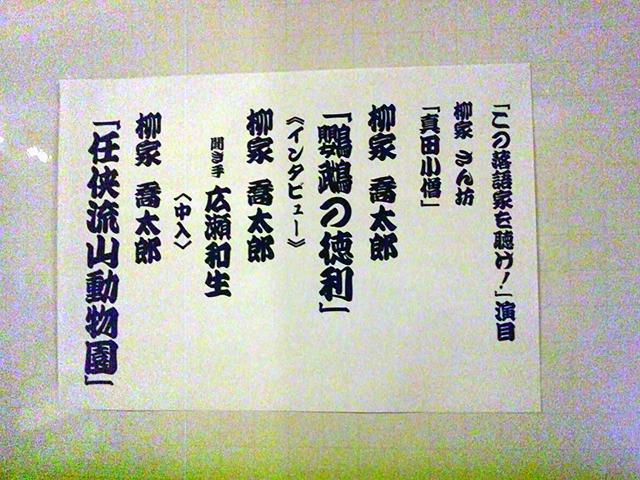
1.真田小僧/さん坊
喬太郎お気に入りのさん喬一門末っ子のさん坊くんです。
三代・さん坊として頑張っていますね。
マクラで、北海道/別海出身であることと、牛の乳搾りが得意!!
そんな話を毎回するさん坊くんなのですが、かなり上手くなりました。
そして、『真田小僧』 これも昨年5月に聴いた時より、上達しています。
これで、金坊に愛嬌が出て来ると、二つ目ですね。
真面目で一生懸命が伝わる前座さんの高座って、いいと思います。
喬太郎お気に入りのさん喬一門末っ子のさん坊くんです。
三代・さん坊として頑張っていますね。
マクラで、北海道/別海出身であることと、牛の乳搾りが得意!!
そんな話を毎回するさん坊くんなのですが、かなり上手くなりました。
そして、『真田小僧』 これも昨年5月に聴いた時より、上達しています。
これで、金坊に愛嬌が出て来ると、二つ目ですね。
真面目で一生懸命が伝わる前座さんの高座って、いいと思います。
2.鸚鵡の徳利
出囃子が、東京ホテトル音頭でした。かなり声が風邪にやられている!!
登場してマクラで、「この落語家を訊け!」という企画に触れて、
広瀬さんの風貌を、“髪の毛の短い連獅子”と表現しました。
これは、受けました。
かの恩田えり師匠は、“焼きソバみたいな髪型のお兄さん”と表現していました。
風邪で声がやられている事について、大変恐縮する喬太郎。
「こんな声だと、この落語家を訊け!!じゃなく、訊くな!!だよ」と卑下しておりました。
雪が降った話に話題を移して、新成人、成人の日の話をしました。
例年だと新成人には、あまり好感を持たなかった喬太郎師匠!!
今年の新成人は、真面目で可愛いと言うのです。理由は…
成人の日14日は、風間杜夫さんの会のゲストで横浜にぎわい座だった喬太郎。
昼の部と夜の部の合間、15時半に食事を取りに外へ出たら一面の銀世界!!
いつものラーメン屋が休んでいたので、なんと!トンカツ屋さんに入ったそうです。
そして、一番値段が高い1,600円のビーフかつ定食を注文!!
ここらで、成人式→星人式だと楽しい!!というウルトラ根多を一頻り喋って元に戻る。
喬太郎らしい展開ですね。
ガッツリ、牛のカツを堪能していると、この店の知り合いと思しき新成人の男の子が入って来て、
「足の先冷てぇー!足の先冷てぇー! お湯飲まして?」と言ったそうです。
この男の子が、お湯を飲みながら、足冷てぇー!を連呼する姿が可愛かったそうです。
更に、その子が店主と喋った後、記念写真を撮って、寒い外へ再度出る時に、
「オシャレは、寒さに勝つ!」って言ったのがまた可愛いと言う喬太郎。
勝つと、ドンカツの“カツ”を掛けたのかな?その男の子、と私は思いました。
何かを求めて来ている感じがプンプンする客席に対して、
今日はやりずらい、貴方ら、敵だよ!!と、言いながら、
まずは、『鸚鵡の徳利』に入りました。読めますか?鸚鵡:オウムです。
あるお店の主人が、録音機=レコーダーを手に入れて、
それが徳利なんですね、音を拾う徳利です。
蓋を開けて、音を聞かせると中にそれが溜まるのです。
そして、旦那から頼まれて、番頭さんが寄席に録音しに出かけるのです。
原作は、女将さんに頼まれて書生が、芝居を録音する噺なんですが、
この部分は、喬太郎が現代風に、池袋演芸場の寄席風景の録音に変えています。
喬太郎自らが、高座を下りて、袖まで下がって出囃子に乗って登場し、
それぞれの形態模写をしながら、高座に上がります。
そして、モノマネで落語を一席ダイジェストで語ります。
最初は、前座、柳家いっぽんくん。
無駄に元気な様子を元気良く演じました。
次に、二つ目。秋に真打の天どんくんでした。
やる気なさすぎ様子を上手く演じました。
さて、本格派若手真打の登場です。
入船亭扇辰さんで、お血脈を、らしくやります。
流石、同期でネタ卸しの会を一緒に続けている間柄。
更にベテラン真打の登場、ここは圓丈でした。
大笑いでした、わざわざ眼鏡して、言いそうなギャグを連発です。
この後、色物の登場。江戸曲ゴマの三升紋之助師匠。
これも似てました。あわてる仕草がそっくりです。
そして仲トリ。重鎮真打として前会長の馬風師匠が上がります。
「蛙から馬にされました」と掴みを言って、
初代三平の話を振り、正蔵&二代・三平の悪口です。
食い付の真打は、五街道雲助師匠。
誰にでもできる雲助モノマネ講座付きでした。
これが、最高!!笑いころげる。
膝代わりの色物は、お馴染み紙きりの正楽師匠。
これは、一番細部までのモノマネでした。
「ご注文は? と、言ったら、『とりあえず、ビール』って客が居ました」
これをやりました。そして、大トリの真打は!?
師匠である柳家さん喬の真似です。
流石、総領弟子です。瓜二つ。
最高に盛り上がってた、この噺のオチが仕込みオチなんですね。
一番太鼓から追い出し太鼓までを録音したけれど、
コンピュータのデータをスタックする場合と同様に、
上から順に、徳利に詰め込んだもんだから、
そのまんま出すと、一番新しい音から飛び出してしまうのです。
アセンブラのPUSH/POPの原理でして、
一旦、データを別の徳利にでも移し変えて出さないと、
聴いた順番=録音時の順番にはならないので、
いきなり、追い出し太鼓から流れてしまう。
「アッ!底に前座が詰まっていらぁ?!」がサゲになります。
3.対談/柳家喬太郎VS広瀬和生
いやはや、1時間の長い長い対談でした。
対談というより芸談。初めて落語を聴きに来た人は、
チンプンカンプンだったに違いないと思います。
いやはや、1時間の長い長い対談でした。
対談というより芸談。初めて落語を聴きに来た人は、
チンプンカンプンだったに違いないと思います。
では、私の記憶の限り紐解いてみると…
まずは、終わったばかりの一席:鸚鵡の徳利の説明から。
この噺が明治期に作られた新作であること、
そして、落語漫画の傑作「寄席芸人」で最近やられない落語として紹介されている。
これを読んだ喬太郎が、よし!復活させてみようと、
速記本を頼りに現代に蘇らせたのが『鸚鵡の徳利』なのです。
明治・大正落語集成の中に『鸚鵡の徳利』は、あるそうです。
興味のある方は原作も読んで下さい。
まだ、この日が4回目だと言ってましたが、
もっとやって欲しい一席です。寄席でもできると思います。
落語で言うと『法事の茶』みたいな噺ですね。
ただ、ご通過のみなさんには受けるが、落語初めてとかビギナーには面白さが伝わらないネ。
この咄家の出囃子と登場の仕種モノマネは、
談志、馬風、小朝なんかもやってましたね。
広瀬さんが、「仏馬」「擬宝珠」みたいに、
埋もれている噺の掘り起こしは、今後も続けるのか?と質問。
喬太郎が答えて、やるけど、その前に古典の持ちネタを増やしたり、
新作を書いたりする方を優先したい。
圓窓、歌丸みたいに集中的にライフワークにするのではなく、
衝動が湧いた時に手掛けたい、と言っておりました。
ここで『擬宝珠』を掘り起こした時のエピソードを披露しました。
橋に付いている擬宝珠を舐めたくてたまらない男の噺だが、
「フェチズム」というオタク的な人種が市民権を得る以前の社会では、
『擬宝珠』なんて落語は、客に認知されず、下らん!と、
埋もれて当然の存在だが、今日では、若い世代から支持され喜ばれる不思議な噺に成っている。
このような、時代を先取りし過ぎて埋もれてしまった噺は、
生きかえらせる事ができそうだと言う喬太郎に共感しました。
ここから、古典口調と現代話法の話に。
新作を古典口調にしたり、古典を現代話法に直すよりも、
埋もれている古典落語を掘り起こして古典のまんまやる方が、
持ちネタは増えるのかもしれないと言っておりました。
更に話は、DEEPになりました。
広瀬さんが、50歳を迎えて、どんな咄家になるのか?
50歳の談志、志ん朝、小三治は、もう大看板だったと言うのですね。
広瀬さんは名人だと思ったと言っておりました。
(私は、まだ名人じゃないだろうと思っていた)
もう、そんな年齢になったのだから、そんな芸人に成ろうとしないといけない。
それは重々認識しているからこそ、悩めると言う喬太郎。
若い時は、失敗を恐れず、何でもかんでもがむしゃらにやる。
「俺、こんな面白い事ができるんだぜ!」で良かったし、
そいう自分の若い時代の過ごし方が、自身好きだと言う喬太郎。
今の人気は、その失敗を恐れず突き進むパワーと、
失敗が糧になって育った芸だからこそなんだと言ってました。
そして、もう、そのステージからは、次のステージに登る必要があり、
そこで、悩む部分もあるし、だから、先輩や師匠の意見は素直に聞くと言う喬太郎。
でも、もう喬太郎くらいの地位になると、
だんだん周囲が批判や指導をしてくれないそうです。
人気者でもあるし、実力もそれなりにある。
「裸の王様」とまでは言わないけど、
周囲からとやかく言われなくなったのが淋しい。
しかし、しかし、それを乗り越えるのが次のステージですね。
今は、アドバイ、小言、注意が有り難いそうです。
その為にも、自分が失敗を恐れず、貪欲にやって来た事、
これをそろそろ後輩に譲り、それを見守る地位に来ているとも言っておりました。
一之輔、白酒、この世代が、30代・40代の喬太郎のように活躍してこそ、
次の時代の落語界の発展があるのだと。
広瀬さんから、一之輔・白酒じゃなく、まずは弟弟子ですね。
この言葉には、苦笑いの喬太郎でした。
話題は、少し変わって、「チケットが取れない咄家」と言われる事について、
自身も芝居の切符は苦労して取っているので、よく分かるという喬太郎。
それでも、まったく落語が注目されない時代を知っているので、
こんなバブルには騙されないぞ!とは思っているといいます。
それでも、やっぱり落語に足を運ぶ新しいファンが居るからこそ、
チケットが争奪戦になっていて、「ネットの住人」も寄席やホールへ来る。
自身も芝居の切符は苦労して取っているので、よく分かるという喬太郎。
それでも、まったく落語が注目されない時代を知っているので、
こんなバブルには騙されないぞ!とは思っているといいます。
それでも、やっぱり落語に足を運ぶ新しいファンが居るからこそ、
チケットが争奪戦になっていて、「ネットの住人」も寄席やホールへ来る。
最初は、ネットの書き込みに一喜一憂していたが…
今は、全然見ないという喬太郎。
批判や悪口もナーバスになるが、それより褒められて喜ぶ自分も居て、
それが、どーも芸にいい方には影響していないように思うと言う。
また、かなり不条理な批判もある。(広瀬さんが語る)
『カマ手本忠臣蔵』ですよ、と、ネタ出ししての会なのに、
会を観た感想に、『文七元結』が観たかったなんて書く客も。
もう、こうなると何が言いたいやら??? 閉口して当然ですね。
そんなこんなで、喬太郎はネットの書き込みは見ないらしい。
一方で、ライヴ芸なんでハズレに当たる場合がある。
これは、落語に限ったことではないけど、芝居のお客さんは、
「金返せぇー」までは言わないで、大人の対応が多いが、落語は…
確かに、私も反省するが、酷いとボロカスに書く場合がある。
天どん、喬四郎、キウイに対して、散々酷評したなぁー
更に、落語コンテンツの話、DVD/CD/本なんて儲からない!!
と、広瀬さんが言うと、喬太郎が「そんな事言って沢山書いてますよね」
喬太郎らしい切り替えしで笑いに。ナイス!!
また、人気ランキングは迷惑じゃなかったか?と広瀬さん。
落語の世界は、ランキングなんてやらない。
悪気は勿論なく、小学館はランキングを付けたけど、
やっぱり、1位に選ばれると、かなりプレッシャーだったようです。
特に、師匠さん喬よりランキングが上で、
談志、小三治・志の輔を差し置いての一位ですからね。
と、広瀬さんが言うと、喬太郎が「そんな事言って沢山書いてますよね」
喬太郎らしい切り替えしで笑いに。ナイス!!
また、人気ランキングは迷惑じゃなかったか?と広瀬さん。
落語の世界は、ランキングなんてやらない。
悪気は勿論なく、小学館はランキングを付けたけど、
やっぱり、1位に選ばれると、かなりプレッシャーだったようです。
特に、師匠さん喬よりランキングが上で、
談志、小三治・志の輔を差し置いての一位ですからね。
音楽の世界などでは当たり前のランキング。
あまり落語には定着しませんでしたね。
でも、喬太郎は仲間が気遣ってくれたのが嬉しかったと言ってました。
談志師匠が晩年本で使ったフレーズ。
「古典落語は、江戸の風が吹くかないといけない」に触れました。
広瀬さんは、それはどうでもいいと言いますが、
私は、吹かないと古典落語じゃないと思います。
決め式、様式美でこその古典落語だと思うし、
基本的に“保守”“本流”だと思います。
お前は、自民党か?!って言われそうですけどね。
そして、喬太郎自身の古典落語にはあまり江戸の風が吹いていない、
そう本人も理解しているし、師匠さん喬さんも、もう少しなんとかならんか?
と、言うそうです。俺もそう思います。
腹黒くズル賢い白酒や一之輔は、それなりに吹かせますよね、江戸の風。
落語という様式を借りて、自分の伝えたい事を客に伝える能力。
これ一点で言うと、三遊亭白鳥は、将来の名人です。
この話も盛り上がりました。確かにそうです。
あんな変ちくりんな話を、客に理解させるんですから!!
広瀬さんが、「白鳥さんの落語会に行くと言って、恥ずかしくなくなりました」
と言い、これは受けましたね。確かに昔は奇人変人扱いでしたから。
時代が、白鳥に追いついたとも言えます。
最後に、喬四郎を叩き直す!宣言が出て、
落語カフェで三月から二人会を八月までやるそうです。
二席づつやり、「喬四郎短気集中高座」と銘打つらしい。
落語カフェで三月から二人会を八月までやるそうです。
二席づつやり、「喬四郎短気集中高座」と銘打つらしい。
4.任侠流山動物園
三遊亭白鳥作のシリーズものです。第一作目ですね。
ブタの豚次が活躍するお話で、喬太郎が今楽しくやれる一席なんだとか。
喬太郎で聴くのは、去年の5月の恵比寿以来です。
この日は、非常にテンポも良かったですね、25分くらいでした。
いつもより、5分くらい詰まっていて良かったです。
対談と落語二席、非常に良い会だったと思います。