見たい見たい、と思いつつナチスドイツがテーマということで迷っているうちに上映終了。
今年の夏、ブックオフで原作を見つけ、ようやく昨日今日で読了した次第。
実に淡々とした文章で、私はドイツ文学はほとんど読んだことはないけれども
ドイツの友人たちの表情が思い浮かぶような、いかにもドイツ人的な文体で翻訳されていました。
なんとなく記憶に残っているのか、もしかしてベルリンの話?と思いつつ読み進めていましたが
やはり東西ベルリンの時代のお話(おそらく1960年代半ばころ)でした。
描かれているアパートの様子、シュトラーゼの様子、そういったものがありありと浮かんで来たこと、
そして何よりも、無駄のない文章にもかかわらず、心をえぐるような言葉の数々にあっという間に
引き込まれてしまいました。
15歳で21歳年上の女性と知り合って恋に落ちる。
彼女が突然姿を消すまでのことが第1章には描かれています。
文字にするとかなりセンセーショナルではあるけれども、冷静な文章で描写されたいくつもの
エピソードは、実際には何も特異なことを感じさせません。自然です。
いつも彼女は彼に本を読むことをせがみ、彼は朗読しつづけます。
でもある日彼女は突然姿を消してしまう。
その理由。後に間違いであることがわかりますが、このくだりにまずやられてしまいました。
愛情がありながらも、彼女の存在を誰にも明かさない。
明かすことができなかったことが、彼の考える彼女への裏切り行為だという。
そうだろうな、と思います。
誰にも明かせないということはどこかに良心の呵責なり、恥じいる気持ちが存在することだから。
愛情とは別に存在する、客観的評価なわけだから。
そういった感情は存在してほしくはないけれども、存在する可能性は否定できない。
彼はそれを彼女が感じ取ってしまったと思い込み、彼女を失った後も長いこと悩みます。
第2章 法学部の学生となった主人公が、ゼミの課題で強制収容所に関する裁判を傍聴し、
そこで戦犯として裁かれようとしている彼女に出会います。
そしてはじめて彼女が文盲であったことを知ります。
第1章の彼女とのいくつかのエピソードの中で、本を読むことをせがまれたことをはじめとして
当時の彼にとって理解しがたかった彼女のいくつかの言動の意味がここでようやく解明されます。
裁判を熱心に傍聴する彼。その存在に一度は気づきながらも、結審まで二度とこちらを
見なかった彼女。
最後まで文盲であることを明かさずにいたために、彼女は無期懲役の判決を受けます。
主人公の苦しみも悲しみも人ごとのように、やはり淡々とした文章で綴られて2章も終わり。
第3章 もっとずっと後のこと。
主人公は司法試験に合格し、結婚。子供を儲け、やがて離婚。
ある時彼は彼女に昔読んであげた本を取り出します。
そしてその朗読を録音したテープを彼女に、以後8年間に渡って送り続けます。
恩赦を受けて18年ぶりに出所できることになってはじめて彼は彼女に会いに行きます。
彼女のための働き口も見つけ、住まいも探しておいたのですが・・・・。
でもこの結末は語らずにおきますね。
悲しいとか辛いとか、そういう言葉では語れない想いといえば良いのか・・・
なんとも表現しがたい読後感です。
21歳年上の女性との恋愛というのもテーマのひとつ・・・それは多分、道徳的あるいは
宗教的な罪なのかなと思いますが、それとは別に、あとがきに書かれていた
「あなたの愛した人が戦争犯罪者だったらどうしますか?」というテーマをやはり私は
考えずにはいられない。
作品の中でも、何度も彼は悩みます。
ナチスの党員として強制収容所の看守をしていた彼女の過去を知らずとはいえ、
愛していた自分もまた罪人なのか・・・・と。
この感覚は、多分私以外の多くの日本人にも理解しがたい感情ではないかと思います。
宗教観?国民性?歴史教育?いったい何によるものなのでしょうか。
たとえば、もう今更だから構わないと思いますが、私の祖父は県議などを
務めていたものの戦後はC級戦犯として公職を追われてしまいました。
だからといって私はまったく祖父を断罪する気にはなれないのです。
あの時代は時代なりの事情があったと思うし、むしろ庇いたい気持ちになる。
何についても両面があるわけで、先日のノーベル平和賞の授賞式に出席できなかった
中国の受賞者(名前は不明です。ごめんなさい。)は、本国では罪人です。
戦争を肯定する気は毛頭ないけれども、仕方ないのかなと思ってしまうわけ。
スペインで知り合ったドイツの友人たちの中にはずっと私より若い子達もかなりいたけれど
誰もがナチスドイツという負債を背負わされ、傷ついて、それでも真摯に過去と
対峙していたように見えました。
それは隣接しながら分断されてしまって国交のない、もうひとつのドイツが身近にあったことも
大きいのかもしれないけれど、私にとってはああやって今もなお(といっても20年前になるよ)
戦争を知らない世代までもがその負債を引きずっていることが大変な衝撃でした。
今回この本を読むことで、その理解に近づいたとはとても言いがたいけれど
誤解を恐れずに言えば、自虐とナルシスティックな意識も内包しているような気が何となくあります。
この印象は主人公のレポート的な冷静な文章によるものとは思います。
いや、冷静というよりも、むしろ冷たいんじゃ?と私は実のところ思っています。
歴史や彼女に対して、真剣に向き合おうとしつつも、15歳のころから常に何となく逃げ腰なところが
同時にあるような印象を受けているからこそだろうとは思うのですが、どうなんだろう・・・。
あくまでも、ある男性側の視点から書かれたドイツの傷跡。
女性側から書かれたらまた異なった印象だったとは思うけど、いずれにせよ小説に過ぎません。
これでドイツを判断することなどもちろんできない。
ただエピソード的に出てくる彼女の描写の様子から、共感とは異なるけれども
ドイツ女性の強く、質実剛健的な意識に惹かれるものはありました。
泣き叫ぶか弱い女性ではないところ。
友人たちも皆、意思が強く弱音を吐かない、やさしい素敵な子達でした。
先にも書いたようにいくつもの心にせまる言葉や文章がありました。
涙流しながら読んだ本なんて久しぶりです。
今年のナンバー1はアラン・シリトーの「長距離走者の孤独」だと思っていたけど、
もしかしたら入れ替わるかも。どちらも再読の要ありかな。
機会がありましたらぜひ。
朗読者 (新潮文庫)/ベルンハルト シュリンク

¥540
Amazon.co.jp
愛を読むひと (完全無修正版) 〔初回限定:美麗スリーブケース付〕 [DVD]/ケイト・ウィンスレット,レイフ・ファインズ,デヴィッド・クロス
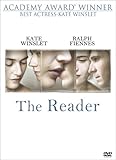
¥3,990
Amazon.co.jp