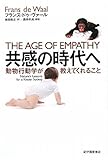
¥2,310
Amazon.co.jp
「自然は生存のための闘争に基づいているから
私たちも闘争に基づいて生きる必要があるなどと言う人は、
誰であろうと信じてはいけない。」
という言葉に共感できる人にとっては、
その名の通り共感に満ちた内容となる本書。
「あくびも種の壁を越えて伝染する」とか、
「ミラーニューロンは自他の境界を消し去る」とか、
興味深い内容がポロポロとあっておもしろい。
資本主義の構造が人間を幸せにしないことが明らかになったいま、
人との絆の重要性を「ヒトという種」の視点から唱えるこの本は、
これから注目されてしかるべき。決して叱るべきではない。
【引用メモ】
人は配偶者を失うと絶望し、生きる意欲が萎えることが多い。
残された配偶者が交通事故やアルコール濫用、
心臓病、癌で命を落とすのは、そのためかもしれない。
配偶者を失った人は、その後の半年間、死亡率が高くなる。(p21-22)
私たちは恐ろしいまでに集団性の動物だ。
政治指導者は群衆心理の扱いに長けているから、
人々が大挙して彼らに付き従い、
狂気の企てに乗り出した例は、過去、無数にある。
指導者は外からの脅威をでっち上げ、恐れをかき立てるだけでいい。
すると、あとは人間の集団本能が引き受けてくれる。(p38)
私たちの祖先は資源が乏しく、
集団どうしで依存し合っていたので、
大規模な戦争を始めたのは、
定住して農業によって富を蓄積しだしてからだった。
その富のおかげで、他の集団を攻撃することのメリットが増えた。
戦争は攻撃的な衝動の産物というより、
権力と利益の追求にかかわるものに見える。
これはもちろん、戦争が不可避ではないことも意味する。
私たちの祖先を獰猛で恐れ知らずで自由な人間として描く、
欧米における人類の起源の物語は、このように神話にすぎない。(p43)
たいていのアメリカの家庭と、
どのホテルの部屋にもある本(聖書)は、
ほとんどどのページでも私たちに
思いやりを示すようにとしきりに促すのに、
社会ダーウィン主義者は、そのような気持ちを嘲る。
自然がしかるべき過程をたどるのを妨げるだけだというのだ。
彼らは、貧しさは怠惰の証、社会的公正は弱点として切り捨てる。
貧しいものはただ滅ぶにまかせればよいではないか、と。
なぜキリスト教徒がはなはだしい矛盾に苛まれることなく、
そのように無慈悲なイデオロギーを信奉できるのか、
私には理解できないが、現に多くの人が
それを受け入れているようだ。(p47)
アメリカは利潤原理に頼ったために悲惨な状況に陥り、
医療の面では今や先進国中、断然最下位だ。(p59)
著名な経済学者ミルトン・フリードマンは、次のように主張している。
「企業重役が株主のためにできるだけ多くの
お金を稼ぐ以外の社会的義務を負うことほど、
私たちの自由な社会の土台をはなはだしく
損なう傾向は、他にほとんどない」。
フリードマンはこのように、人々をいちばん
後回しにするイデオロギーを私たちに提供した。(p59)
共感は「他者の自己」に直結する経路を提供してくれる。(p97)
あらかじめ急ぐように言われていた学生は、
時間に余裕があった学生よりも、手助けする率が低かった。(p130)
空港で誰かが搭乗券を落とせば教えてあげる。
注意する側はほとんど労力を費やさないが、
相手にとっては大きな痛手を未然に防いでいる。(p159)
所得格差が大きい州ほど死亡率が高い。
イギリスの疫学者で健康問題の専門家リチャード・ウィルキンソンは、
最初にこの統計をまとめた人物で、その結果をひと言で言い表した。
曰く「格差は人を殺す」。(p279)
見ず知らずの人の命は無価値と見なされることが多い。
なぜイラク戦争で亡くなった一般市民の数について
語らないのかと訊かれたアメリカの
ドナルド・ラムズフェルド国防長官(当時)はこう答えた。
「よその人たちの死者は数えないから」(p287)
利己的な動機と市場の力だけに基づいた社会は
富を生むかもしれないが、人生を価値あるものにする
まとまりや相互信頼は生み出せない。
だからこそ、幸せの度合いを調べると、
最も豊かな国々ではなく、国民の間の信頼感が最も高い国で、
最高のレベルが記録されるのだ。(p311)
満足度
★★★☆☆