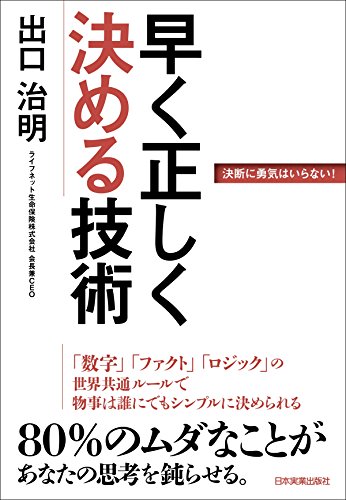先日の伊藤健太さんをお招きしてのWEBセミナーは多数ご参加いただきありがとうございました。
①問題設定を変える、②PV×CVRという話は、聞けば当たり前の話なんですが、
日々の業務の中ではついついおろそかにしがちな基本中の基本だと思うので、参加された方には思考の整理のいい機会になったのではないでしょうか。
セミナーでも紹介したこの本も是非読んでみてください。
そんなこんなで、ゴールデンウィークも終わりで、いよいよ今年も中盤戦ですね、と言いたいところですが、
緊急事態宣言延長され、各自治体での出口戦略策定という、またまた新たな未知のフェーズへ突入することになりましたね。
個人的には、出口戦略を示すことは、希望を与える効果よりも、むしろ緩んでしまって、5月末にまた感染爆発するリスクがかなりあるんじゃないかと懸念しています。
まあ、そういうことが書きたいわけではなくて、今日はこういった不確実な状況の中での意思決定という問題について少し書きたいと思います。
将棋の羽生さんが、最近(といってもここ10年ぐらいですが)、直感の重要性みたいな話をよくされるようになっています。
実は、経営においても、将来の見通しが不確実な局面(まさに今ですよね)においては「直感」を大切にすべき、というセオリーがあるんです。
今日はそれをちょこっと解説したいと思います。
そもそも、意思決定の判断ミスについては、予測エラー度=認知バイアス×ヴァライアンス×ランダムエラー
という定式があります。
認知バイアスは先日話しましたが、要するに「人間は見たいものしかみない」という習性だと覆ってもらえばいいです。
ヴァライアンスという言葉はあんまり聞いたことがないかもしれませんが、これは要するに、
「収集してきた情報が実は使いものにならない」という確率だと思ってください。
たとえは、一生懸命、飲食店の売上分析して事業計画立てても、今回のように宴会の自粛が計算にはいらないと、分析として意味がないですよね。前提が変わってしまっているからです。
そして、現在のように、先の見通しが立てにくい状況ほど、このヴァライアンスが増えるのです。
つまり、認知バイアスを避けるために、様々な情報を収集分析したら、逆に使えない情報も入ってきてヴァライアンスがあがる、というジレンマが発生するわけです。
そこで、重宝されるのは直感です。直感での判断は、基礎となる情報が少ないために認知バイアスは避けられませんが、ヴァライアンスがあがるというメリットがあります。
そうすると、将来不確実な状態においては、変に判断材料を集めるよりも、直感で判断したほうがいい結果を産むほうが多いということが有り得るのです。
もちろんこれは、危機においてはただ直感を頼れ、という防災でんでんこみたいな話ではなく、
長年の経験があり、最低限の認知バイアスの歪みは自分の中で正せるという方については、ヴァライアンスの危険を避けるために直感で破断したほうが良い結果になりやすい、という程度の話でしかありません。
よく、結構ベテランの、今までバブルやらリーマンショックやらの数々の修羅場を乗り越えてこられた経営者の方に、この「直感派」の方の割合が高かったりするので、
危機時にメンター的先輩に話を聞いて、
若手のベンチャー経営者が、「やっぱり最後は直感なのか」という風に考えるようになる、という流れがあったりしますが、
この直感派の理論的基礎を理解していれば、若手のベンチャー経営者のような、認知バイアス入りまくりの人には、直感判断はお勧めでないことがわかると思います。
直感判断はあくまでも認知バイアスよりもヴァライアンスを恐れるようなベテラン経営者だからこそ正当化できるのです。いわば「玄人の勘」だからこそ意味があるのです。「素人の思い付き」ではだめなのです。
意思決定については近年色んな研究が進んでいるので、是非これを機に勉強してみてください。