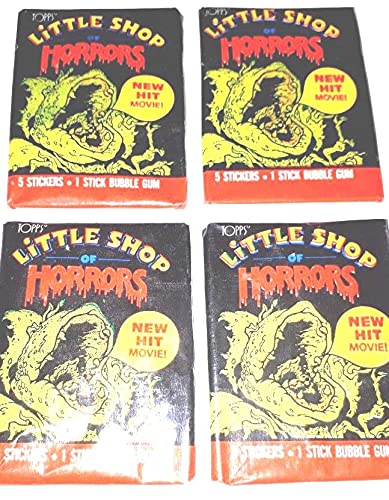映画『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』(1960年)は、のちに1986年のミュージカル映画版が大成功を収めたことで広く知られるようになりましたが、そもそもの原点はこの1960年のモノクロ映画にあります。
監督は低予算映画の名手ロジャー・コーマン。わずか2日間という超短期間で撮影されたにもかかわらず、カルト的人気を博し、後年にまで語り継がれる独特な存在感を放っています。
舞台は、ロサンゼルスのダウンタウンにある小さな花屋。店主ムシニックの下で働く、ややドジで頼りない青年シーモアが物語の主人公です。
彼は同僚のオードリーに恋心を抱いているものの、気の弱さから気持ちを伝えられずにいます。
そんな彼の人生が一変するのは、ある日、彼が育てていた不思議な植物が急成長を遂げたことからです。その植物にはどうも奇妙な力があり、実は「人間の血」を餌にして成長する肉食植物だったのです。
シーモアは偶然その事実を知り、最初は自分の指から出る少量の血を与えていましたが、やがて植物はどんどん大きくなり、血の量も増えることを求めるようになります。
やがて花屋の注目を集めた巨大植物のおかげで店は繁盛し始め、シーモアの存在も街の人々に知られるようになります。しかしそれは同時に、恐ろしい歯車が回り出す瞬間でもありました…。
1960年版『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』は、低予算ゆえの素朴さが逆に魅力となっている作品です。
植物の造形は現在の視点から見るとチープではありますが、その雑然とした質感がかえって不気味さを醸し出しています。
さらに、時折ブラックコメディ的な要素が織り交ぜられており、恐怖と笑いの間を行き来する奇妙な空気感があります。そのバランス感覚こそがこの映画の持ち味であり、ただのホラーではなく、どこか風刺劇のような印象も与えます。
また、この映画で有名なのは、若き日のジャック・ニコルソンが登場していることです。彼が演じているのは、歯科医のもとを訪れる患者で、痛みを楽しむという変わった嗜好を持つ青年の役。登場時間は短いながら、その異様な存在感と強烈なキャラクター造形は観客の記憶に残り、映画史における小さな名場面として語り継がれています。
感想
この映画を観ると「映画ってアイディアと勢いがあれば成立するのだな」と改めて感じさせられます。
正直、映像の豪華さや効果の完成度という点では決して優れているとは言えません。
むしろ家具のような硬さで動く植物や、どこかマヌケな登場人物たちに笑ってしまう瞬間の方が多いでしょう。
しかし、それでも物語が持つ毒っ気や風刺は色あせていません。小さな成功や繁栄に目が眩んだ人間が、より大きな代償を払う羽目になる。
そんな寓話性はシンプルながらも普遍的で、今の時代でも十分に通じるテーマです。
また、シーモアという主人公像も少し考えさせられます。彼は善人で臆病者ですが、ただ「いい人」で終わらないのは、自分の夢や欲望のために知らず知らずのうちに取り返しのつかないことをしてしまうからです。
彼は積極的に悪事を企てるわけではありませんが、結果的に人を犠牲にしていく。その曖昧さが物語に妙なリアリティを与えており、単純な勧善懲悪のストーリーではない奥行きを作り出しています。
怖さのレベルについて言えば、現代のホラー映画を基準にするとそれほど恐ろしいものではありません。むしろ「奇妙で風変わりなコメディ」として楽しむ方が適切だと思います。
ですが、植物が成長していく過程で「もっと血を!」とねだるシーンには、不気味さとシュールなユーモアが絶妙に同居していて、この映画をただの珍品に終わらせない魅力があります。
最終的に、1960年版『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』は、映画史の傍流にひっそりと残っていながらも、その後の音楽劇やリメイク版を通じて、文化的に大きな波及効果を持った作品といえるでしょう。
低予算で撮りっぱなしの奇作が、のちのミュージカル映画や舞台を通じて世界的に親しまれるようになる。その背景を知ったうえで1960年版を観ると、映画の持つ不思議な生命力を感じられます。大作とは違う意味で、映画という表現の柔軟さや、観客を惹きつける何かを確かに備えているのです。
『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』は、正統派のホラーを期待すると肩透かしかもしれませんが、映画史の裏側を彩る“奇妙な花”のような作品です。
観ている間はどこか場末の空気に引き込まれ、シーモアの頼りない笑顔や妙に生き生きとした植物の姿に愛嬌すら感じてしまう。不完全だからこそ残る余韻。それがこの映画の隠れた魅力なのだと思います。