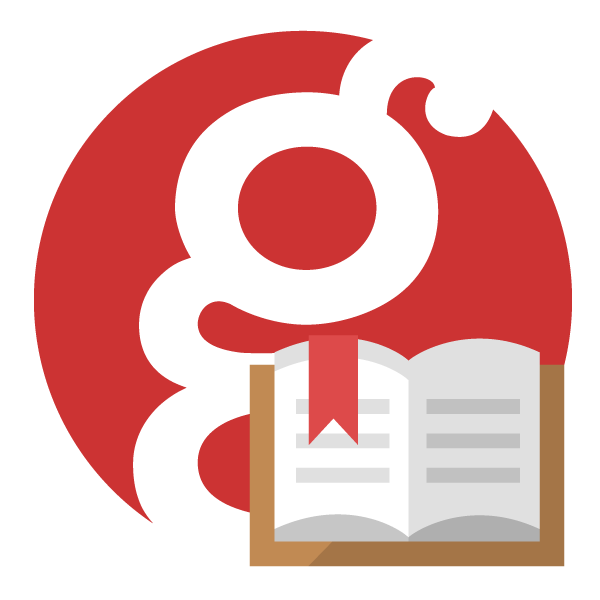📺ないので観てないのですが
🐶HKの大河 主人公がどうこうっていう✉を
最近仲良くなった人からもらったのもあって
NHK公式のインタビューとかみたら
道長役の人が●モくて苦手です。
まひろ?
誰やねん?
ていうか妄想がすごい大河なの?
視聴率悪いのわかる。
紫式部って本当に居たんだろうか?
道長の字は残ってるけど紫式部の字が残ってない。
それは知ってたけど
道長の字が残ってるのに?
紫式部の字が残ってないばかりか
本名もわからない。
色々おかしなことがありすぎる。
額が黒く塗られてるの💦
気になり過ぎる😢
この題字を揮毫した書家が気になる。
この方が道長やればよかったのに。って
思うくらいꉂ(ˊᗜˋ*)
タイトルに「光る君つ」って書いたのは
根本氏曰く【「へ」は平安古筆では「つ」とほぼ一緒】
って読んだから
「したがって、カギカッコのような「へ」は書きたくなく、
それはしっかりと先方へ伝えました。
すると、理解を示してくれ、間を取ることで落ち着きました。」
なるほど。
🐶HKの考える「ポップに」「煌びやかに」「エロティックに」ってことか!
「私の作品としての書ではなく、あくまでドラマとして印象を大事に書いてほしいという意見に則って、「ポップに」「煌びやかに」「エロティックに」など、抽象的な要望に応えるかたちで」
なんてオーダーだ![]()
書家に依頼しておきながら
根本氏の作品でなくドラマの印象でって
だから書く人の気持ちに雑音が入ったような書なんだね。
ちなみに、根本氏の書が見られるサイトがあって
お茶席の設え風になって、お菓子まで別注されていたり
とても興味深いのですが、
ここでみる淀みなく書かれている字の方が
私は全然好きです。
美しい料紙。
女性の平仮名と違う
美しい緻密で計算の行き届いた平仮名。
「平安の男の娘 紀貫之」
あんまりグッと来なかったけど
なるほど女性の書き散らしたような書にはない
男性の平仮名の魅力ってあるのかもと根本氏の平仮名みて思ふ( ..)φ
もし紫式部が居なくて
源氏物語は別人が書いていたとしたら?
すんなり納得できることが色々あるんです。
たとえば何故奈良の興福寺から
彰子に八重桜が献上されたときに行かず
その役目を伊勢の大輔に譲ったのか?
それは彼女が高階と婚姻関係にあったから
そして自分の推察では紫式部が架空の人物だったから。
伊勢大輔(いせのたいふ / いせのおおすけ、永祚元年〈989年〉? - 康平3年〈1060年〉?)は、平安時代中期の日本の女流歌人。大中臣輔親の娘。高階成順に嫁し、康資王母・筑前乳母・源兼俊母など優れた歌人を生んだ。
『百人一首』にも採られて有名な「いにしへの」の歌は、奈良から献上された八重桜を受け取る役目を、紫式部が勤める予定のところ、新参女房の伊勢大輔に譲ったことがきっかけとなり、更に藤原道長の奨めで即座に詠んだ和歌が、上東門院をはじめとする人々の賞賛を受けたものである[1]。
1 奈良時代以後、大嘗祭 (だいじょうさい) ・新嘗祭 (にいなめさい) に行われた五節の舞を中心とする宮中行事。
「五節の舞」、献上される舞姫は帝の添い寝の相手になるかどうか(紫式部出仕時代は「そういう慣習」はもうなかったようだが、『源氏物語』内では添い寝候補として認識されている可能性があるようだがそれはどうなのか)みたいな研究がある中で「紫式部自身が舞姫だったかも解釈」をぶっ込むNHKさん。
— たられば (@tarareba722) June 8, 2023
このタイミングで大嘗を持ってくる。
これは?計画的?
瀬戸内寂聴さんは 源氏物語は 女人成仏の話で
みんな光の君と交際した女性が出家してしまう。
と言っていましたが
なぜ紫式部は出家しないのでしょう?
それは存在しない人は僧籍に入れないからでは
ないでしょうか?
この話はいずれ
白河院や後白河法皇と繋がるように
思っているのですが
様々な観点から紫式部が実在していない。という視点で
検証してみたいと思う。