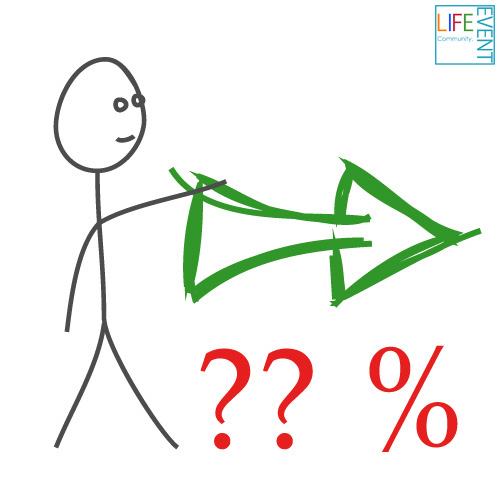
昨日のニュースリリースで、とあるネット終活サービスの会社が突如としてサービス終了を発表されていましたが、サービス開始後にプレスリリースがなされ登録したユーザーさんがそのサービスに託したメッセージは当然ながら「配達率=0%」となりますよね?
とても残念な結末ですね。。
このようなサービス打切りも含め、配達率を考えていきたいと思いますが、実際にはどの程度なんでしょうかね…?
終活サービス業界も誕生ままならない新業界。世界的にも先進国である日本、資本主義社会が高度高齢化に対してどのように推移していくのか世界中が注目しています。
これからも新しい終活ビジネスサービスが続々と登場してくると思いますが、終活ビジネスサービスに参入する新たな企業には「ゴーイング・コンサーン|going concern」が求められます。
このゴーイングコンサーンを実現するには、やはり上場でしょうか…
企業が上場するということはどういう事か…私企業から公企業に変化することです。
一般に公開された上場企業は常に厳しい監査の元に経営が進められ、四半期単位で業績報告や社内においては重要な会議が開催され、将来的なリスクアセスメントを日々行っています。
この作業を継続することにより企業を将来にわたって継続していく前提を構築していくわけです。
突然のサービス打切り→配達率ゼロパーセントではいけません。
実際のサービスでは、あらゆる方法を起業家のみなさんは考えていると思いますが、本来あるべき比率は100%です。
がっ、実際に100%はあり得ないのではないでしょうか?
郵便物を預かり、サービス申込者が死亡したことを確認しポストに投函される場合を考えてみると、一般的な年賀状やお手紙、封書など「宛先不明」で返送されることも普通にありますよね?
これと同じ現象が当然ながら終活サービスの中でも日常的に発生してきます。
10人分の手紙を託し、さすがに5人はないでしょうが8人に無事に配達されたとしても配達率は“ 80% ”です。
電子メールならなお更確率が下がってくるのではないでしょうか?
こんな感じで考えいくと打倒な配達率の標準指標値は、“ 50% ”前後と考える方が良いのかもしれませんね。
今後は、自分が使いたい終活サービスを選ぶ際には、この50%をひとつの基準値としてサービスを選定していければいいですね!!
続きは次回…
♂ELAMICA