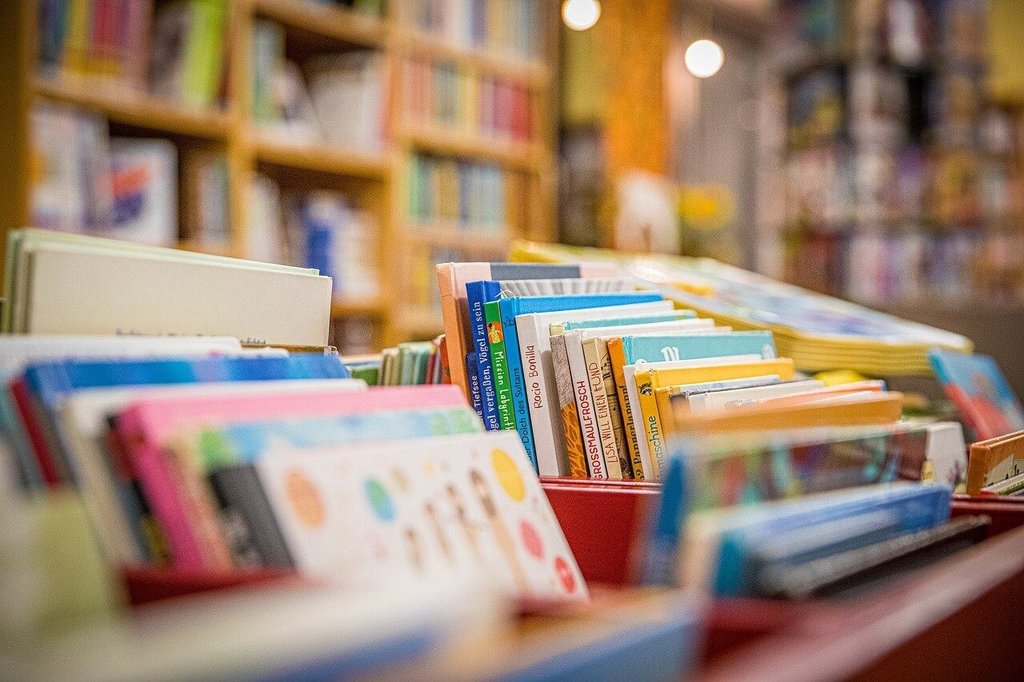司書免許取得への道
こんにちは!
司書資格は、短大で取れる!高卒で大丈夫!のようなことを書かれていることもありますが…
ちょっと違います。
(応募では、なぜか短大卒程度の枠で募集がなされています)
それ、
実は昔の制度のままなんです
現在では、司書資格は四年制大学でないと取得できません。
短大では取得できませんし、高卒や短大卒で司書をしたいのであれば図書館司書補助という仕事を探すことが近道です。
私は通信制大学で、司書免許を取得しました。
大学によっては4年間で司書資格を取る事が出来たり、短期集中講座を行ったりするところもあります。
それぞれどのように取得するのか、
見ていきましょう。
ちなみに…私はダブルスクールで取得したので、どのようにして勉強して取得したのかは、下記の記事を見てみて下さいo(_ _*)o
大学で取得
1番簡単なのが、通っている大学で取得することです。
通学している大学の教育課程で、司書資格が取れる講義を選択していくと、大学卒業とともに司書の資格を取る事ができます。
短期集中講座で取得
夏休みなど長期休暇を利用して集中講座を行っている大学もあります。
大学によって在学歴等が必要で、申込期間にその大学に申し込みをして講座を受講します。
約1週間から10日程大学に通い、司書資格を取得するための講義を受けます。
その間の宿泊費や食費等が掛かるため、貯金必須です![]()
通信制大学で取得する
司書課程があり、通信の学科がある大学なら通信制大学で取得するのもありです。
仕事をしながら勉強することが出来るので、社会人になったけど司書の免許を取りたい!と思った方にはオススメです。
既に大学卒業している、在学中だけど司書課程がないという方には、司書課程のみを通信制大学で履修する科目等履修生という学び方があります。
私の場合…テキストやらパソコン環境も自分で整備しました。
大学によっては、大学のパソコンを貸してくれるところもありました。(今はコロナの影響で無理かもですけど )
)
どれにしろ、レポートや実習で司書としての教養や知識を学んでいきます。
個人的には、『情報探索』と『レファレンスサービス』という科目が好きでした。
(今も好きです )
)
この2つは、実際の課題に対して、近くの図書館に行って、言葉を探したり、その言葉の出典を探したり、いくつかの二次資料(事典、辞典)にあたってどんどん調べていくことです。
図書館司書の勉強は専門用語も多かったので、図書館用語辞典のヘビーユーザーになりましたけどね(笑)
でも、図書館が好き!という人は面白いと思います。