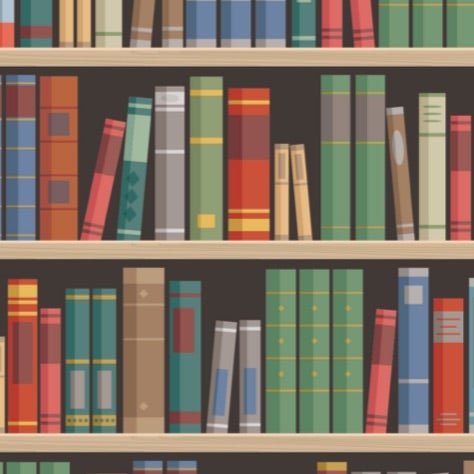はじめに
みなさん、こんにちは。本野鳥子です。今回は、マキァヴェッリの「マキアヴェッリ全集1」についてです。「北欧神話と伝説」については、今しばらくお待ちください。
フィレンツェの栄華と衰退をじかに見つめた一人の政府高官、のちに政治思想家とされるマキァヴェッリは、何を思っていたのでしょうか。
「マキアヴェッリ全集1」ニッコロ・マキァヴェッリ(筑摩書房)
「君主論」
これについては、先日読んだばかりなこともあるので、以前この作品について書いた記事をご参照いただこう。
https://ameblo.jp/librariantoriko/entry-12598132352.html
「戦争の技術」
この巻では、傭兵として生計を立ててきたファブリツィオと若き青年たちの、軍事についての議論で成り立っている。いかにして、戦争に勝つかが、とにかくひたすら語られているのだ。
題名からして「戦争の技術」とある通り、本当にどこでも通用しそうな、理論を究めた作品だった。このようなことは、歴史を読んでいても分からない。
常々、戦争が、架空歴史小説なり、ファンタジーなり、あるいは歴史小説の中で登場する中で、どのように展開するかはずっと気になっていたことだった。たとえば伏兵を潜ませた、とか、騎兵を有効活用して敵の側面を突いた、などと書かれていても、では戦争は実際にどのように展開するのか、はよく分からない。大槍兵がどこにいて、盾はどのように使われ、では指揮官は軍隊の中ではどこにいて指示を出すのか、ということを聞かれても、答えに窮するのだ。
だから、この「戦争の技術」は本当に参考になった。専門家でも何でもないので、これがどれくらい正しいのかは私にはよく分からないが、司令官たちを主人公に据えることの多い物語からでは、見えてこないものがよく分かった。第一列、第二列、第三列と兵を並べるとき、後ろに行くにつれて、兵の密度を薄くしていくことで、前列が後退できる余地を作る、というのは、その代表と言って良いかもしれない。
また、古代の人々の想像力にも感嘆した。ファブリツィオの語り、マキァヴェッリの筆と来たら、兵がみるみる動いていって、頭の中に図を描こうとしても、とうてい追い切れるものではない。映像で可視化することがいとも容易くなってきた現代人である私では、文章から想像するのは不可能と言って良いほどだった。各巻末についている図がなければ、困惑の度合いを深めるばかりだったに違いない。
実際に戦争で何が起こっているのか、その一端が分かる作品だった。
「カストルッチョ・カストカラーニ伝」
この伝記—物語、と表現した方が正しいのかもしれないが—では、カストルッチョ・カストカラーニという人物の生涯が語られている。巻末の解説によれば、創作によるところの多い伝記であり、古代の英雄譚のパターンを踏襲するものであるとのことだが、それにも納得した。いかにも、マキァヴェッリが「君主論」で述べるような君主像の投影、といった雰囲気である。
英雄というのは、えてしてその大きな意志を達することなく、倒れることの多い人々であろう。また、もう少し長生きしていれば、英雄と呼ばれたかもしれない人も、歴史上の中には多々いたに違いない。このカストルッチョ・カストカラーニもまた、そのような人々の一人だった。それが、本当に惜しまれる。歴史というのは、無数の人々の生と、そして死の集合体であり、またその一つが欠けただけでも、今の歴史はなかったであろう。カストルッチョも、また生きていれば、歴史が違った様相を呈していたのかもしれない、と思った。
マキァヴェッリの筆というのは、人間の本質を突き、どこにおいても通用する理論なのではないか、と思わせるところがある。どんな物語であっても、たとえ異世界を舞台とするファンタジーであっても、彼の理論からは逃れられないのかもしれない。そう考えると、ふと笑みがこぼれた。
おわりに
ということで、マキァヴェッリ全集は、これから少しずつ読み進めていきたいと思います。早く読める部類の本に含まれないことは確実でして、多少の不安もありますが、読破できたらいいな、と思っています。ファンタジーを見る視点が、また一つ増えるようです。
さて、次回はまだ未定です。今読んでいる「緋文字(ホーソーン)」「北欧神話と伝説」「青の王(廣島礼子)」の中から一冊、と思っています。それでは、最後までご覧くださりありがとうございました! またのお越しをお待ちしております。