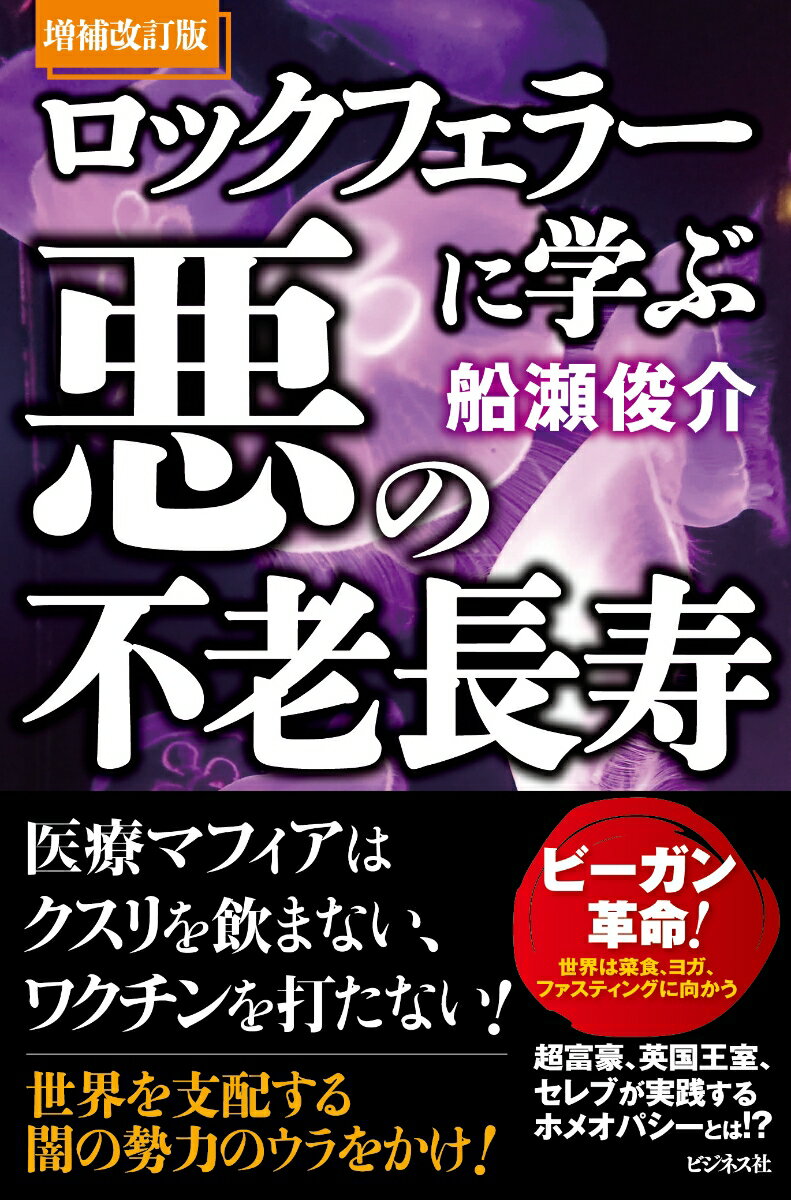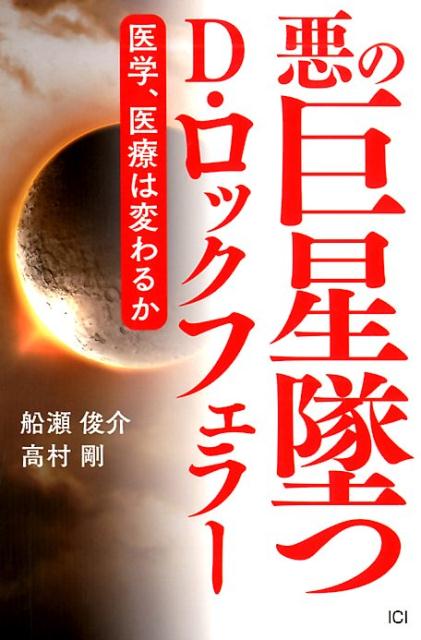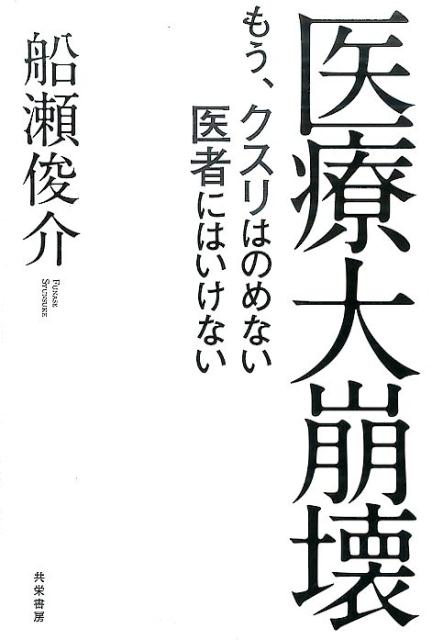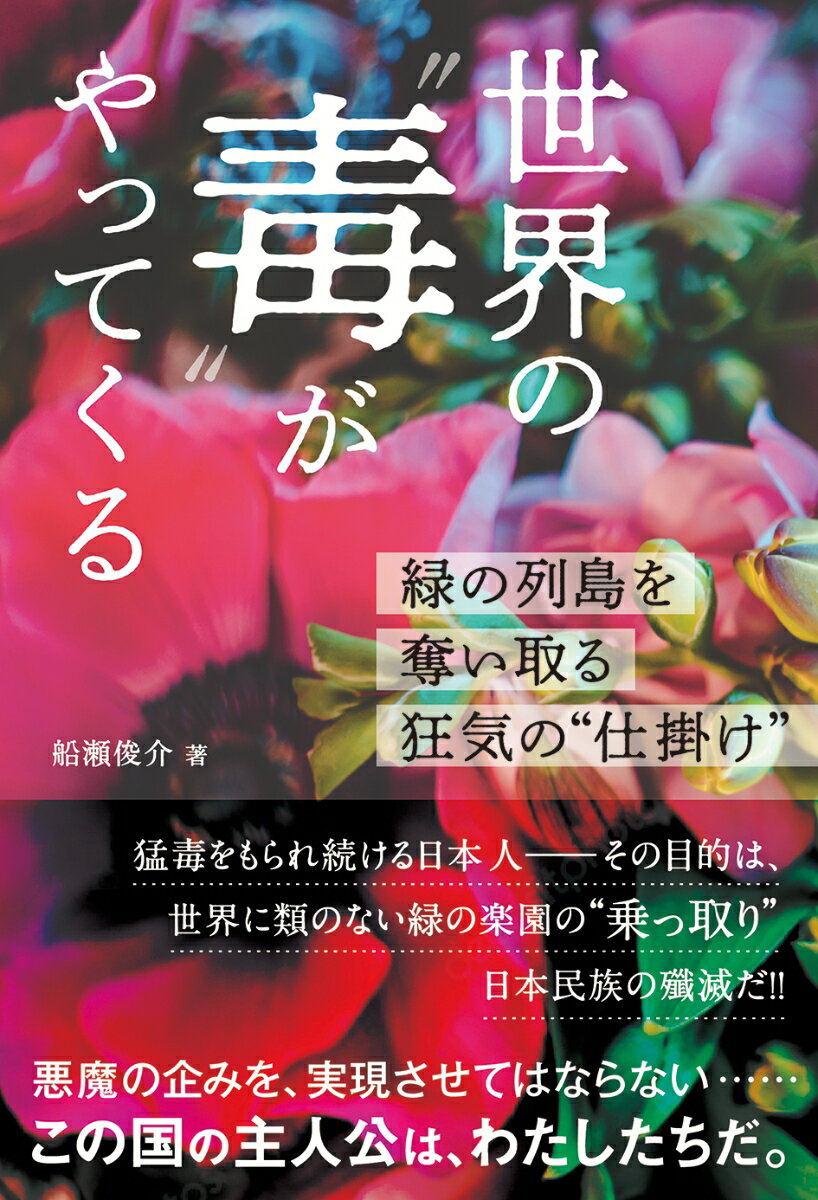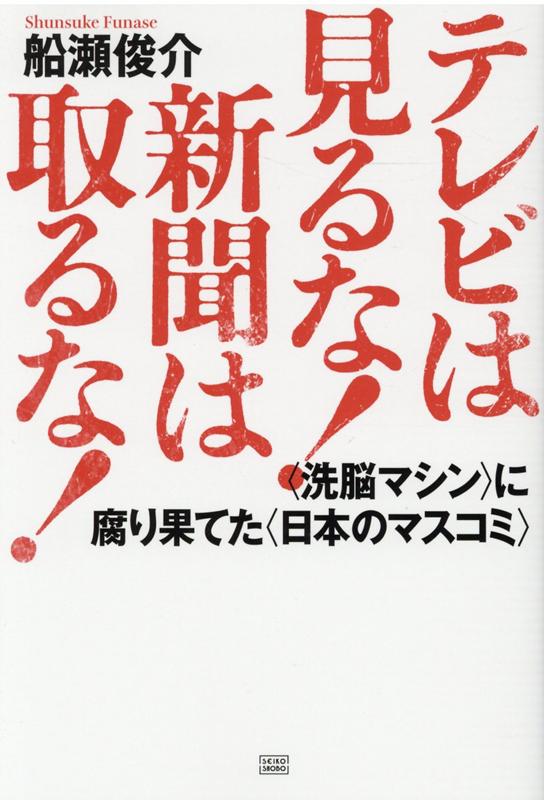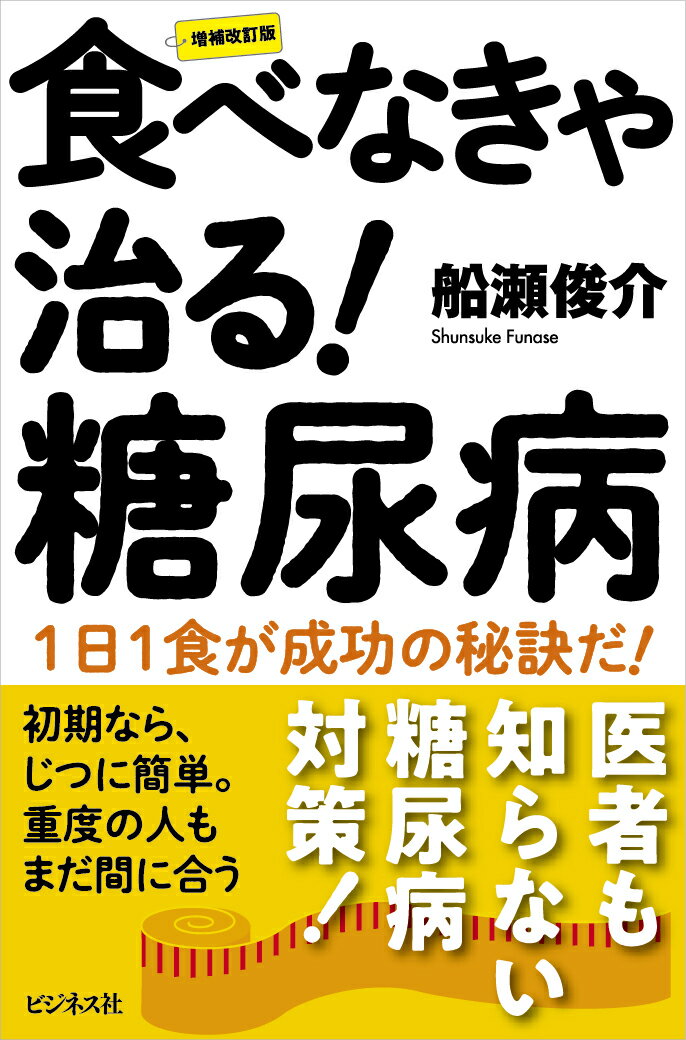⚛️序章|なぜ医師は“病気の原因”をあまり学ばないのか
あなたは「医師は何でも知っている」と思っていませんか? とくに、病気の原因や予防法についても、当然詳しく学んでいるだろうと。
けれど現実は少し違います。
医学部では、病気の診断や治療法は徹底的に学びますが、「なぜその病気になったのか」という根本原因については、ほとんど時間が割かれません。 栄養や生活習慣、環境要因といった“病気の土台”に関わる部分は、カリキュラムの片隅に少しだけ。
これは医師の怠慢ではなく、医学教育そのものの構造によるものです。
では、なぜそうなったのか。 それを知るには、100年以上前のアメリカで起きた出来事に目を向ける必要があります。 その時代に、現代の医学の形がほぼ出来上がったのです。
次の章では、その背景に迫ります。 なぜ「薬を使うこと」が医療の中心になり、病気の原因や予防が置き去りにされたのか──その答えは、歴史の中にあります。
⚛️第1章|100年前のアメリカで起きた医学の大転換
19世紀後半から20世紀初頭、アメリカは産業革命の波に乗って急速に発展していました。 石油産業は巨万の富を生み、その中心にロックフェラー財閥がありました。 石油からは燃料だけでなく、合成化学品や医薬品の原料も作られるようになり、製薬産業が勢いを増していきます。
当時のアメリカには、今よりずっと多様な医療が存在していました。 西洋医学だけでなく、自然療法、ホメオパシー、植物療法、カイロプラクティック、鍼灸…多くの学校があり、医師免許の形態もバラバラ。 食事や生活改善、ハーブなどを中心に、薬をほとんど使わない治療も珍しくありませんでした。
しかし1900年代に入ると、こうした多様性が「非効率」「非科学的」と見なされるようになります。 背景には、科学的な基準で医学教育を統一しようという動きと、それを支える産業界の思惑がありました。 科学的基準という響きは魅力的ですが、その定義は「薬物や外科手術を前提にした西洋医学」だけを指していました。
1910年、アメリカで一つのレポートが発表されます。 それが、医学教育のあり方を根本から変えることになる「フレクスナー・レポート」です。 この報告書が、薬中心の現代医学を世界の標準にするきっかけとなりました。
⚛️第2章|フレクスナー・レポートの衝撃
1910年、カーネギー財団の支援を受けた教育改革者、エイブラハム・フレクスナーが「フレクスナー・レポート」を発表しました。 目的は、アメリカとカナダの医学教育の質を調査し、標準化すること。 このレポートは「科学的でない医学教育を一掃する」という旗印のもと、医学部の評価と改革案をまとめたものでした。
しかし“科学的”という基準は、西洋医学の中でも薬物療法と外科手術を柱とする近代医学だけを指していました。
食事療法や自然療法、ハーブや手技療法を教える学校は「非科学的」とされ、閉鎖か統合を迫られます。 その結果、当時全米に存在していた100校以上の医学部の多くが姿を消しました。
この動きの背後には、石油化学産業と製薬産業の急成長があります。 石油を原料とする合成医薬品が次々と開発され、それを支える医療体系が求められていました。 薬を中心に据えたカリキュラムは、製薬業界と医学部、そして資金を提供する財団の利害が一致する形で広がっていきます。
こうして、医学教育は診断と薬・手術による治療に特化し、栄養や生活習慣、環境要因といった「病気の土台」については、ほとんど教えられなくなりました。 この構造はその後100年以上経った今も、世界中の医学部に色濃く残っています。
⚛️第3章|薬中心の医療体系の定着
フレクスナー・レポートの影響で、アメリカの医学部は一気に薬物療法と外科手術を中心としたカリキュラムへ統一されました。 これにより、卒業する医師たちはみな同じ方向性の教育を受けることになります。 つまり、病気を見つけ、薬か手術で対応する──これが現代医学の標準となったのです。
製薬産業は急速に発展し、医療と産業界は強く結びつきます。 新しい薬が開発されれば、それを使うためのガイドラインや診断基準が整備され、医師は最新の治療としてそれを採用します。
この流れの中で、食事や生活習慣、環境改善による予防は、教育でも臨床現場でも脇役に追いやられました。
薬物療法が悪いというわけではありません。 感染症や外科手術の成功率が飛躍的に向上したのは事実です。
しかし同時に、慢性疾患や生活習慣病といった「長い年月をかけて進行する病気」に対しては、原因の土台に踏み込む視点が薄れてしまいました。
こうして、医学部で栄養や生活習慣、環境要因をほとんど学ばない構造が完成しました。 そしてこの構造は、戦後、日本にもそのまま輸入されることになります。
⚛️第4章|日本への輸入と予防医学の置き去り
第二次世界大戦後、日本はアメリカの強い影響下に置かれました。 その一環として、医学教育の制度やカリキュラムも大幅に再編されます。 モデルとなったのは、すでにフレクスナー・レポートの影響を受けたアメリカ型の医学教育でした。
この新しいカリキュラムは、診断と薬物・外科による治療を中心に構築されています。
栄養学は必修ではなく、わずかな単位で基礎的な内容にとどまり、生活習慣や環境要因について体系的に学ぶ機会はほぼありませんでした。 つまり、日本の医師は学生時代から「原因よりも治療を重視する」枠組みの中で育つことになります。
その結果、慢性疾患や生活習慣病、自己免疫疾患など、原因に複数の環境要因が絡む病気に対しては、薬での症状コントロールが主な選択肢となりました。 予防や生活改善は補助的な扱いにとどまり、患者自身が病気の背景を理解し、日常生活を変えていくためのサポートはほとんど整いませんでした。
この構造は、現在の医療制度や保険診療の仕組みにも色濃く影響しています。 医師が悪いのではなく、教育と制度がそうなっている──それを知ることが、現代医療をより良く活用するための第一歩です。
⚛️第5章|もう一つの視点──選択肢を広げるために
歴史をたどれば、現代医学が薬と手術を中心に発展してきた背景は明らかです。 それを批判する声もありますが、感染症や外科治療の分野で現代医学が救ってきた命は計り知れません。 大切なのは、「どちらが正しいか」という二元論ではなく、医療の成り立ちを知った上で自分に合った選択をできるようにすることです。
作家・船瀬俊介さんをはじめ、多くの自然療法家や統合医療の実践者は、この歴史的背景を指摘し、予防や生活改善の重要性を訴えてきました。 彼らの主張のすべてに賛同する必要はありませんが、「病気は環境や生活の影響を大きく受ける」という視点は、現代医療だけでは見落とされがちな部分です。
私たちが知っておくべきなのは、病気の治療には薬や手術が有効な場面がある一方で、病気の土台をつくる生活や環境を整えることも同じくらい重要だということです。
歴史を知れば、「なぜ医学部で原因や予防を深く学ばないのか」という疑問にも答えが見えてきます。
現代医学と生活改善──どちらか一方ではなく、両方を使いこなす視点こそが、これからの時代に求められる医療の形ではないでしょうか。
⚛️最終章|知ることで、守れる健康がある
私たちは、医療の成り立ちや医学教育の背景についてほとんど教わることなく暮らしています。 病気になれば病院へ行き、薬や手術で治す──それが当たり前だと思ってきました。
けれど、その教育や制度は歴史的な選択の積み重ねであり、決して唯一の正解ではありません。 100年前のアメリカで形づくられた「薬中心の医療体系」が、戦後の日本にもそのまま導入された。 その流れを知れば、「なぜ医師も病気の原因や予防をあまり学ばないのか」という疑問も解けます。
病名や症状にだけ目を奪われず、「なぜこの病気になったのか」を考えること。 その視点があれば、あなたは自分の健康を、そして未来を守るための選択肢を確実に増やすことができます。
こうした“病気の土台”に目を向け、生活や環境から立て直す医療の考え方は、1990年代にアメリカで体系化されました。 それが**機能性医学(Functional Medicine)**です。 現代医学の限界を感じた医師や研究者たちが、薬や手術だけでは改善しきれない慢性疾患に対して、栄養、生活習慣、環境、ストレス管理など多方面からアプローチする体系を築きました。
この視点は、フレクスナー・レポート以降に置き去りにされてきた“病気の原因”へのアプローチを、現代に取り戻す試みでもあります。 最新医療の強みと、機能性医学の土台づくり──その両方を使いこなすことが、これからの健康戦略の鍵になります。